ハノイ・モイ・ウィークエンドは、この問題を明らかにするために、米国のエネルギー分野で研修を受け、成功を収めた環境経済・気候変動研究センター(CECCS - VUSTA)の事務局長、ダオ・マン・トリ氏と対談した。
環境経済・気候変動研究センター(CECCS - VUSTA)のエグゼクティブディレクター、ダオ・マン・トリ師。
- 米国カスケード市の地熱プロジェクトの技術コンサルタントとして、ASEAN国際エネルギー環境会議で2年連続(2023年、2024年)「最優秀スピーカー」の称号を獲得された経歴を持つあなたは、このプロジェクトについて詳しく教えていただけますか?
米国アイダホ州カスケード市における地熱発電(地中熱利用)プロジェクトの開発支援は、私にとって忘れられない経験となりました。カスケード市は人口約2,800人の僻地に位置し、移行のための資源も乏しい地域です(アイダホ州の住民の所得は下位レベル)。一方、地熱発電には多額の費用がかかり、財源と高度な専門知識が求められます。州および連邦レベルの政策はいずれも包括的な目標を掲げていますが、草の根レベルでは、政策のメリットを最大限活用するための経験が不足しています。この現状を踏まえ、私たちの研究チームは、連邦資源管理機関、政策執行機関、市当局、そして特に日々エネルギーを利用する人々と直接連携しました。明確なメリットを目の当たりにした彼らは、長年の課題解決に協力し、貢献する用意ができていました。カスケード市は、 政府からの初期投資により、プロジェクト立ち上げに必要な1,100万ドルを調達する予定です。
このプロジェクトは後に、米国エネルギー省主催の地熱発電コンペティションで準優勝を果たしました。しかし、私にとってさらに大きな喜びは、この地域の人々が厳しい冬を乗り越え、持続可能な経済発展を遂げるための豊富で安定したエネルギー源を得られたことです。この経験を通して、エネルギー転換は誰一人取り残さない公平性の要素があって初めて持続可能なものとなることを改めて実感しました。
カスケードはベトナムのいくつかの地域と多くの共通点があることに気付きました。ですから、このアプローチを故郷で実践できればと思っています。そして、最も貴重な教訓は、成功するには人々の理解と支援が必要だということです。よく言われるように、「人がいなければ耐えるのは百倍容易だが、人がいれば成し遂げるのは千倍困難だ」のです。この経験を通して、ベトナムでもこのようなプロジェクトを実施したいという思いが私の中に燃え上がりました。
- では、あなたの意見では、ベトナムの現在のエネルギー転換の道筋をどのようにまとめることができますか?
まず第一に、国民に周知徹底し、各レベルおよび関係部門の当局と団結し、2045年までのビジョンを含む2030年までのベトナム国家エネルギー開発戦略の方向性に関する2020年2月11日付政治局決議第55-NQ/TW号を理解し、実行する決意を固める必要があると考えます。
ベトナムにおけるエネルギー転換の目標、ビジョン、そして解決策は、決議の中で明確に定義されています。「国家のエネルギー安全保障の確保は、社会経済発展の基盤であり、重要な前提である」「再生可能エネルギー源、新エネルギー、クリーンエネルギーの開発、徹底的かつ効果的な利用を優先する。国内の化石燃料源の開発と合理的な利用に努め、国家エネルギー備蓄の安定化、調整、需要確保という目標に重点を置く」。その核心は、エネルギーを経済的かつ効果的に利用し、環境を保護することが国家政策であり、「生存、発展、あるいは死」の問題であることを明確に認識することです。
多くの課題に直面しているにもかかわらず、ベトナムは蓄積された経験と国際的な支援のおかげで「絶好の機会」に恵まれています。エネルギー転換は、増大する電力需要を満たすだけでなく、ベトナムが世界の「新しい工場」となるための条件を整えることにもつながります。しかも、それは「グリーンファクトリー」でなければなりません。国益、エネルギー安全保障、そして人々の生活は、不変の目標です。持続可能性、適正なコスト、それぞれの地域への適合性、創造性の促進をモットーとし、流行にとらわれないやり方で進めていきます。
当面は、石油・ガス、電力などの専門法体系を整備し、輸出入、市場、土地、資源に関する政策を連携させ、突破口を開くメカニズムを構築し、エネルギーに関する国家基準と規制を整備する必要がある。同時に、管理職や科学技術専門家の育成と再教育に重点を置く必要がある。最も重要なのは、集団利益、業界利益、地域利益といった思考様式を排除することである。
ベトナムのエネルギー転換に関する私の研究は、プリンストン大学(米国)、マサチューセッツ工科大学(MIT)、清華大学(中国)など、多くの主要なフォーラムで注目され、議論されてきました。その現実から、私は、海外のモデルを機械的に適用するのではなく、国際的な経験をどのように選択し、ローカライズして、ベトナムの現実に適した方法を構築するかを知る必要があるという結論に至りました。
屋上太陽光発電の開発は、個人の電力節約の傾向であるだけでなく、ハノイ市のグリーン都市開発方針の一部でもあります。
- 先ほど主要な大学や、これまで訪問・協力してきた国々についてお話いただきましたが、この分野において、これらの国々からどのようなことを学び、どのような経験を積むことができるとお考えですか?
各国のアプローチは異なりますが、移行を成功させるための共通点がいくつかあります。第一に、政策は将来を見据え、明確な財源を伴わなければなりません。実用性と必要なリソースがなければ、どんなに優れたモデルやアイデアであっても、単なる「絵に描いた餅」に過ぎません。第二に、電気自動車、AI、データセンターといった新たなトレンドに対応できるインフラを整備する必要があります。電力網、分散型電源を含むバックアップ電源も、負荷クラスターと電源クラスターに基づいて計画し、最先端の予測モデルと密接に連携させる必要があります。第三に、教育・研修における官民連携を促進し、学生時代からエンジニア、エネルギー管理者、データ専門家からなるチームを育成する必要があります。そして最後に、トレンドに追随したり、インフラの能力を超える目標を設定したりすることは避けるべきです。一部の国における手続きや接続性のボトルネックから得られた教訓は、組織規律、データの透明性、そして部門横断的な連携が技術と同様に重要であることを改めて認識させてくれます。
- 今後のエネルギー転換についてどのような提言がありますか?
- 私の考えでは、まず喫緊の課題は、洋上風力、太陽光、小水力、バイオマスなどを活用し、電源の多様化を図り、自立性を高めることです。これは、各地域の自然的優位性を活かしつつ、需要エリアに応じて電力を配分する方法です。同時に、柔軟な電源と蓄電ソリューションを開発し、システムの安定運用を確保する必要があります。リスクを軽減するために、一つの技術に「集中」することは避けるべきです。次に、電力網のアップグレードが必要です。主要な送電プロジェクトに注力し、給電指令をデジタル化し、損失を削減する必要があります。電力網は「背骨」であり、背骨が強固である場合にのみ、組織全体が迅速に機能し、経済全体の生産性を高めることができます。第三に、炭素市場や大規模負荷向けの直接電力購入など、クリーン電力を促進する経済メカニズムを実践し、企業が「グリーン」への移行による明確なメリットを実感できるようにする必要があります。最後に、人材とデータです。システムモデリング、コストシナリオ分析、国・企業・大学の連携、計測の標準化、排出量報告、リアルタイムデータ運用に投資する必要があります。ベトナムには才能豊かな若者がたくさんいます。彼らに現実的な問題、実用的なツール、そして優れた教師を与えれば、自国ですぐに知識を習得できると信じています。メカニズムが透明化され、データが信頼できるようになれば、市場の信頼は高まり、安価な資本が自然と標準的なプロジェクトを見つけることができるでしょう。私は、依存を避けるために自立を目指し、統合を加速させるためには、この2つが両立する必要があると考えています。
どうもありがとうございます!
出典: https://hanoimoi.vn/chuyen-dich-nang-luong-chia-khoa-cho-an-ninh-quoc-gia-va-phat-trien-ben-vung-716076.html





































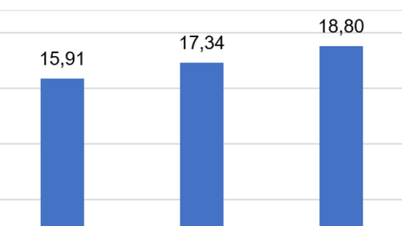






































































コメント (0)