バイン・トロは、クアンガイ省ダックウイ村ダック・スアン村のヌン族によって代々受け継がれてきた伝統料理です。見た目は凝っておらず、他の餅のように具材も入っていませんが、独特の風味、手の込んだ調理法、そして非常に独特な食文化が魅力です。
ダクスアン村の年配のルアン・ティ・ベイさんによると、バイン・トロは旧正月、7月15日、ドアン・ゴ祭といった重要な祝日や祭りに欠かせない料理だそうです。カオバン省の新経済政策によってヌン族の人々がこの地に移住した際、バイン・トロも中央高地へと移り住み、コミュニティの文化生活の一部となりました。
バイン・トロが他のもち米の餅と異なるのは、加工に使われる特別な材料にあります。それは、ヌン族が「マック・テット」と呼ぶ木の薪から作られる灰水です。マック・テットは赤い芯と小さな黄色い実を持つ木質の木で、薬用植物とされています。この木を燃やして灰にした後、人々は籠で灰を圧縮し、その上にゆっくりと水を注ぎます。灰層を通過した水は淡い黄色になり、独特の香りがします。これは多くの経験を必要とする工程です。灰を丁寧に圧縮しなかったり、他の種類の薪を使用したりすると、灰水は香りと色の点で基準を満たさなくなります。
ベイさんは、灰水が美味しくなるのは、熟練した職人の技があってこそだと語る。普通の薪で作ると、味気なく、香りも色もつかない。丁寧に濾過した後、灰水を濾過水と適切な割合で混ぜ、少量の塩を加えて沸騰させ、冷ます。各家庭の経験によって、混合比率は異なる。灰水が濃すぎると、ケーキは硬くて食べにくくなり、薄すぎると、独特の風味が薄まってしまう。
餅を作るのに使用するもち米は、通常の米を混ぜず、純粋なもち米でなければなりません。餅職人は、もち米を2~3回洗った後、ろ過した灰水に3~6時間浸します。浸漬の過程で、米粒は徐々に黄色くなり、柔らかく粘り気が増していきます。これは、茹でた後の餅の色と粘り気を決める重要な工程です。
ヌン族の灰餅作りのもう一つの特徴は、餅を包むのにトンボの葉を使うことです。トンボの葉は森の端に自生していることが多く、早朝、まだ柔らかく、日焼けしたり巻かれたりしていないうちに摘み取られます。摘み取った葉は洗って熱湯で湯通しすることで柔軟性が増し、包みやすくなります。ベイさんによると、トンボの葉だけが灰餅独特の風味を保てるとのこと。トンボやバナナの葉で包んでしまうと、灰餅は灰水の香りを失い、本来の風味を失ってしまいます。
包んだ後、餅は冷水の入った鍋に入れられます。底に沈んだ餅は茹でられますが、浮いた餅は生焼けやムラが多いので、取っておきます。葦餅は、1~2時間茹でるだけで済む普通の餅とは異なります。ヌン族は通常、葦餅を17時間茹でます。この工程中は、絶対に新しい水を加えてはいけません。新しい水を加えると、餅のコクが失われ、味が変わってしまいます。
餅をくり抜いた後、職人は自然に水を切らせます。葉を剥がすと、餅は独特の黄金色を呈します。餡を抜いても、灰餅は柔らかくもちもちとした食感で、爽やかでほのかなナッツの風味と脂っこい味わいが楽しめます。もち米と混ざり合った灰水のほのかな香りは、他の餅では代用できない洗練された味わいを生み出します。
ベイさんは、長年ケーキ作りをしてきたが、バイン・トロの魅力が薄れたことは一度もないと付け加えた。祝日や旧正月には、どんなに忙しくても、村のヌン族の家族は材料を用意して何十個ものケーキを作り、それを子供や孫たちと分かち合い、先祖に捧げる。バイン・トロは伝統料理であるだけでなく、地域社会の結束と民族のアイデンティティを守る象徴でもあるのだ。
ダク・スアン村のヌン族にとって、バイン・トロは単なる料理の一部ではなく、故郷との繋がり、記憶、そして文化的な美しさでもあります。ヤシの葉の一枚一枚、黄色いもち米の一粒一粒を通して、この小さなケーキは、この地の人々の日常生活の中で伝統的価値観を守り、育んできた物語を物語っています。
出典: https://baolamdong.vn/deo-thom-banh-tro-389185.html




![[写真] 国家功績展を通して見るベトナム人民軍の栄光の80年の歩み](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/29/99ca4109cd594a45849a3afed749d46d)
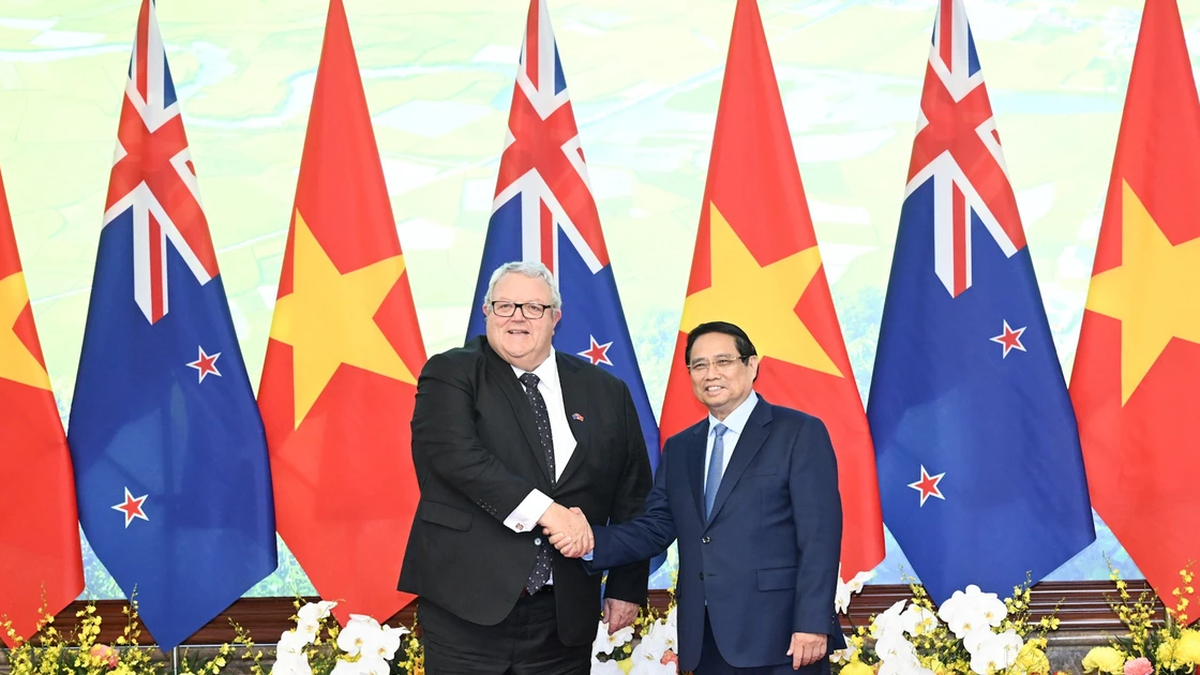
![[写真] ハノイは9月2日の建国80周年記念式典に備えている](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/29/c838ac82931a4ab9ba58119b5e2c5ffe)
![[写真] ト・ラム書記長がファン・ディン・トラック同志に党員45年記念バッジを授与](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/28/e2f08c400e504e38ac694bc6142ac331)





![[モーショングラフィックス] 教育訓練開発の飛躍的進歩に関する決議](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/29/0cbd539b47f845e1b59e90f16ff0406b)










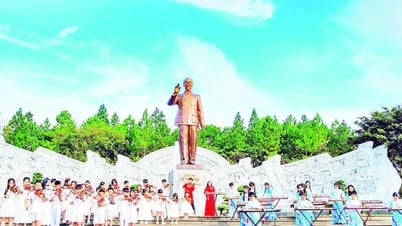




![[写真] 9月2日のフランス建国記念日に、黄色い星が描かれた赤い旗がはためく](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/28/f6fc12215220488bb859230b86b9cc12)

































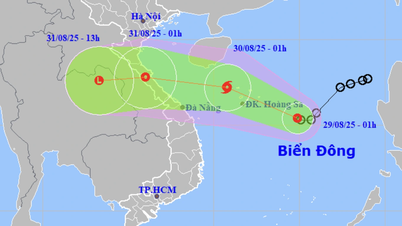






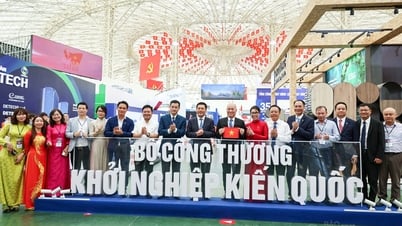








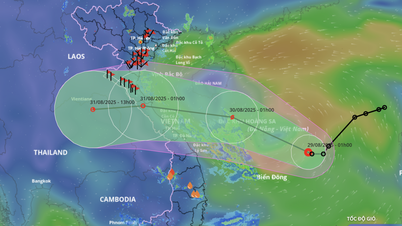




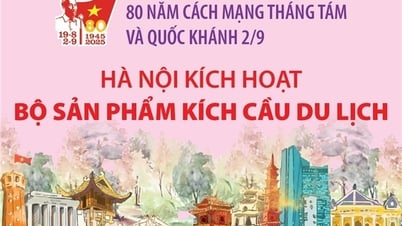














コメント (0)