国会代表らは、「国家が投資した資金があるところには必ずその資金を管理・監視する仕組みがなければならない」という原則に基づき、投資資本が50%未満の企業と国有企業が投資した企業であるF2、F3企業にまで管理・監督の範囲を拡大することを提案した。
第8回会議のプログラムを継続し、11月29日の午後、国会はホールでプロジェクトについて議論した。 企業における国家資本の管理および投資に関する法律。
代表ホアン・ヴァン・クオン氏( ハノイ代表団)によると、国有企業は現在、多額の資本と資産を保有しているものの、民間企業に比べると活動が活発ではなく、効率も低いとのこと。
このような状況が生じる理由の一つは、国有企業の現在の管理体制が依然として不適切であり、業務が重複し、制約されていることにある。
国が投資するところはどこでもその資金を管理・監視する仕組みがなければならないという原則に基づき、代表は、投資資本が50%未満の企業と国営企業が投資する企業であるF2企業とF3企業の両方について、対象を拡大し、管理と監督に原則的な要件を課す必要があると提案した。
特に、国有資本の代表者については、これに応じて改正する必要がある。所有者の代表機関は、複数の人物からなるグループではなく、資本管理を担当する代表者を任命または雇用する必要がある。代表者は、目標と計画を任命・実行するだけでなく、組織の組織化や基準に基づいた選抜など、完全な権限を持つ必要がある。
上記の見解に同意し、 ハティン省代表団のブイ・ティ・クイン・トー氏は、国資が49%、残りが5人の主要株主に分配され、各株主が10%未満の株式を保有する株式会社の例を挙げました。このように国資が支配的な立場にある場合、規制がなければ、誰が管理、実施、監視の責任を負うのかが不明確になります。
女性代表は、これらの企業における国家資本がどのように管理・使用されるのか、資本投資による利益がどのように扱われるのか、違反行為はどのように処罰されるのか疑問に思った。
そのため、代表は、国有資本が50%未満の企業に対する管理範囲を拡大し、国が資金の流れを監視・管理し、持分比率に基づいてのみ管理するという「国有資金管理原則」を規定する必要があると提言した。そうすることで初めて、財務管理原則が確保される。
国株主の役割の明確化
ホアン・ヴァン・クオン議員は、法案草案へのコメントの中で、第5条に規定されている「企業に投資された国有資本は当該企業の法定資本となる」という原則を高く評価した。この原則に基づき、100%国有企業を含む企業における資本の管理と使用は、予算資本のように管理されるのではなく、企業の権利となる。
したがって、現在、公共投資法第25条から第32条に規定されている投資決定権限に関する企業の資本投資権限の分割に関する規定を廃止し、この権利を企業の自己決定権に戻す必要がある。
「国が企業に資本を投下した後、国は投下資本に応じた株式を保有する株主となるという規定を追加する必要がある。株主として、所有者の代表機関は企業における株主権を行使するために代表者を任命または雇用しなければならない」とクオン議員は提案した。

その時、代表者はその企業に投資された国家資本を管理する責任を負い、同時に国家がその企業に達成してほしい目標を遂行しなければなりません。
所有者代表機関は、企業が使用した資本金の割合に応じて資本保全目標、資本増加目標、利益控除目標など企業が実施すべき計画目標を指定して代表者に任務を割り当てます。
割り当てられたタスクを実行するには、企業のオーナー代表者が、機構を組織し、コーポレートガバナンスの役職に適切な人材を配置する完全な権限を持っている必要があり、そうして初めて企業は効果的に運営されます。
企業の投資資本が適正な目的で管理・使用されることを保証し、リスクを防止するために、所有者代表機関は、企業の活動および所有者代表の活動を監視する独立した監督部門を任命する必要があります。
このような考え方に基づき、クオン代表は、第 13 条の人事規則は、所有機関の代表者と監督部門の任命の原則に関する要件のみを規定するべきであり、企業の管理職の任命は、国の基準と規則に従って企業の所有者代表者によって決定されるべきだと述べた。
利益分配に関して、ハノイ代表団は、規則案による現在の利益分配の仕組みでは、報酬基金と福祉基金に積み立てるために最大3か月分の給与しか控除できないため、企業が健全な事業を行い、高い利益を上げることを奨励しないだろうとコメントした。
企業の効率が悪いのに自社の給与が高い場合、ボーナスや福利厚生に充てる利益がなく、従業員の月収は依然として高いままです。逆に、企業自体が給与を低く設定し、業績が好調で利益率が高い場合、たとえ3か月分の給与をボーナスに充てることを許可したとしても、従業員の月収は依然として低いままです。
「利益分配は、まず資本増強、予算配分、開発積立金の積み立て、積立金の積み立てといった、割り当てられた目標と計画の遂行に充てられるべきです。残りの部分は従業員に分配され、従業員は結果に応じた利益を享受することになります。残りの利益が多ければ、従業員の享受する利益は増え、利益が少なければ、従業員の享受する利益は減ります」と、代表者は自らの見解を明確に述べた。
ソース



![[写真] 第1回政府党大会の厳粛な開会](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/13/1760337945186_ndo_br_img-0787-jpg.webp)








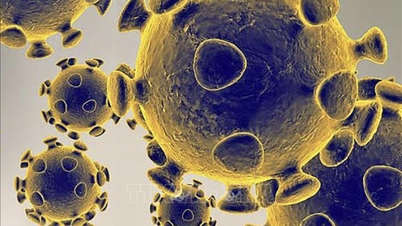


































































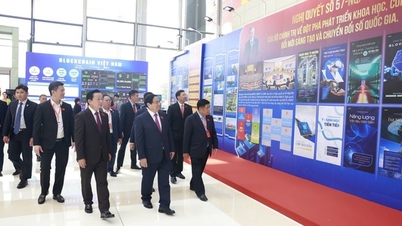


























コメント (0)