ワールド&ベトナム紙は、国連人口基金(UNFPA)が最近発表した「世界人口の現状2023」報告書を記念して、UNFPAアジア太平洋地域事務局長ビョルン・アンダーソン氏の記事を紹介しています。
 |
| 国連人口基金(UNFPA)アジア太平洋地域事務局長、ビョルン・アンダーソン氏。(出典:UNFPA) |
2022年11月に世界人口は80億人に到達しました。これは人類にとって重要な節目であり、医療、教育、科学、社会経済発展の進歩を示すものです。
この節目を迎えるにあたり、新型コロナウイルス感染症のパンデミックから気候危機、脆弱な経済、紛争、食糧不足、そして大規模な人口移動に至るまで、世界が重なり合う複数の課題に直面していることへの懸念が高まっています。こうした状況下、人口変化への恐怖と不安は、女性が子供を持つかどうか、いつ、何人持つかを選択する権利に影響を与えています。
今年の国連人口基金(UNFPA)の世界人口の現状報告書は、人口規模、人口変化、人口構造、出生率の影響に関する懸念から生じる「人口不安」に取り組んでいます。
新たな報告書は、こうした数字のみに焦点を当てた懸念が、時に出生率抑制を目的とした強制的な措置につながることを明確に示している。子どもの数、あるいは産むとすれば何人産むか、そしてどのくらいの間隔をあけて産むべきかといった決定権を侵害するこうした行為は、誤った方向への導きであり、社会の真の問題を見逃す危険性がある。
アジア太平洋地域は広大で、人口動態も多様です。人口減少に見舞われている国もあれば、人口増加に見舞われている国もあります。そして、ほとんどの国で人口増加は鈍化し、高齢者の割合が高まった社会を形成しています。
いずれにせよ、出生率の変動や人口規模の変化は、人口動態の領域を超えた政策の見直しを必要とします。しかし、こうした政策はすべて、ジェンダー平等の促進と女性・女児のエンパワーメントの進展を加速させることに重点を置く必要があります。
世界中の経験から、出生率を低下させたり上昇させたりする計画、特に出産を奨励または抑制する具体的な政策は、効果はわずかで、場合によっては有害であったことが明らかになっています。政策は、人口が「多すぎる」か「少なすぎる」かという単純な見方を超えなければなりません。
気候変動、経済問題、人口の高齢化など、多くの現実的な懸念に対処するには、出生率を操作しようとする政策ではなく、賢明で証拠に基づいた人権に基づいた政策が必要です。
ジェンダー平等の推進は、人口動態の変化に対処し、回復力と持続可能性に富んだ社会を築くための鍵となります。女性をエンパワーし、自らの身体と人生について意思決定する能力を伸ばす機会を提供することは、女性自身、その家族、そして社会の繁栄を支えることになります。
女児の教育を保障し、女児と女性が性と生殖に関する健康と権利に関する情報やサービスにアクセスできるようにし、社会のあらゆる分野に完全かつ平等に参加できるようにすることで、女性の人生のさまざまな段階に投資する必要がある。
 |
| 世界人口が80億人に達したことは、人類にとって重要な節目です。(出典:国連人口基金) |
さらに、政府は、個人が出産を希望する状況を実現できるよう、家族に優しい政策(例えば、父親休暇制度、質の高い保育、柔軟な勤務形態など)を制度化し、性と生殖に関する保健サービスを含む国民皆保険制度(ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ)を確保する必要がある。また、政府は年金制度を強化し、活動的で健康的な高齢化を促進する必要がある。
少女や女性が人生の様々な段階で、生殖に関する選択も含め、自らの意思決定や選択を行えるよう権限を与えられる「ライフサイクル」アプローチを採用することで、少女や女性は人生の夢や希望を追求し、社会の経済発展を促進することができるようになります。
では、アジア太平洋地域はジェンダー平等と女性の性と生殖に関する健康権(セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス・ライツ)の実現にどう取り組むべきでしょうか?多くの成果は上がっていますが、まだ多くの課題が残されています。1億3000万人以上の女性が、依然として家族計画サービスや妊娠計画に必要な情報にアクセスできていません。また、世界の18億人の青少年の半数以上がアジア太平洋地域に暮らしており、その大半は、自らの身体について十分な情報に基づいた決定を下せるようになるための包括的な性教育を受ける機会を依然として得られていません。親密なパートナーによる女性への身体的暴力や性的暴力の発生率は依然として高いままです。
今こそ、1994年の国際人口・開発会議でなされた公約の進捗を加速すべき時である。同会議では、生殖に関する健康と権利、女性のエンパワーメント、男女平等を含む人権とあらゆる個人の尊厳を開発の中心として認める行動計画が採択された。
人口問題への取り組みを含め、開発政策は権利に基づくものでなければなりません。人口動態の変化に耐え、繁栄できる社会を築く上で、女性と女児の権利と選択を最優先に据えるよう、共に取り組んでいきましょう。
 |
| ビョルン・アンダーソン氏がバクカン省のコミューン保健所を訪問。(出典:国連人口基金) |
[広告2]
ソース




![[写真] ファム・ミン・チン首相が地方との政府オンライン会議を主宰](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/5/264793cfb4404c63a701d235ff43e1bd)






























































![[ビデオ] ペトロベトナム50周年記念式典の概要](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/4/abe133bdb8114793a16d4fe3e5bd0f12)

![[動画] ラム事務総長がペトロベトナムに8つの黄金の言葉を授与:「先駆者 - 優秀 - 持続可能 - グローバル」](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/23/c2fdb48863e846cfa9fb8e6ea9cf44e7)


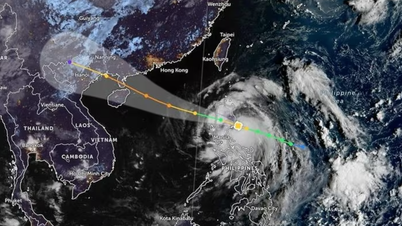








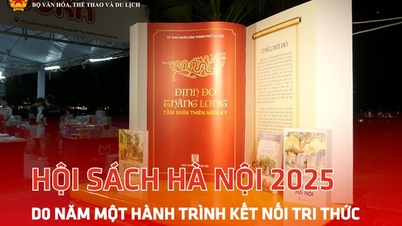







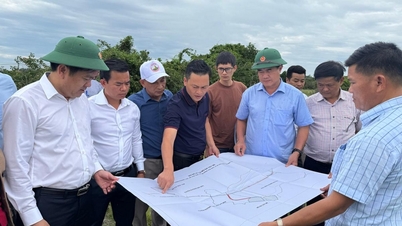

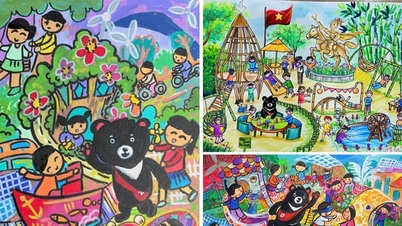














コメント (0)