父は笑いました。「わらの煙のいい香りだよ、坊や。まるで手作りのご飯の香りだ」。母は台所で、はっきりとした声で言いました。「いい香りがするなら、たくさん食べなさい。でないと明日畑に行くときにお腹が空いて泣くことになるわよ」。家族全員が大きな声で笑いました。その笑い声は太陽のように輝き、貧しい家に暖かさを感じさせました。
そしてある日、その笑い声はまるで陶器の椀がタイル張りの床にぶつかる音のように消え去った。その日の午後、ハンが学校から鞄を持って戻ると、ドアは大きく開いていて、父親は庭の真ん中にひざまずき、震える手で木のように動かずに横たわる女性を抱きしめていた。「おい、起きろ!」ハンは駆け寄った。「ママ!」という呼びかけは喉の奥で砕け散った。屋根の影が突然伸び、10歳の子供の叫び声を飲み込んだ。
葬儀の後、父は口数の少ない男になった。毎日午後、仕事から帰ると、肩に自分の体よりも大きな米束を担ぎ、歩くたびに道に埃を巻き上げていた。ハンは米の炊き方、庭の掃き方、米のとぎ方、火起こし方を覚えた。台所で母の手が届かない火は、まるで息を切らしたように揺らめいていた。しかし、丘の中腹にある小さな家には、父が息子を励ます声が聞こえていた。「息子よ、勉強しなさい。貧乏だけど、勉強で貧乏になるなよ」

イラスト:AI
時が流れ、ハンは成長し、白いシャツの背中は父と娘の汗でびっしょりになった。暑い昼、ハンは校門前のホウオウボクの木の下に自転車を停め、鞄を開けて父がバナナの葉で包んでくれたご飯を取り出した。魚醤に浸したご飯に、数本の白菜の漬物が添えられ、新米のように甘く美味しかった。夕方になると、灯油ランプが蝶の羽のように揺れ、父はうとうとと眠り、ハンは熱心に数学の問題を解いていた。二人の姿は、風から身を守るように寄り添うつがいのスズメのように、壁にきれいに描かれていた。
高校3年生の試験を終え、ハンはこれで終わりだと思った。勉強を続けるためのお金はどこから捻出するのだろう? 父は「働きなさい」と言った。まるで無関心なように軽やかな声だった。しかし、心の中では言葉が鳴り続けていた。村役場が彼の名前を呼び、近所の人々が励まし、教育大学への入学許可書が家に届いた。父は書類を握りしめ、真昼の太陽のように曇った瞳が、突然きらめいた。父は喜びながらも、クローバーのように心配していた。「もしよかったら、行って。まだ手が2本あるんだから」 ハンは父の手を握り、「行って、それから戻ってきて」と言った。
地方でハンは勉強に励み、奨学金も受けた。田舎娘のハンは髪を高く束ね、シャツを丁寧に洗い、月明かりに照らされた運河の水のように瞳を輝かせていた。昼夜を問わず多くの男子生徒が彼女に注目していた。しかし、ハンが疲れている時、突然雨が降った時、借りた部屋の電気が止まった時…いつもそばにいてくれたのはアンだった。アンは大したことは言わず、ただ玄関の下に立って、そっと声をかけた。「お腹が空いたでしょ? 外に出て食べなさい」。風に逆らう一対の稲のように、愛は芽生えた。二人は卒業後に結婚することを約束した。
卒業後、ハンは故郷に戻って教師になりたいと願った。新任教師の給料はそれほど高くなかったが、そこの教師たちは給料ではなく、生徒たちの目に輝く言葉で評価していた。毎日午後、ハンは赤い堤防を自転車で渡った。アオザイはコウノトリの羽のようにひらひらと揺れ、父親との夕食を思うと心が軽やかだった。
ある晩、父親はハンを呼び戻した。その声はためらいがちで、めったに聞かれないほどだった。
ハン…もう大人だし、仕事もあるし、そんなに心配しなくていいよ。これ…何て言えばいいのか分からない。
「この家には二人しかいない。君が言わないなら、誰に言うんだ?」ハンは微笑んでティーポットをテーブルに置いた。
お父さんは…下の階に住むナムさんの娘、リンちゃんに恋してるの。お父さんはずっとリンちゃんを家に連れて帰ろうと考えていたんだけど、あなたが勉強しているんじゃないかって心配してたの…今、あなたが教師になったから、お父さんはあなたの意見を聞きたいの。
ハンは驚愕した。
リン?彼女はあなたより数歳年上で…独身で子供もいる…あなたと彼女は…相性が良いですか?それとも…ただ…彼女が可哀想なだけ?
父は目を細め、目尻のしわに光がきらめいた。
―そう思わないで。君が学生だった頃、リンはよく訪ねてきて、僕が病気の時にお粥を持ってきてくれた。人生では、相性が良かろうが悪かろうが、優しくしなきゃいけない。僕は年寄りだから、誰かに寄り添ってもらえれば、空虚感は薄れる。もし君が僕を愛してくれるなら、心から愛してくれるといいな。
ハンは黙って、柵の外の虫の鳴き声に耳を澄ませていた。当初の不快感は、長年シングルファーザーとして子供たちを育ててきたことへの罪悪感と混ざり合い、彼女は静かに言った。
- 構いません。ただ、優しくて、分かち合える人を選んでほしいです。
結婚式は簡素だった。リンは、恥ずかしがり屋の頬のように、真っ赤なブーゲンビリアの花束を抱えて帰宅した。三人で食事をする間、スプーンが静かにカチンと鳴る音が響いた。リンは、魚醤のボウルからシャツを天日干しするまで、小さなことにも気を配り、よく微笑んでいた。ハンは次第に恥ずかしさを紛らわせるようになった。父の幸せそうな姿を見て、彼女の心は木の葉のように軽やかになった。
そしてハンの結婚式の日がやってきた。白いドレスをまとった花嫁は、父親が自作の花のクリップを彼女の髪につけると、目に涙を浮かべた。父親は娘を抱きしめ、肩を風に吹かれたように少し震わせた。
― 今はもういないけれど、ご主人の家族を自分の家族のように大切にしてください。誰にも笑いを届けてあげてください。遠く離れていても、食べることと寝ることを忘れないで。幸せは…自分の手で大切に築き上げていくもの。お父さんは…いつもそばにいることはできないのよ。
ハンは微笑んだ。温かい涙が頬を伝った。父は荒れた手でそれを拭ったが、藁の煙の匂いが漂っていた。
週明けのある朝、ハンが授業の準備をしていると電話が鳴った。電話の向こうから聞こえてきたリンの声は、まるで風に吹かれたかのように途切れ途切れだった。
- ハン…お父さん…
電話が彼の手から滑り落ち、床に落ちた。アンは外から駆け込み、倒れている妻を抱きしめた。「ただいま。帰ろう!」
ハンはひざまずいて父親を抱きしめた。父親の顔は、まるでやるべきことをすべてやり終えたかのように穏やかだった。ハンは泣き叫んだ。
お父さん…どうして急にいなくなったの?そして私は…
アンは妻の肩を抱きながらゆっくりとした声で言った。
落ち着いて聞いて。ずっとあなたに隠していたことがあるの。
アンさんによると、数ヶ月前、トゥアンさんは脳腫瘍が見つかり、医師から余命いくばくもないと告げられたという。ちょうどその頃、アンさんの父親も重度の腎不全を患い、同じ病室に入院していた。間もなく義理の両親となる二人の老年は、偶然にも病室で出会った。トゥアンさんはその話を聞いて、数日後、アンさんにこう言った。「彼を助けさせてください。私ももう長く生きられません!私の体の一部をください…娘がまた笑顔でいられるように」
アンは両手を握りしめながら言った。
― 受け入れる勇気がなかった。でも、お医者さんはまだ可能性はあるって言った。お父様はすごく決意が固かったから。あなたには言わないようにって。お父様は、あなたが結婚する時には、稲の花のように瑞々しいままであってほしいと願って、あなたを私のところに送ってくれたのよ…どうか、お父様が私を愛してくれたように、私をも愛してください。お父様との約束を守って、突然の苦しみを与えてしまって、ごめんなさい。
ハンは胸に水が溢れ出し、心臓を襲い、窒息しそうになった。結婚式当日に起こった奇妙な出来事――父親がいつもより長く彼女を見つめ、いつもより長く指示を出した――が、今や扉を開ける鍵となった。彼女はしゃっくりをしながら頭を下げ、申し訳なさと後悔、そして感覚が麻痺するほどの感謝の気持ちでいっぱいだった。
彼女はリンの方を向いた。
- おばさん…お父さんのこと知ってる?どうして…お父さんが…いつお父さんと結婚したの?
リンはハンの手を引っ張った。彼女の手は淹れたての緑茶のように暖かかった。
― 分かっています。でも、私は愛と義務感から結婚したんです。苦しみを恐れてはいませんでした。以前…私は間違いを犯しました。私が妊娠したと知ると、人々は去っていきました。ある時、自殺しようと川岸に行きました。その夜、月は出ず、水は墨のように黒くなっていました。あなたのお父さんが通りかかり、川岸でひらひらと揺れている私のシャツを見て、駆け下りてきて私を抱き上げ、病院に連れて行ってくれました。そして、私が一生忘れない言葉を言いました。「子供に罪はない」。そして、父親の名前を名乗るように頼みました…そうすれば、将来子供が学校に行く時、後悔することはないでしょう。感謝しています。彼と一緒に暮らしていると、安心します。彼があなたをとても愛していることは分かっています。私はあなたと私たちの家族を守るためにここにいます。
リンの物語は、揺らめくろうそくのように、揺らめき、そしてしっかりと立ち上がった。ハンは叔母を抱きしめた。過去の思いが洪水の泥のように消え去っていくことに、罪悪感を覚えた。居間では、アンが静かに祭壇を整え、新しい水の入ったコップを持ってきた。三人の影は、まるで同じ木の三つの枝のように、寄り添っていた。
葬儀は簡素だった。上と下の両町の人々が立ち寄り、線香に火を灯した。老人が庭に立ち、風を見つめながら、半分は生者へ、半分は死者へ語りかけた。「彼は立派な人生を送りました。今は安らかに逝かれました…」
ハンは線香を手に持ち、肖像画の隣に立った。その写真は卒業式の日に父親が急いで撮ったものだった。白いシャツに銀髪、斜めに笑みを浮かべ、目尻には赤い土の跡が浮かんでいる。線香の煙が、彼女の記憶にある乾いた藁の匂いと混ざり合い、突然、奇妙な香りが家中に広がった。ハンは幼い頃、父親が言った言葉を思い出した。「藁の煙は、家庭で炊いたご飯の匂いだよ」。今、藁の煙は、人の愛の匂いを漂わせている。
父の葬儀の日、太陽はそれほど暑くなかった。雲は薄く、風は優しく吹いていた。まるで紳士の眠りを邪魔するのを恐れているかのように。人々は埃まみれの足取りで歩き、詠唱はかすかに響き、ヤシの木の上でかくれんぼをする子供たちの声が今もこだましていた。どこかで牛が長い「モー」という音を立て、胸に鋭い痛みを感じた。ハンは墓に線香をあげ、囁いた。
お父さん、僕は良い人生を送るよ。お父さんが言ってくれたように、キッチンを暖かくして、笑顔を絶やさないよ。
リンはハンの肩に手を置き、彼女の隣に立った。アンは少し後ろに下がり、二人の女性を互いに寄りかからせた。まるで水路の両岸が水を抱きしめるように。
時が過ぎた。午前中、ハンは教室へ行き、生徒たちが暗唱する声が鳥のように響き渡った。午後、彼女は家に立ち寄り、父親の好物であるスズキの煮込み料理を作った。祭壇の香炉はいつも赤い炭火で赤く染まっていた。リンは時折、子供をブーゲンビリアの屋台に連れて行き、「お姉ちゃん」と呼ぶように教えた。子供は「お姉ちゃん」と鳴いた。その声はまるで蝶がハンの肩に舞い降りたようで、彼女の心を軽くした。
ある時、市内の病院から家族へ感謝の手紙が届きました。そこにはシンプルながらも温かい言葉が書かれていました。「トゥアンさんの体の一部のおかげで、また一人の命が助かりました。家族に支えとなる柱が一つ増えました。」ハンさんは手紙を握りしめ、まるで自分の髪に触れるかのように父の手を感じました。そして手紙を祭壇に運び、静かに祈りました。
「分かりました、お父さん。与えることは失うことじゃない。与えることは保つこと。自分の最高の部分を相手の中に保っておくことよ」
その夜、竹垣の向こうから月が昇り、庭の真ん中にミルクカップのように明るく輝いていた。ハンは父親の竹椅子を縁側に引き出し、畑の蛙の鳴き声に耳を傾けながら座っていた。アンは熱いお茶を二杯持ってきてくれた。リンは家の明かりを消し、三人の影が地面に横たわった。川岸から風が吹き込み、刈りたての稲穂の藁の香りが漂ってきた。祭壇の線香の煙は、夜が更けたにもかかわらず、誰かが肩にかけた一筋の陽光のように、細い帯となっていた。
ハンは空を見上げて微笑んだ。どこかで、お父さんもきっと微笑んでいるだろう。そして、藁の煙の匂い――手料理の匂い、肩の匂い――は、この小さな家に、受け継がれた優しさの中に、お父さんのように互いを愛し合う心の中に、永遠に残るだろう。

出典: https://thanhnien.vn/vet-nang-tren-bo-vai-cha-truyen-ngan-du-thi-cua-duong-thi-my-nhan-18525101512380187.htm




![[写真] ト・ラム書記長がハノイで第18回党大会(任期2025~2030年)に出席](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/16/1760581023342_cover-0367-jpg.webp)







































![[動画] トリップアドバイザーがニンビンの多くの有名観光スポットを称賛](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/16/1760574721908_vinh-danh-ninh-binh-7368-jpg.webp)
















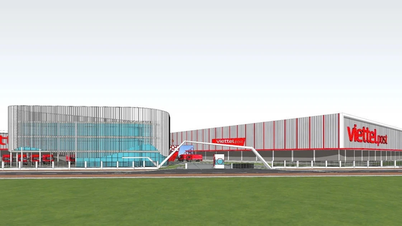















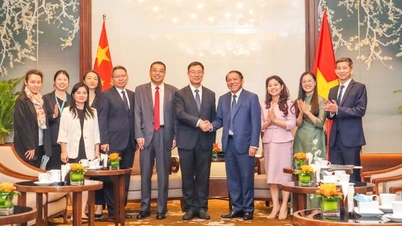































コメント (0)