
最初の9ヶ月間の輸出額は83.3億米ドルに達し、前年同期比15.5%増加しました。この結果は、幾多の変動を経て水産業界が着実に回復していることを反映しているだけでなく、不安定な世界市場において企業が迅速に適応する能力も示しています。
製品構成では、エビが9月に約4億1,000万米ドルの売上高を記録し、引き続き首位を維持しました。これにより、9ヶ月間の総売上高は33億8,000万米ドルを超え、前年同期比20.3%増加しました。この成長の勢いは、主に米国、日本、EUにおける安定した需要と、地域市場における受注の拡大に支えられています。
パンガシウスも9月に売上高が約1億9,100万米ドルに達し、前年同期比11%増と、大きな注目を集めました。9月末までにパンガシウスの輸出額は16億米ドルを超え、前年同期比約10%増となりました。中国、米国、そして一部の中東諸国の市場における力強い回復は、ベトナム産パンガシウスの世界水産物市場における地位強化に貢献しています。
海水魚、イカ、タコ製品群も目覚ましい成長を記録しました。最初の9ヶ月間で、その他の海水魚の輸出額は16億1,000万米ドル(18.5%増)、イカとタコは約5億5,000万米ドル(18.7%増)に達しました。特に貝類は30%以上の増加を記録し、1億9,200万米ドルに達しました。一方、マグロは3.2%の微減となり、7億500万米ドルとなりました。これは、海水魚分野における競争の激化を反映しています。
市場面では、中国(香港を含む)は引き続き明るい兆しを見せています。9月の輸出は若干減少したものの、9ヶ月累計では32.1%増の17億6000万米ドルに達し、最大の市場シェアを占めています。この市場は、高い消費需要と物流コストの優位性により魅力的です。一方、米国市場では、ベトナム企業は反ダンピング税や海洋哺乳類保護法(MMPA)の厳格な規制による圧力にさらされており、参入が困難になっています。
一方、日本とEUは着実な成長の勢いを維持しました。最初の9ヶ月間の日本への輸出額は12億7,000万米ドル(15.6%増)、EU市場は8億8,500万米ドル(13.3%増)に達しました。特に、韓国は9月に約50%の増加を記録し、成長が加速する市場として浮上しました。最初の9ヶ月間の総売上高は6億4,500万米ドルに達し、同時期比で13%以上増加しました。ASEANと中東も潜在的なニッチ市場となりました。ASEANへの輸出額は5億3,600万米ドル(23.3%増)、中東への輸出額は2億9,500万米ドル(7.6%増)に達し、9月だけでも50%以上増加しました。
Vasepの副事務局長であるLe Hang氏は、上記の印象的な数字は企業の適応力と柔軟な事業転換能力を示していると分析しました。多くの企業は、新たな税制政策や技術的障壁が施行される前の時期に輸出を拡大するとともに、積極的に市場構造改革を進め、アジアへの輸出比率を高め、従来市場における市場シェアを強化しました。付加価値加工製品への投資、ますます厳格化する品質基準とトレーサビリティへの対応といった傾向も、特に中高級品分野において、業界の競争力維持に貢献しています。
しかし、今後の道のりは依然として困難に満ちています。米国をはじめとする一部の市場における反ダンピング税や相互税は、利益率をますます狭めています。厳しい漁獲規制を定めた海洋哺乳類保護法は、水産物に大きな圧力をかけています。また、EUのIUU(違法・無規制)漁業に対する「イエローカード」は依然として撤廃されておらず、ベトナム産水産物の評判と輸出コストに直接的な影響を与えています。インド、タイ、インドネシア、エクアドルといった地域諸国からの競争圧力は、特にエビやパンガシウス製品において高まっており、これも企業にとって大きな課題となっています。

専門家は、水産物業界が成長の勢いを維持するためには、市場の動向と貿易政策を積極的に監視し、新たな障壁が現れた際には迅速に戦略を調整する必要があると指摘しています。同時に、米国、EU、日本といった主要市場を維持しながら、ASEAN、中東、そして競争の少ないニッチ市場における機会の開拓を促進することで、市場構造を再構築していく必要があります。
製品の多様化と付加価値の向上は、特に世界中の消費者が高品質で持続可能かつ安全な製品を重視する傾向が強まる中で、ベトナム水産物が持続的に競争力を維持していくための重要な要素です。加えて、業界はイノベーションを推進し、養殖と加工に技術を適用し、高級グルメチャネルやeコマースを通じて国家ブランドを強化することが、長期的な競争力強化の鍵となります。
出典: https://baotintuc.vn/kinh-te/xuat-khau-thuy-san-9-thang-tang-155-20251006153801947.htm



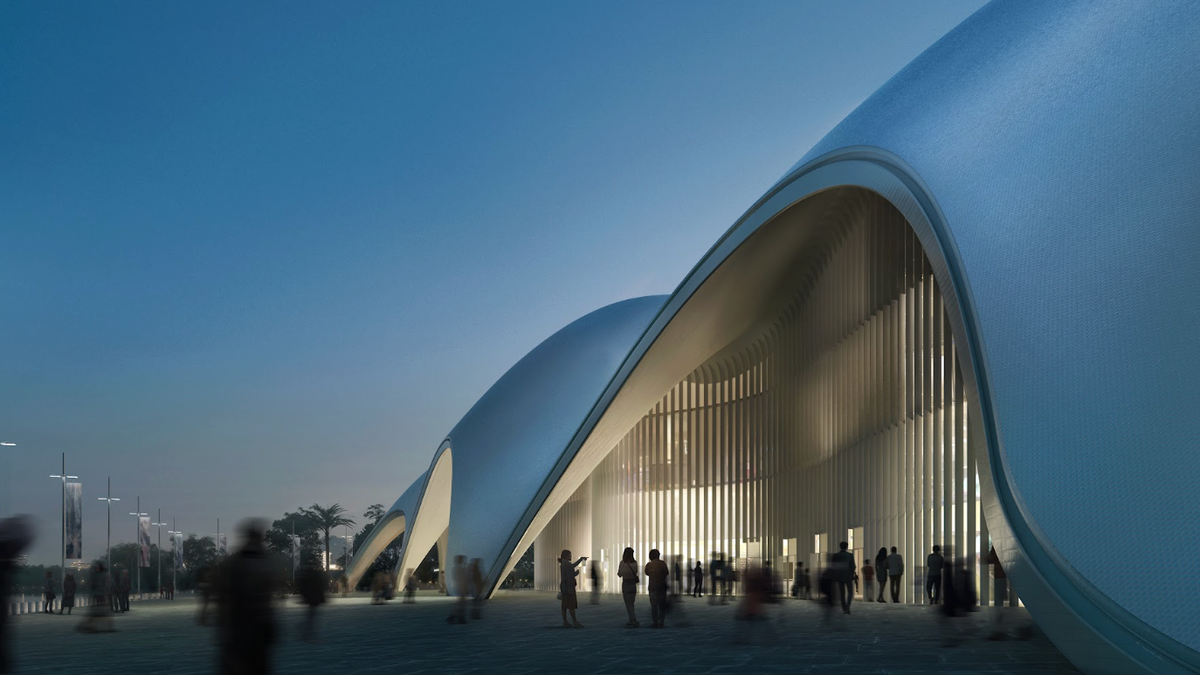


































































































コメント (0)