
子どもたちが「フィード・ザ・オーシャン」のシャコ放流セッションに参加 - 写真:ササチーム
このプロジェクトは、ダナンのササ海洋生物救助センター(ササチーム)の創設者である海洋学者ル・チエン氏によって始められ、この地に住む多くのメンバーの強力な支援を受けて、フーコック島( キエンザン省)をプロジェクトの出発点として選びました。
ミン・ヴォ氏
海に対する考え方を変える
フーコック島の海に卵を抱えたカニ200匹を放流する旅の途中、ダイバーたちはカニの入ったカゴをそっと海に沈めました。すると母ガニがすぐに海に出て、砂に隠れました。すると魚たちがすぐに群がり、落ちたカニの卵を拾い集めました。「Feed the Ocean」のメンバーはこうして海に「餌」を与えているのです。
現在フーコック島在住のプロジェクトメンバー、ミン・ヴォ氏は、多くの科学的報告書や現地調査から、フーコック島が沿岸漁業資源を深刻に減少させていることが示されていると述べた。「フィード・ザ・オーシャン」は、卵を抱えている在来種や繁殖期の雌を海に放流することで、この地域で過剰に漁獲されている種の回復に貢献する。
このプロジェクトで再放流される魚種には、タコ、シャコ、サメ、アカエイ、タツノオトシゴ、ウナギ、ハタ、シードラゴン、シャコガイなどが含まれます。彼らはフーコック島の養殖場で稚魚を購入するか、ササ・チームのソンチャ半島( ダナン)にある養殖場から孵化した稚魚を輸送し、海に放流します。「このキャンペーンは5年間実施されます。約2ヶ月で、フィード・ザ・オーシャンは約20万匹の稚魚をフーコック島の海に放流しました」とミン・ヴォー氏は述べています。
多くの人にとって、これはほんの一滴、あるいは少し狂気じみてさえ見えるかもしれません。しかし、メンバーたちは、少なくとも自分たちの子供たちだけでなく、今の世代にも自然、特に海に親しみ、理解を深める機会を提供できるよう、行動を起こしようとしていると述べています。
「真珠島」との愛
Feed the OceanプロジェクトのメンバーのほとんどはSasaチーム出身で、その中心メンバーは現在、真珠のような島、フーコック島に住んでいます。ミン・ヴォー氏は生粋の都会人ですが、「フーコック島に恋をした」ため、海辺に定住し、そこで生計を立てることを選びました。
フランスで学んだ後、ホーチミン市に戻り、事業が安定するまで何年もかけて事業を築き、第一子を出産したミン・ヴォー一家は、3年前にフーコック島への移住を決意しました。海を愛し、スキューバダイビングも趣味とするミン・ヴォーは、フーコック島が山や森、そして美しい海に囲まれていることを心から愛していると語ります。
夫婦には現在6歳の子供がおり、もうすぐ2人目の子供が生まれます。子供たちにはフーコックの海と美しい自然に触れさせてあげたいと願っています。それは子供にとってとても良いことだからです。プロジェクトに参加する他のメンバーと同様に、ミン・ヴォーさんも、たとえ限られた力であっても、フーコックの未来のために、この土地の恵みを守り続けていきたいと考えています。
フランス留学時代からダイビングに情熱を注いできたミン・ヴォーは、フーコック島に移住した今もその習慣を続けています。生き物を海に返すたびに、ミン・ヴォーはダイビングチームに直接参加し、海中の適切な生息地へと連れて行きます。
「海洋科学者のル・チエン氏の指導の下、私たちはプロジェクトの効果を最大限に高めるために科学的にプロジェクトを進めています。また、より多くの人々にプロジェクトを知ってもらい、協力してもらうために、地域住民に魚の購入への協力を呼びかけ、募金キャンペーンも行っています」とミン・ヴォ氏は語った。
海をもっと理解し、愛するために
漁法は依然として主にトロール漁船と電撃漁法が用いられています。漁師は大きな魚から小さな魚へと漁獲するため、魚種の回復は不可能です。プロジェクトでは、このような無差別な漁業が続けば、どれだけ放流しても足りないだろうと予測しています。
毎回の救助活動の様子を記録し、Sasa Team Marine Animals Rescueのファンページで共有しています。一部の救助活動には、若者や学生のボランティアも参加しています。カニや魚を海に放つ前に、学生たちは海の生き物の生態について学び、海への理解を深め、愛着を深めています。
 水資源の再生のために海洋生物を放流する
水資源の再生のために海洋生物を放流する[広告2]
ソース


![[写真] 朝鮮労働党創立80周年記念パレードに書記長が出席](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/11/1760150039564_vna-potal-tong-bi-thu-du-le-duyet-binh-ky-niem-80-nam-thanh-lap-dang-lao-dong-trieu-tien-8331994-jpg.webp)


![[写真] ホーチミン市は2025~2030年任期の第1回党大会前夜、国旗や花で華やかに彩られている](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/10/1760102923219_ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-43-png.webp)














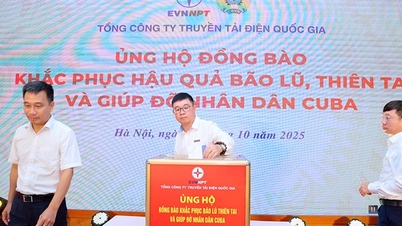



















































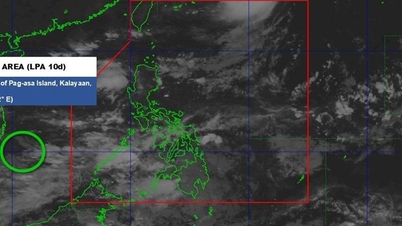

































コメント (0)