 |
強制社会保険加入者
規定によれば、強制社会保険の加入対象者には以下が含まれます。
1- 強制社会保険の対象となる従業員は、社会保険法第2条第1項のa、b、c、g、h、i、k、l、m、n、および第2項の規定を遵守する必要があります。
社会保険法第2条第1項第a号、b号、c号、i号、k号、l号及び第2項に規定する労働者で、国内外に留学、研修、就労するために派遣され、国内で給与を受け取っている者は、社会保険に強制加入する義務がある。
2- 社会保険法第2条第1項m号に規定される事業登録を有する事業世帯の事業主で、強制社会保険に加入するものは以下のとおりです。
a- 登録事業所の事業主は申告方式に従って税金を納める。
b-上記aの規定に該当しない登録事業世帯の事業主は、2029年7月1日から強制社会保険の対象となります。
3- 上記第 2 項および社会保険法第 2 条第 1 項 n に規定する対象者が、同時に社会保険法第 2 条第 1 項に規定する複数の対象者に属する場合、次のとおり強制社会保険に加入するものとする。
a- 上記第 2 項に規定する対象者が、社会保険法第 2 条第 1 項の b、c、d、dd、e、i、a、l、k、n、h、g 号のいずれかに規定する対象者でもある場合、先着順で社会保険法第 2 条第 1 項の b、c、d、dd、e、i、a、l、k、n、h、g 号に規定する対応する対象者に従って強制社会保険に加入する。
b- 社会保険法第 2 条第 1 項 n 号に規定する対象者で、社会保険法第 2 条第 1 項 b 号、c 号、d 号、dd 号、e 号、i 号、a 号、l 号、k 号のいずれかに規定する対象者でもある場合は、優先順位に従って、社会保険法第 2 条第 1 項 b 号、c 号、d 号、dd 号、e 号、i 号、a 号、l 号、k 号に規定する該当対象者に応じて強制社会保険に加入するものとする。
4-社会保険法第2条第7項a号に規定される社会保険加入義務の対象とならない社会保険給付および月額手当の受給資格者には、以下の者が含まれます。
- 毎月障害手当を受給している人
- 1995年7月26日付政府法令第50/CP号を改正および補足する1998年1月23日付政府法令第09/1998/ND-CP号の規定に従って毎月手当を受給している者。
- 労働能力喪失手当の月額支給停止時に退職年齢に達した者に対する手当に関する2000年8月4 日付首相決定第91/2000/QD-TTg号、労働能力喪失手当の支給期間が終了した実労働経験15年以上20年未満の者に対する月額支給金に関する2010年5月6日付首相決定第613/QD-TTg号の規定に従って月額支給金を支給されている者。
- 2008年10月27日付首相決定第142/2008/QD-TTg号「抗米戦争に参加した軍歴20年未満の兵士が除隊し、地元に帰還した場合の制度の実施について」、2008年10月27日付首相決定第142/2008/QD-TTg号「抗米戦争に参加した軍歴20年未満の兵士が除隊し、地元に帰還した場合の制度の実施について」の修正および補足に関する2010年5月6日付首相決定第38/2010/QD-TTg号の規定に従って毎月手当を受給している者。 2010年8月20日付首相決定第53/2010/QD-TTg号は、抗米戦争に参加した人民公安部隊における勤務年数が20年未満で、退職して地元に戻った人民公安部隊の将兵に対する制度を規定している。2011年11月9日付首相決定第62/2011/QD-TTg号は、1975年4月30日以降に祖国防衛戦争に参加し、カンボジアで国際任務を遂行し、ラオスを支援した者で、動員解除、除隊、または退職した者に対する制度と政策を規定している。
- 社会保険法第23条に基づく月額給付金を受給している人。
5. 社会保険法第2条第1項a号に規定する対象者で、パートタイムで勤務し、本政令第7条第2項の規定に基づいて算出された月給が、強制社会保険の納付基準となる最低賃金を下回る者。労働法の規定に従って試用契約に基づいて勤務する労働者は、強制社会保険加入の対象ではない。
強制社会保険の登録と社会保険手帳の発行
社会保険への加入登録および社会保険手帳の発行は、社会保険法第 28 条の規定に基づいて行われ、次のように詳細に規定されています。
上記第2項及び社会保険法第2条第1項n号に規定する対象者が、経営に参加する経営世帯、企業、協同組合、協同組合連合会を通じて社会保険の加入を登録する場合は、社会保険法第28条第1項の規定を遵守しなければならない。
上記第2項及び社会保険法第2条第1項に規定する対象者が、社会保険機関に直接社会保険加入を登録する場合は、社会保険法第28条第2項の規定を遵守しなければならない。
社会保険法第2条第1項g号に規定する対象者は、海外に就労する前に、社会保険法第27条第1項b号に規定する申請書を社会保険機関に提出しなければならない。
幹部、公務員、公務員及び労働者を管理する機関及び組織は、ベトナム社会主義共和国の海外代表機関の構成員として任命される前に、社会保険法第2条第1項h号に規定する対象者について、社会保険法第28条第1項の規定に従って社会保険加入を登録しなければならない。
強制社会保険料納付の基礎となる給与
この政令は、強制社会保険料納付の基礎となる給与は社会保険法第31条第1項の規定に従って実施されることを規定しており、以下のように詳細に規定されています。
社会保険法第31条第1項b号に規定される強制社会保険料の納付基準となる給与は、職務または職位に応じた給与、給与手当、その他の手当を含む月給であり、以下のものが含まれます。
a - 職務または役職に応じた給与は、労働契約で合意された労働法第93条の規定に従って雇用主が作成した給与表、給与スケールに従って職務または役職の時間(月ごと)によって計算されます。
b - 労働契約において合意される、a の給与水準が考慮していない、または十分に考慮していない労働条件、仕事の複雑さ、生活環境、労働力の魅力に関する要素を補償するための給与手当。従業員の労働生産性、仕事のプロセス、仕事のパフォーマンスの質に応じて決まる、または変動する給与手当は含まれません。
c- a に規定する給与と併せて一定の金額で決定され、労働契約で合意され、各給与期間に定期的かつ安定的に支払われるその他の加算額。従業員の労働生産性、作業プロセス、作業成果の質に応じて左右されるその他の加算額は含まれません。
この政令では、社会保険法第2条第1項第1号に規定される対象者に対する強制社会保険料納付の基礎として使用される給与は、労働契約で合意された月給であると明確に規定されています。
労働契約で時給を定めている場合は、その月給に労働契約で定めた労働時間数を乗じて月給を計算します。
労働契約で日給制を定めている場合は、月給は労働契約で定められた月の労働日数に日給を乗じて算出します。
労働契約で週給を定めている場合は、その週給に労働契約で定めた月の労働週数を乗じて月給を計算します。
本政令は、社会保険法第2条第1項k号に規定する対象者の強制社会保険料の納付基準となる給与は、村、村、居住集団レベルのパートタイム労働者の月額手当とすることを規定する。村、村、居住集団レベルのパートタイム労働者の月額手当が、強制社会保険料の納付基準となる最低給与よりも低い場合、強制社会保険料の納付基準となる給与は、社会保険法第31条第1項d号に規定する強制社会保険料の納付基準となる最低給与と同額とする。
社会保険法第2条第1項第1号に規定する対象者に対する強制社会保険料納付の基礎となる給与は、法律の規定に基づいて当該対象者が受け取る権利を有する給与とする。
労働契約書に記載された給与及び従業員に支払われる給与が外貨建てである場合、強制社会保険料の納付の基礎となる給与は、年の最初の6か月間については1月2日、年の最後の6か月間については7月1日の末日現在で国営商業銀行4行が発表するベトナムドンと外貨の送金による買付レートの平均為替レートでベトナムドンに換算された外貨建て給与を基準としてベトナムドンで計算される。これらの日が祝祭日と重なる場合は、翌営業日の為替レートが使用される。
従業員と雇用主の社会保険料の納付額、納付方法、納付期間
この政令は、社会保険法第33条および第34条の規定に従って、従業員および雇用主の強制社会保険の保険料率、方法、支払期間を規定しており、その詳細は以下のとおりです。
社会保険法第2条第1項k号に規定する対象者が、1か月間に14営業日以上就業せず、手当も受け取っていない場合、従業員と雇用主はその月について社会保険料を支払う必要はありません。
出典: https://baodautu.vn/those-subjects-who-must-participate-in-social-insurance-are-required-according-to-the-new-regulations-from-172025-d314842.html




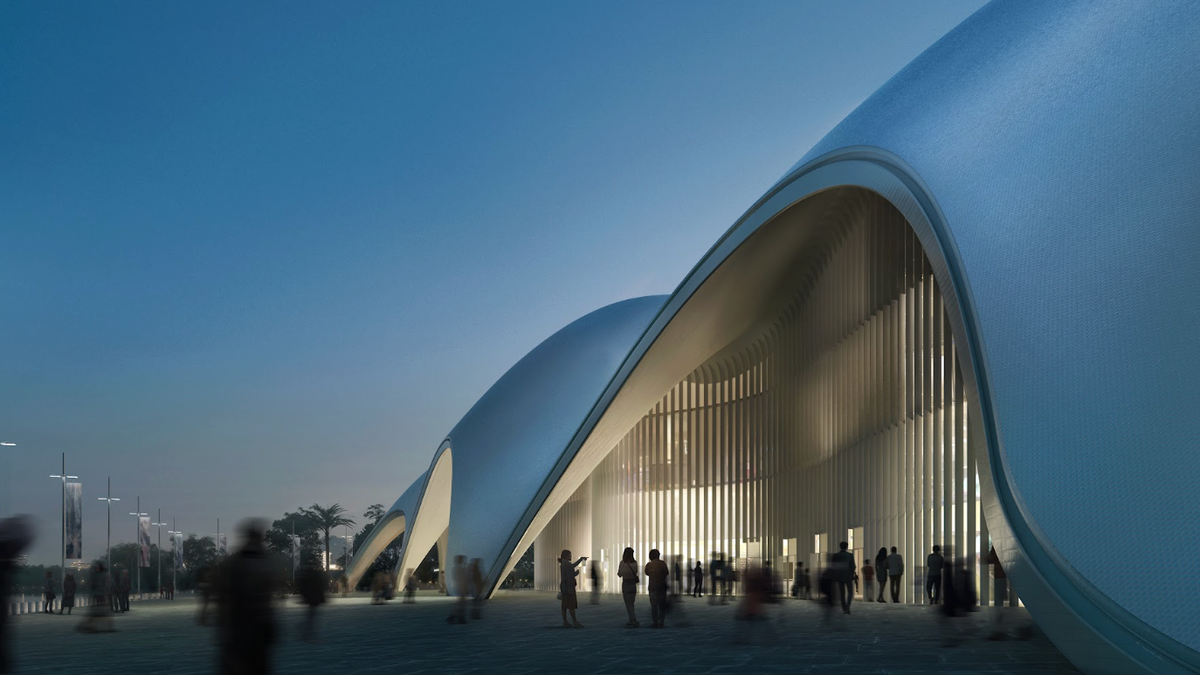



















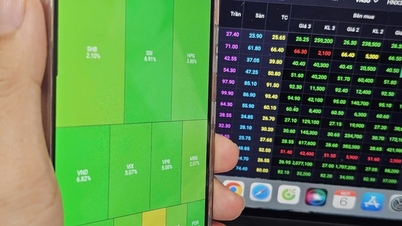
















































































コメント (0)