
魚の香り、海の魂
波頭のあの場所に、ハムフォンという小さな魚がいることを、知っている人は多くありません。カインズオン島の昔の漁師たちは、この魚は箸の先ほどの大きさで、身は透き通ったピンク色で皮は薄く、毎年旧暦の6月と7月頃にしか戻ってこないと言い伝えています。この魚は独特の香りがあり、風下にいた人々は、風上に群れが現れた時にこの魚だと見分けることができます。そのため、この魚は「ボイフォン」と呼ばれています。「ハムフォンはまるで王家の美女の名にふさわしい高貴な香りを持って生まれたかのようです」と、地元の研究者グエン・ティエン・ネン氏は語ります。

しかし、ハムフォン魚は単なる香りの問題ではありません。ハムフォン魚醤に塩漬けされたこの小魚は、カインズオン族の「国民的精神」とも言える王室特産品となります。黎朝時代以来、ハムフォン魚醤は王室から毎年の貢物として定められており、漁村にとって税金のように負担すべき産物でした。
地元の学者から「カイン・ズオン学者」として知られるグエン・ティエン・ネン氏によると、「後黎朝は、村民に対し、毎年400瓶のハムフォン魚醤を国王に献上するよう命じる勅令を出しました。少ない数に思えるかもしれませんが、村民にとっては400嵐に等しいのです。」

魚は数週間しか姿を見せないため、捕獲は困難で、魚醤作りはさらに手の込んだ作業です。魚は新鮮でなければならず、ほんの数時間でも遅れると腐ってしまいます。塩は天日干しと露で乾燥させ、強いえぐみを取り除きます。最高の魚醤は、木瓶に塩漬けし、数ヶ月間天日干しして色と風味を醸し出すことで作られます。風と塩を経験した女性だけが、忍耐と技量で「誓いの香り」と呼ばれる魚醤を作ることができます。
しかし、漁期は良い時もあれば悪い時もありました。カンドゥオン村の人々は、貢物として納める魚醤が足りず、「まともに食べられず、よく眠れない」ことがよくありました。朝廷の命令は王の命令でもありました。魚醤が足りなくなると、郡の長官は兵士を派遣し、村人たちを殴打し、逮捕し、魚醤の瓶一つ一つを捜索させました。荒れた海で村全体が一文無しになった年もありました。
この物語は伝説となっている。漁獲量の少ない季節の混乱の中、王室の試験に合格したばかりのド・ドゥク・フイという男が、村の縁を切る機会をうかがい、宮廷に入る道を探して都に潜伏した。彼は役人でも教師でもなかった。召使いに変装し、宮廷の高官に仕えることを願い出て、あらゆることを仕切った。
しかし、賢く、忍耐強く、比類なき心を持つ者であれば、永遠に「召使い」でいることはできません。ド・ドゥク・フイはすぐに信頼される人物となり、追悼文を書くよう任命されました。ある日、官吏は喜びに浸り、汗と涙で魚醤を作る村で、自分たちが作った魚醤を食べようとしない人々の運命を打ち明けました。彼は言いました。「もしあなたが私の村をその重荷から解放してくれるなら、私はその恩恵を子や孫たちに伝えます。」

官吏は感動して頷きました。コン・フイ氏は嘆願書を書き、国王に提出しました。官吏の働きかけにより、国王はハムフォン魚醤の貢物を廃止する勅令を出しました。
それ以来、カンドゥオン村の人々は胸から大きな石が取り除かれたような気持ちになった。最初の魚醤の瓶はもはや首都へは送られず、南北に売られるようになった。魚醤は芳醇な香りを放ち、人々は温かく迎えてくれた。そして、人々はそれを届けてくれた人のことを忘れることはなかった。家庭の台所から村の共同住宅へと、ある韻文が伝わるようになった。「ハムフォンの魚醤を食べながらコン氏を思い出す」とはまさにこのことだ。
魚醤の瓶から伝統へ
現在、ハムフォン魚は希少な存在となっています。魚醤の中には今でも独特の香りが漂うものもありますが、カインズオン省の魚醤職人たちは、純粋なハムフォン魚醤はもはや記憶の中にしか残っていないことを認めざるを得ません。ほとんどの生産施設では、ハムフォン魚を他の小魚と混ぜることしかできません。しかし、混ぜ合わせたとしても、独特の香りは魚醤の一滴一滴に染み渡り、まるで魚がそれぞれの陶器の壺に魂を宿したかのようです。
何世代にもわたって魚醤を作り続けてきたカオ・ティ・ニンさんはこう語った。「マム・ハム・フォンは単なる魚醤ではなく、村の記憶です。海の季節であり、母の魚籠であり、季節が来ると父が毎晩語る物語なのです。」

今日のカンドゥオン村は様変わりしました。漁業祭に加え、カンドゥオン村には1キロメートルに及ぶ壁画の道があり、村の歴史、村人たちが魚醤を作る様子、手漕ぎボート、そして嘆願書を手にしたコン氏の様子などが描かれています。 クアンビン省とクアンチャック郡は、この村を中部地方のユニークな文化観光村として育成しようとしており、その主力産品は魚醤です。
カインズオン村党書記のトラン・チュン・タン氏はこう述べた。「私たちは観光客にただ来て写真を撮ってほしいだけではありません。ハムフォン魚醤を食べるとき、人々はコミュニティ全体の記憶、海の文化、そして人道的な逸話の味を味わっているのだということを理解してほしいのです。」
今では王への供物も、税金の徴収もなくなった。しかし、魚醤の一つ一つ、伝承された詩の一つ一つに、カイン・ドゥオンは今もなお、正義への信念から召使いに扮した若者の声が響いているようだ。魚の香りのように、塗る必要もなく、名付ける必要もないその香りは、毎年6月の海風に漂う。

そして、カイン・ドゥオンさんは、川を漂う船から波を砕き、コンさんの話といつまでも香りが失われない魚醤の味を携えて、新たな旅に出ています。
ニン夫人は、伝統的な製法のようにハムフォン魚醤を大量に作ることはないものの、今でも小さな瓶詰めにして家で作り、来客時に食べていると話した。6月の食事は海の香りとともに振る舞われ、古来のハムフォンの香りは、何百年も前の騎士道精神を今なお呼び起こす。ニン夫人はこう語った。「ハムフォンは純粋で、昔の人たちはそれを熟知していました。他の魚種から作られた何十種類もの魚醤とは味が違います。希少性が高いため、王様に献上しなければなりませんでした。そうでなければ、誰も王様に献上しようとはしなかったでしょう。何百年も経った今でも、ハムフォン魚醤の一滴が村に芳しい香りを漂わせています。」
ニン夫人の言った通りだった。豚バラ肉のスライスが魚醤の器に触れるだけで、まるで涼しい海風を飲み込んだかのようだった。最初の一滴は遠い海の味を呼び起こし、次の一滴はカインズオン族の何世代にもわたる記憶が、故郷の味として凝縮された。最後の一滴は、魚の響きだけでなく、かつて王宮の中心で民衆への愛のメッセージを嘆願書に込めた、かつて生まれたコン氏の響きをも感じさせた。
出典: https://www.sggp.org.vn/ve-canh-duong-an-mam-ham-huong-nho-thuong-ong-cong-post801016.html



![[写真] ホーチミン市は2025~2030年任期の第1回党大会前夜、国旗や花で華やかに彩られている](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/10/1760102923219_ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-43-png.webp)


![[写真] 朝鮮労働党創立80周年記念パレードに書記長が出席](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/11/1760150039564_vna-potal-tong-bi-thu-du-le-duyet-binh-ky-niem-80-nam-thanh-lap-dang-lao-dong-trieu-tien-8331994-jpg.webp)



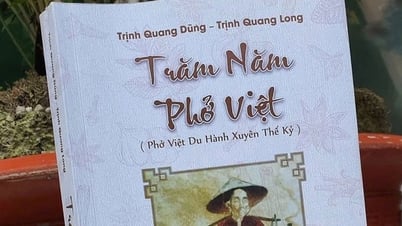











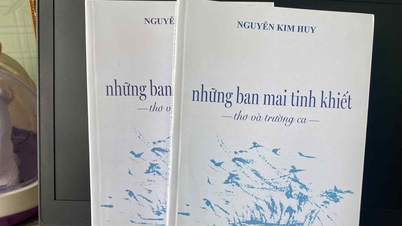
















































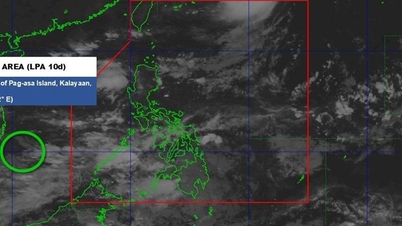





























コメント (0)