
グエン・ミン・ホアさんは、 ハノイ市ハドン区の私立小学校で教師をしています。夫と二人の月収は4,000万ドン未満です。個人所得税の控除額は2,200万ドン、子供2人の扶養控除額は880万ドンです。
つまり、課税所得が月額920万ドンの場合、個人所得税として約46万ドン、年間550万ドンを支払うことになります。これは、生活費の高騰を考えると決して小さな金額ではありません。
「税金を払うのは国民の責任ですが、収入は同じなのに生活費は何倍にも増え、税金は全く減額されていません」とホアさんは語り、4人家族の生活費を確保するためあらゆる出費を節約しなければならないと付け加えた。
ホアさんは、2023年末時点で個人所得税を納めている2,600万人以上の給与所得者の一人だ。規定により、社会保険料、 健康保険、失業保険、家族控除などが差し引かれ、残った金額が課税所得となる。
個人控除は2020年から月額1,100万ドンに維持され、これは税務当局が「個人の最低限の生活ニーズを満たす支出水準」と定めたものです。扶養家族控除は440万ドンです。
ホアさんのような給与所得者にとって、家族控除は個人の課税所得を決定する基礎となります。しかし、課税開始点と所得税の計算の基礎となる家族控除は、過去16年間でわずか2回しか変更されていません。当局による直近の調整は2020年7月で、4年以上前のことですが、その間、人々の所得、支出、物価、インフレ率は毎年上昇していました。
「個人所得税法は2025年に改正され、2026年初頭から施行される必要がある」と、ハノイ国家大学ベトナム経済政策研究所(VEPR)副所長のグエン・クオック・ヴィエット博士は述べ、運営者は「2025年末に国会に提出し、2026年半ばに承認するというロードマップに固執すべきではない」と付け加えた。
個人所得税法が制定された2007年を基準年とすると、国民の支出と所得は家計控除の増加率に比べて何倍も増加しています。具体的には、個人所得税法が施行された2008年には、一人当たり平均約79万2000ドンを支出していました。
ベトナム統計局(GSO)が全国のコミューンと区の約4万7000世帯を対象に実施した調査によると、2022年にはこの数字は3.5倍の約280万ドンに達する見込みです。一人当たりの支出額は2008年と比べて4~5倍に増加し、最低賃金は6~7倍に上昇しましたが、世帯控除は3倍未満にとどまっています。
しかし、記者の調査によると 平均月収2,200万ドンの23,900人以上の読者を対象に実施した調査によると、納税者は自身の支出が1,000万ドン以上である一方、扶養家族への支出は少なくとも700万ドンに達しています。この割合は個人支出の70%を占め、財務省が定める40%の基準を上回っています。
2023年末時点での経済規模は4,300億米ドルです。一人当たりの平均所得は年間約1億200万ドンで、2007年の7.5倍以上となっています。生活必需品やサービスの価格も毎年着実に上昇しており、多くの品目は「所得よりも速いペースで上昇」しています。例えば、統計総局のデータによると、教育は2020年と比較して17%、食料品は27%、ガソリン価格は105%上昇しました。
法改正に関する今回の協議において、財務省は、家族控除額を政府が規制する選択肢を検討することを提案しました。これにより、政策は柔軟になり、現実に適合し、国民の合意形成につながるでしょう。
グエン・クオック・ヴィエット氏によると、家族控除は各地域の実際の生活水準に基づいており、地域最低賃金を基準とすることができるとのことです。仮に、家族控除額が地域最低賃金の4倍だとすると、ホーチミン市の最低賃金は496万ドンなので、家族控除額は現在の月額1,100万ドンではなく、約1,984万ドンとなります。
地域最低賃金に基づく家族控除について、中小企業支援センター(ホーチミン市ビジネス協会)副所長の弁護士グエン・ドゥック・ギア氏によると、政府は毎年調整する必要はないとのことだ。なぜなら、給与は従業員、雇用主、そしてビジネス協会の代表者間の合意に基づいて毎年決定されるからだ。
ANVI法律事務所所長の弁護士、チュオン・タン・ドゥック氏によると、家族控除額は、年末に総統計局が発表する消費者物価指数(CPI)データの増減に応じて調整されるべきだ。「このような規制は時代遅れになることも、納税者にとって不利になることもありません」とドゥック氏は述べた。
家族控除とは、納税者とその扶養家族(両親、子供)の最低限の生活に必要な費用を賄うための控除額です。この控除額は、消費者物価指数(CPI)が法律施行時(2008年)と比較して20%以上変動した場合に調整されます。
ベトナム税務コンサルタント協会執行委員で弁護士のグエン・ヴァン・ドゥック氏は、人々の実際の支出と給与に合わせて家計の出費を減らすために、消費者物価指数が5~10%変動した場合には政府が調整を行うべきだと述べた。
扶養家族については、Nghia弁護士は控除額の基準額を納税者本人の所得水準の50%に引き上げ、現行の40%から引き上げるべきだと提案しました。つまり、この控除額は月額440万VNDではなく、約992万VNDとなります。
さらに専門家は、医療費、教育費、住宅ローン利息といった合理的な経費を課税所得に算入しないよう勧告している。ベトナム税務コンサルティング協会執行委員のグエン・ヴァン・ドゥオック弁護士は、これらは必要不可欠な経費であり、家計の支出構造において大きな割合を占めていると指摘する。「これらの経費も急増しているにもかかわらず、税金計算前に控除されていない。これは是正すべき不備だ」と同氏は述べた。
| 税率 | 課税所得(百万VND) | 税率(%) |
| 1 | 最大5 | 5 |
| 2 | 5~10歳以上 | 10 |
| 3 | 10歳以上18歳以上 | 15 |
| 4 | 18歳以上32歳以上 | 20 |
| 5 | 32歳以上52歳未満 | 25 |
| 6 | 52歳以上80歳未満 | 30 |
| 7 | 80歳以上 | 35 |
VEPR副所長のグエン・クオック・ベト氏によると、家族控除に加えて、厚い税制と最初の収入段階での税金の積み重ねも、改善が必要な欠点だという。
現行の賃金労働者に対する累進税率は7段階に分かれており、税率は5%から35%までの範囲となっている。ベト氏はこれを5段階に減らし、税率の差を広げることを提案した。
より具体的には、ANVI法律事務所のチュオン・タン・ドゥック所長は、レベル1の税率は1~2%程度に引き下げられるべきだと述べた。最高税率は20%である。「レベル7の個人所得税が法人所得税のほぼ2倍となる35%である理由はない」とドゥック氏は述べた。
言うまでもなく、ヴィエット氏によれば、これは第一階層の納税者、特に若い労働者が、自身の能力の向上と生活の安定に投資するための収入を蓄積する条件を備えるのに役立つという。
「大都市の人々の生活に直接関係する住宅価格やサービスコストが高騰している状況では、これは必要な変化だ」とヴィエット氏は認めた。
この見解は当局も認めている。財務省は、累進課税制度を段階数を減らし、所得格差を拡大する形で調整することを提案している。これは、高所得者への税制優遇措置を確保し、申告と納税を容易にするためである。
TB(VnExpressによる)[広告2]
出典: https://baohaiduong.vn/de-xuat-sua-thue-thu-nhap-ca-nhan-ngay-nam-2025-399487.html













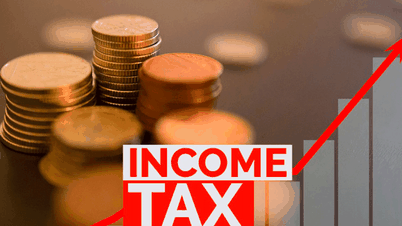



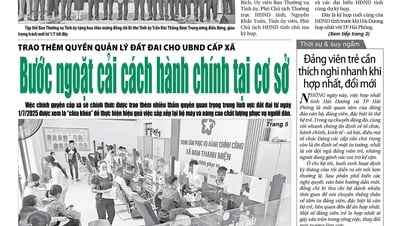








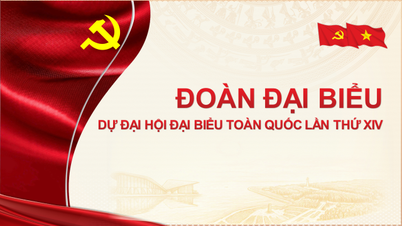


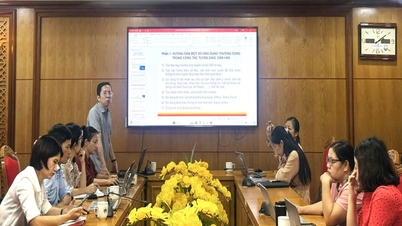


![[写真] ニャンダン新聞が「心の中の祖国:コンサート映画」を発表](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/16/1760622132545_thiet-ke-chua-co-ten-36-png.webp)















































































コメント (0)