この時代には小説、演劇、詩歌の3つのジャンルが誕生し、その代表的な人物としては井原西鶴、近松門左衛門、松尾芭蕉の3人が挙げられる。
都市文学と民俗文学
文学ルネサンスは17世紀、徳川幕府が江戸(現在の東京)に拠点を置いた時代の初めに始まりました。初期の町人文学は17世紀のモデルに沿って18世紀半ばまで発展しました。
2世紀半に渡る孤立と外界との一切の関係のなさの中で、文学は新たな刺激を持たず、特に19世紀に入ると徐々に活力を失っていった。
文学の中心人物は、もはや平安時代の宮廷の王子や貴公子、淑女ではなく、中世初期の戦場で戦った武士でもなく、むしろ都市階級の裕福な商人、小商人、職人、遊女などである。
この時代には小説、演劇、詩歌の3つのジャンルが誕生し、その代表的な人物としては井原西鶴、近松門左衛門、松尾芭蕉の3人が挙げられる。
 |
| 詩人の井原西鶴(1642-1693)。 |
井原西鶴(1642-1693)は、江戸時代の日本文学界を代表する詩人であり小説家でした。大坂の裕福な商人であった彼は、40歳で隠居し、文筆活動に専念しました。旅を重ね、繊細な観察眼で物事を観察し、得意としていた俳句のように、写実的でユーモラス、かつ緻密な作風で作品を創作しました。
彼は12年間、浮世草子を書き続けました。情熱的な恋愛物語や官能的な物語、戦争、経済界の物語など、現代的なテーマに焦点を絞り、都会や田舎の「人生喜劇」を創作しました。滑稽な物語を紡ぎました。
ある小さな主人の美しい妻の話があります。彼女は夫の召使いに恋をした召使いに罠を仕掛け、召使いは夫の腕の中で眠りに落ちました。その後、妻は夫と共に追放され、二人とも捕らえられ、罰を受けました。また別の話では、辺鄙な村の人々が、どこからともなくやって来た傘を崇拝していました。傘の神様は、ある女性に傘を捧げるよう要求しました。若い未亡人が申し出ましたが、神様が来なかったため、彼女は怒り、傘をバラバラに引き裂いてしまいました…
井原西鶴は、晩年までに詩集や詩評を約12冊著した。その中には、たった一日で詠んだ詩集(約2万3500首)も含まれている。妻の死後(1675年)、12時間で千首に及ぶ俳諧(『俳諧独吟一日』)を詠み、同時に出家して日本各地を旅した。
彼は『好色一代男』(1682年)、 『好色五人女』 (1686年)など、数多くの有名な小説を執筆しました。
* * *
近松門左衛門(1653-1725)は人形劇と実写劇の作家であり、「日本最高の劇作家」であり「日本のシェイクスピア」と称えられました。武家の家に生まれ、漢学に精通し、僧侶として過ごした時期もありました。
彼の戯曲は同時代文学をはるかに凌駕していたが、人形劇の特性に偏重したため、文学的価値が損なわれることもあった。今日に至るまで、彼の戯曲には現代的な要素がいくつか残っており、運命に翻弄される下層階級の登場人物を通して、人間の運命を写実的かつ叙情的に描いている。
彼は、女や娼婦を愛する家長を賞賛することも非難することもせず、むしろ憐れんだ。そこで称揚された美徳は義理(ギリは中国語で「亦亦亦」の意)であり、ここでの「亦亦」とは義務、すなわち返済すべき精神的な負債を意味する。近松の有名な戯曲には、『曽根崎心中』(1703年)、『心中天網島』(1721年)、『冥土の飛脚』(1711年)などがある。
* * *
松尾芭蕉(1644-1694)は、八丈禅師としても知られ、詩人であり、著名な画家でした。農民の家に生まれ、若い頃から文学に親しみ、漢詩にも造詣が深かった。しばらく官吏として働いた後、禅の修行に励み、道丹蘇裡(嵐の夜に風に引き裂かれる八丈の葉のような芸術家の人生を比喩的に表現したもの)を創始し、規則や形式にとらわれず、真摯な気持ちを表現することを説きました。
彼は各地を旅した後、江戸近くの川沿いの質素な家に戻りました。家の前には芭蕉畑があったため、芭蕉庵という名前が付けられました。家は焼け落ちましたが、彼は再び景勝地を旅し、詩を詠み、墨を描き、心と詩作の技を磨きました。
彼は、厳格な規則と言葉遊びに偏った、ありふれたユーモア詩の形式に過ぎなかった俳句の形式を改革した功績が大きい。俳句は5+7+5音節の3行のみで構成されていた。
彼は俳句のテーマを拡張し、大衆語と哲学的な内容、自由な叙情性、そして多くの繊細な感情を織り交ぜました。彼の最後の俳句は、詩人と仲間が宿屋で二人の娼婦と寝泊まりした夜のことを歌っています。二人の娼婦は仲間に加わりたいと申し出ましたが、僧侶は他に多くの場所へ行かなければならないため、敢えて受け入れませんでした。
彼は野晒しを愛し、そのことを題材にした詩を詠んだ。主な著作には、『野晒紀行』 (1685年)、 『春に日』 (1686年)、 『鹿島紀行』 (1687年)、 『奥の細道』(1689年)、『佐賀日記』 (1691年)などがある。
俳句を味わうには、その俳句が作られた文脈や歴史的背景を理解することが必要です。
[広告2]
ソース



![[写真] ホーチミン市は2025~2030年任期の第1回党大会前夜、国旗や花で華やかに彩られている](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/10/1760102923219_ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-43-png.webp)



![[写真] プー・ジャーのユニークな馬帽子編み工芸](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/10/1760084018320_ndo_br_01-jpg.webp)










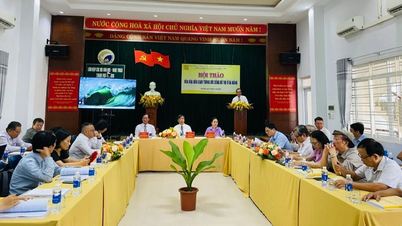

















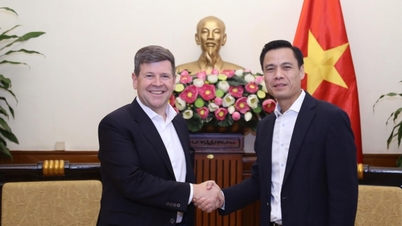

























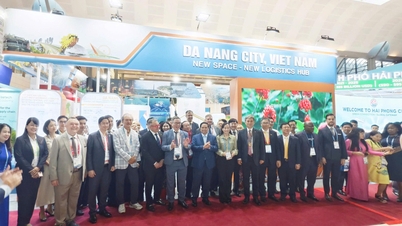











































コメント (0)