ハン・パゴダ(正式名称:カンポンニグロダ・パゴダ、またはコンポン・クライ・パゴダ)は、チャヴィン省チャウタン郡チャウタン町にあります。パゴダの正門は洞窟のように作られているため、ハン・パゴダと呼ばれることもあります。チャヴィン省には数百ものクメール・パゴダがあり、中でも最も古いパゴダの一つです。
彫刻が観光客を魅了する
ハン・パゴダは、約2ヘクタールの敷地に建つ、クメール民族特有の美しい建築様式を誇ります。パゴダの周囲には、古木のスターツリーとアブラナが何本も立ち並び、多くの鳥類が生息しています。そのため、ハン・パゴダはチャヴィンを訪れる多くの観光客にとって魅力的な観光スポットとなっています。
古代の星樹の根から作られた五霊像の隣に立つタック・スオン僧侶。写真:ナム・ロン
友人たちとハンパゴダを訪れたグエン・ティ・トゥエット・マイさん(ホーチミン市在住)は、緑豊かな木々や様々な鳥たちが織りなす、このパゴダの独特の美しさに圧倒されたと語った。「特にパゴダに入ると、細心の注意を払って繊細に手彫りされた木像を鑑賞できます。これらの彫刻が、パゴダの僧侶である職人によって作られたものだと知って、さらに驚きました。そこで、友人たちに写真を撮って保存するように頼みました」と彼女は語った。
グエン・フオン・タオさん(チャヴィン市在住)は、旧暦の中月と末日に定期的に仏塔を訪れ、平和を祈願しているという。「ハン仏塔は木彫りで有名です。仏塔を訪れた方は、僧侶たちが丹精込めて芸術作品を制作する様子を自分の目で見てみたい方は、仏塔裏の工房へ行って見学できます」と彼女は教えてくれた。
ハンパゴダの僧侶が仏像を制作している。写真:ナム・ロン
ハン・パゴダの僧侶、タック・チンさん(24歳)は、3年以上彫刻を学んできたという。最初は難しかったが、経験豊富な僧侶たちが熱心に教えてくれたおかげで、今では難しい形も作れるようになったという。「パゴダでは無料で教わるだけでなく、彫刻を制作して報酬ももらえるんです。この技術をしっかり習得して、将来はパゴダに残ってもっと収入を得られるように頑張ります」とチンさんは語った。
この作品はアジア記録を保持している
ハン寺で木彫りに携わってきたソン・ソックさん(49歳、チャヴィン市在住)は、20年以上この地で木彫りを学び、実践してきたと語った。彼はまた、この寺で多くの僧侶に木彫りの技術を教えている。
タック・チン師匠は仕事に細心の注意を払っています。写真:ナム・ロン
「ニャットロンザン寺院の作品がアジア記録として認められました。これは私の生涯の作品だと考えています。この作品は、私と4人の熟練した僧侶が、樹齢300年を超え、重さ8.7トンもある古代の油樹の根株から、約2年をかけて丹念に彫り上げました。正面には12の干支の動物が彫られ、その周囲には平和、繁栄、自由を象徴する12羽の鳩が配置されています。正面中央には大きな時計があり、ホアンサ諸島とチュオンサ諸島を含むベトナムの地図、バーディン広場のシンボル、そしてチャヴィン歓迎門が描かれています。時計の周囲には、ベトナムの人々の文化的伝統を象徴する12羽のラック鳥が彫られています。裏面には、陸上、水中、宇宙の3つの領域に生息する70種の動物が彫られ、自然の豊かさを象徴しています」とソック氏は説明した。
タンニエン記者の取材に対し、ハン寺の住職タック・スオン氏は、この木彫りの職業は20年以上前から存在していると語った。それ以前は、この寺には多くの古木があり、薪として使うにはもったいないと考えた住職は、職人に彫像を依頼して販売することで寺の建設資金を調達し、人々や観光客に鑑賞してもらうことを思いついた。この彫刻の素晴らしさを見て、寺の僧侶たちはそれを習得し、徐々に職業として確立し、後進の弟子へと受け継がれていった。
ハンパゴダ本堂のパノラマ写真:NAM LONG
「パゴダで修行する若い僧侶たちは、木彫りの技術を習得し、コースを修了すれば技術を習得し、自分と家族を養えるようになります。パゴダの作品は、パゴダの建設資金とパゴダの生活費を賄うために販売されています。パゴダの工房からは多くの彫刻家が育成され、全国の多くの省や都市で活躍しています。また、パゴダでは木版の彫刻や、人々の要望に応じた彫刻も受け付けています」と、タック・スオン住職は述べた。
寺院内には至る所に木彫りが展示されており、参拝者は鑑賞したり写真を撮ったりすることができます。寺院の僧侶や職人が、スターツリーや油木の根、幹、幹から作った鳥や動物の彫像は、ハンパゴダ独特の特徴であり、独特の見どころとなり、参拝者を惹きつけています。(続き)
Baothanhnien.vn
出典: https://thanhnien.vn/nhung-nghe-doc-la-nha-su-lam-dieu-khac-18524102017451673.htm







![[写真] ファム・ミン・チン首相が地方との政府オンライン会議を主宰](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/5/264793cfb4404c63a701d235ff43e1bd)































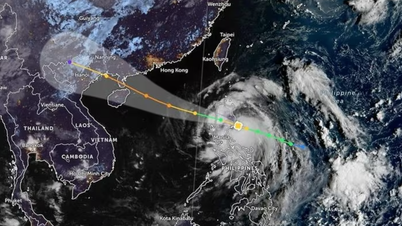






















![[ビデオ] ペトロベトナム50周年記念式典の概要](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/4/abe133bdb8114793a16d4fe3e5bd0f12)

![[動画] ラム事務総長がペトロベトナムに8つの黄金の言葉を授与:「先駆者 - 優秀 - 持続可能 - グローバル」](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/23/c2fdb48863e846cfa9fb8e6ea9cf44e7)








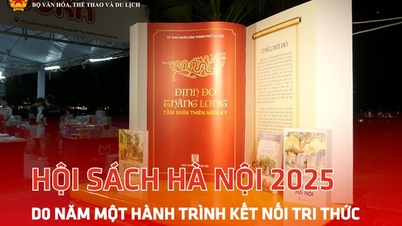





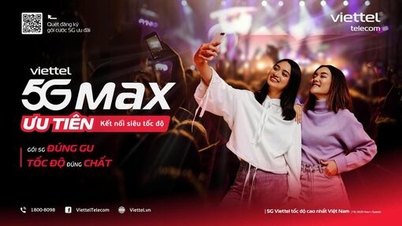




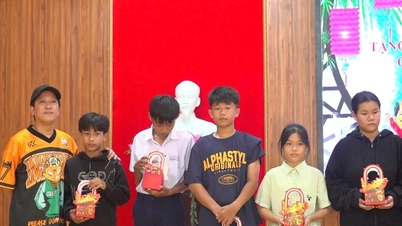













コメント (0)