(NLDO) - 私がガランガルで煮込んだソウギョを初めて食べたのは10年以上前、旧正月を祝い、家族に会うために恋人(今の夫)の故郷に行ったときのことでした。
義母は早くに亡くなりました。家族は姉妹が二人だけで、義母も自分の家族と暮らし、義母が残した家の近くに住んでいました。一ヶ月前、弟が恋人を連れて実家に帰ると言い出したのを聞いて、義母は何日もかけて母の家を片付けました。毛布とマットレスも交換しました。南国出身の私が北国の寒さに慣れていないのではないかと心配し、厚手の綿毛布を何層にも重ねて敷いてくれました。義母はたくさんのものを用意してくれましたが、キッチンは用意しませんでした。「私は料理しなくていいから、入って食べなさい」と言ってくれました。
その日は新年最初の夜だったのを覚えています。夫の親戚に新年の挨拶をしに行くため、家に戻りました。家に着いた時にはもう暗くなっていました。寒かったです。ドアを開けると、テーブルの上に蓋付きの籠が置いてありました。中には、ガランガルで煮込んだソウギョ、唐辛子と魚醤で漬けた白菜、酸っぱい魚のスープ、そしてまだ温かい白米が入っていました。


家族の食事にガランガル入りのソウギョの煮込み
かごの蓋を開けた途端、ドアの外から彼女の声が聞こえた。「温かいうちに食べなさい。どうしてそんなに遠くまで歩いたの?寒くてお腹も空いていないの?」そう言うと、彼女は自転車に飛び乗って走り去った。「家に帰ってバッファローに餌をあげるわ。さもないと納屋に押し入られちゃうわ」と、彼女の声がまだ響いていた。
ガランガルが魚料理に使われるなんて初めて知ったので、その匂いに慣れませんでした。ご飯を数口食べた時は、魚醤に浸した白菜の漬物だけを食べました。夫は「少しだけ試してみて、ゆっくり食べれば次の食事が美味しいよ」と励ましてくれました。実際、次の食事は必要ありませんでした。3口目から脂の旨みと、しっかりとした魚の身が感じられました。魚の骨は火でじっくりと炒められていたので、柔らかく溶けていました。
夫から聞いた話では、ここではテトにソウギョをよく煮込むそうです。裕福な家庭では5~6キロもある大きなソウギョを買ってきて、豚バラ肉と一緒に煮込みます。何度も何度も煮込むので、ソウギョはしっかりと味が染み込み、身は引き締まっていて、骨は柔らかくなっています。煮込んだソウギョをより美味しくするために、両面を軽く焼いたり、炭火で焦げ目がつくまで焼いたりする人もいます。その年、義姉の家庭はあまり裕福ではありませんでしたが、テト初日に彼女が持ってきたソウギョは、背骨から腹皮まで、ほぼ手のひらほどの長さがありました。
食事が終わるとすぐに、妹が玄関に立っていて、「お皿と箸は置いておいて。私が持って帰って洗うから」と言いました。妹は魚が美味しいかと尋ねました。私が褒めていると、夫が「ちょっと甘すぎるね」と言いました。妹は、私が帰る前に南に行ったことがある人に何人か尋ねてみたところ、南のものは何でも甘いと多くの人が言っていたと説明してくれました。南の人たちは寒さに耐えられず、嫁のために炭火コンロを用意しなければならないほどでした…。妹は、将来の嫁が田舎の気候や食べ物に慣れていないのではないかと心配していたので、ソウギョを煮る時に、今までしたことのなかった砂糖を多めに入れたのです。


思い出すと、その年、私はチュオンサへの約1ヶ月の出張から戻ってきたばかりだった。体は日焼けし、顔は黒ずんでいたが、夫は「村で一番のハンサム」と褒められていた。まるで不釣り合いなカップルのようだった。義姉はいつも皆に「島旅行から帰ってきたばかりなの」と言い訳し、「この醜さは一時的なもので、普段はハンサムよ」と仄めかしていた。
私は将来の夫の故郷で一週間以上、旧正月を祝いましたが、初めて食べる料理、初めて会う人、何度も聞かないと分からない方言などがあったにもかかわらず、まったく違和感を感じませんでした。すべて彼女のおかげです。
私の義理の姉は田舎の女性で、一年中畑や庭に慣れていて、一度も村を出たことがなかったが、煮魚の鍋に私が食べやすいように砂糖を多めに入れるなど、あらゆる細かいことに細心の注意を払ってくれたので、私は自分の人生で愛する人たちを選んだのだと信じることができた。


[広告2]
ソース






































![[写真] 民族学博物館で賑わう中秋節](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/4/da8d5927734d4ca58e3eced14bc435a3)





















![[ビデオ] ペトロベトナム50周年記念式典の概要](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/4/abe133bdb8114793a16d4fe3e5bd0f12)

![[動画] ラム事務総長がペトロベトナムに8つの黄金の言葉を授与:「先駆者 - 優秀 - 持続可能 - グローバル」](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/23/c2fdb48863e846cfa9fb8e6ea9cf44e7)



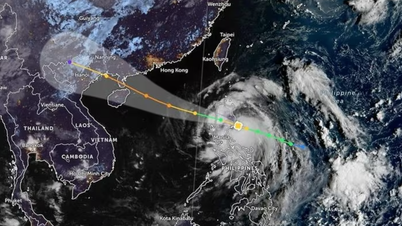






























コメント (0)