
木の梢には線が走り、庭にも揺らめくろうそくの灯りが点々と続いていた。それは前日に作った中秋の名月提灯の灯りだった。あの頃の思い出が、突然私の心に蘇ってきた。
村にまだ電気が通っていなかった頃、月は明るく澄んでいた。街の埃に晒されることもなく、無数の街灯やそびえ立つビルに揺らめくこともなかった。月は空高く輝く唯一の光となり、両親が夜通し水を抜いた帰り道を照らした。月は子供たちを鬼ごっこへと導き、笑い声を幼少期の思い出に染めた。
記憶の中の再会の月は、蜂蜜をまぶした月餅のように丸かった。旧暦の8月の満月の日に、母が熱い蓮の香りの茶を添えて祭壇に置いた、オーブンから出したての湯気の立つ月餅のような月餅だ。月明かりの下、父は竹を削って五芒星の灯籠を作った。私たちは並んで座り、片方は糊を貼り、もう片方は赤いセロハンで遊んでいた。
時々、ぼんやりとした時間 ― 5分も集中できない子供のぼんやりとした時間 ― に、私は月を見上げます。おとぎ話のような目で、月とクオイ、そしてガジュマルの木を描きます。月光に彩られた絵は、空高くにしまい込まれ、二度と取り戻して見ることはできません。時間は一方通行の流れのように、ずっと遠くへと流れていきます。
月を見上げる季節は、しばしば時折の雨で中断された。冷たい雨が窓を吹き抜け、せわしなく音を立てた。私たち子供たちがキャンドルと呼んでいたろうそくは、父が前日に作ったランプの中で、今にも消えそうなほど揺らめいていた。私たちは皆、隣家の広いポーチの下に逃げ込み、月を見上げながら、小さな頭に雨粒を浴びた。
獅子舞の太鼓の音が響き渡り、村の小さな獅子舞の一団はまるで提灯行列のようで、数人の子供たちが月見を楽しんで遊んでいました。大人たちは手の届くところにお菓子の包みを吊るして、その精神を支えました。私のような提灯行列は拍手と歓声で支えました。雨は止み、月は昇り始めました。遠くで獅子舞の太鼓の音が響き渡り、手作りの提灯がずらりと並びました。
月はもはや唯一の光ではなくなり、中秋節も次第にその小さな顔を失っていった。私にとって中秋節は、通り沿いの月餅の屋台を通してしか分からなくなっていた。私は屋台に立ち寄り、月餅を一箱買って父の仏壇に置いた。もう10年も母は月餅を焼いておらず、父は座って竹を研ぎ、提灯を作っていない。
老いて弱り果てた人々もいれば、煙を立ち上らせる香炉の陰で微笑んでいる人々もいる。景色は消え去り、人々は去り、月さえも雲の向こうに霞んでしまった。何かを失った時、人々はそれを思い出してより明るいものを描くというのは本当なのだろうか?月は今も昔も変わらないのだろうか?ただ、昔のように人々が見上げなくなっただけなのだろうか?
恋しい夜には、ふと月を見上げたくなる。人の顔、月、思い出の顔。遠い昔の中秋節の夜に戻りたい。父の隣でランタンを作り、母のシャツを握りしめて蜂蜜を塗った月餅をねだっていたあの頃。
8月になり、秋になり、ゆっくりと月を眺める季節がやってきます。
出典: https://www.sggp.org.vn/mua-ngua-mat-trong-trang-post816399.html






![[写真] ファム・ミン・チン首相が地方との政府オンライン会議を主宰](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/5/264793cfb4404c63a701d235ff43e1bd)





















































![[ビデオ] ペトロベトナム50周年記念式典の概要](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/4/abe133bdb8114793a16d4fe3e5bd0f12)

![[動画] ラム事務総長がペトロベトナムに8つの黄金の言葉を授与:「先駆者 - 優秀 - 持続可能 - グローバル」](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/23/c2fdb48863e846cfa9fb8e6ea9cf44e7)


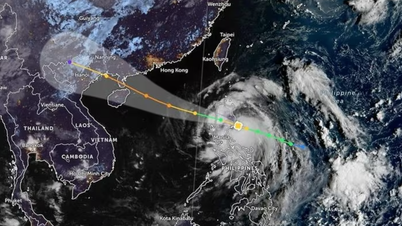
















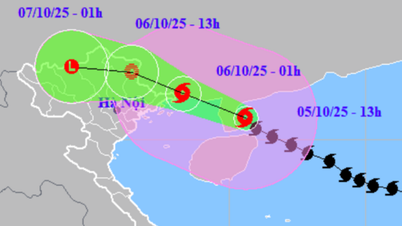














コメント (0)