ベトナムと日本の外交関係樹立50周年を記念したTG&VN新聞のインタビューで、日本の指揮者本名徹治氏は、ベトナム国立交響楽団と仕事をすることになったのは運命だったと語った。
 |
| 日本の指揮者、本名哲治。 |
彼は日本とヨーロッパで大きな成功を収め、数々の賞を受賞し、 世界中から招待を受けてきました。では、なぜ彼はベトナムに渡り、長年にわたりベトナム国立交響楽団に在籍してきたのでしょうか?
2000年10月、名古屋フィルハーモニー交響楽団と共演し、アジアに交響楽文化を届ける「トヨタクラシックツアー」を8カ国で開催しました。
ハノイは私にとって4番目の場所でした。ノイバイ空港からニッコー・ハノイ・ホテル(現ホテル・デュ・パルク・ハノイ)へ向かうバスの中で、通りの商店の黄色い灯りが作り出す光景に心を奪われました。フォーのレストランへ向かう夜道でも同じ光景でした。
| 11月28日夜、東京で行われたベトナム・日本外交関係樹立50周年記念式典において、ベトナム文化スポーツ観光省の主催と駐日ベトナム大使館の協力により、本名徹治指揮によるベトナム・日本友好コンサートが開催された。 |
コンサート会場はハノイ・オペラハウスでした。リハーサルの準備で客席に座っていた時、ふとロゴを見上げると「1911」という数字が目に入りました。敬愛する作曲家グスタフ・マーラーが亡くなった年です。その時、2011年はマーラーの死後100年、そしてハノイ・オペラハウスの100周年に当たる。そして、2011年に必ずこの地に戻り、マーラーの交響曲第九を演奏しようと心に誓いました!
その日のコンサートのソリストは、チェロ奏者のゴ・ホアン・クアン氏(当時、ベトナム国立交響楽団(VNSO)の首席チェロ奏者兼副指揮者)でした。演奏後、クアン氏が楽屋に私に会いに来てくれて、「手伝って、戻ってきてください!」と言ってくれました。「何かできることはありますか?」と尋ねると、クアン氏は「指揮、指導、何でもできます!でも、お金があまりないんです」と答えました。
こんなに早くベトナムに戻れるとは思ってもみませんでした。すぐに引き受けました。2001年に名古屋管弦楽団との契約を終え、2001年2月からベトナム国立交響楽団との縁が始まりました。2011年にはマーラーの交響曲第九番を演奏することができました。今振り返ると、まさに運命だったとしか言いようがありません。
ベトナム交響楽団との活動やプロジェクトについての印象や感想をお聞かせください。
数え切れないほどたくさんあります。2003年には、日本とベトナムの外交関係樹立30周年を記念して、大阪交響楽団と共演しました。2004年には、アジア・オーケストラ・ウィークの一環として、初めて日本で演奏しました。
 |
| 2023年4月6日、フェニーチェ堺劇場にて大阪交響楽団とのコンサートに出演する指揮者本名徹治とアーティストたち。 |
2005年には定期演奏会を始めました。次に2007年からは「トヨタ・コンサート・プログラム」を開催し、ベトナム各地で開催しました。ラオスやカンボジアへのツアーもありました。2007年から2012年にかけてはマーラーの交響曲全曲を演奏しました。2008年には東京グローバルフォーラムで開催されたラ・フォル・ジュルネ音楽祭へのツアーに参加しました。2009年から2011年にかけてはベートーヴェンの交響曲全曲を演奏しました。どれも素晴らしい思い出です。
2010年には東京交響楽団と共演し、ニューヨーク・フィルハーモニックを迎えました。同年、タンロン・ハノイ開城1000周年を記念し、世界中からゲストソリスト、合唱団、オーケストラを迎え、マーラーの交響曲第8番を演奏しました。
2011年は「ハーモニー・コンサート」と題した初のアメリカツアーとなり、カーネギーホール(ニューヨーク)とボストン・シンフォニーホール(ボストン)で開催されました。ボストン公演には多くのベテランが来場しました。
2013年、日越外交関係樹立40周年を記念し、オーケストラは日本国内7都市を巡回しました。東京での初演には、皇太子さま(現天皇)をお迎えしました。奈良・東大寺では、ベートーヴェンの「入寺」、「蜘蛛の糸」、「交響曲第7番」を演奏しました。「蜘蛛の糸」では、ベトナム代表アーティスト、レ・カン氏が演奏しました。
2014年にはディエンビエンフー勝利60周年記念コンサートを開催しました。2015年にはミーディン国立競技場で「秋の旋律」プログラムを開催しました。2018年には、日越外交関係樹立45周年を記念して日本ツアーを行い、天皇皇后両陛下もサントリーホールでコンサートにご臨席されました。
2020年6月、ベトナム国立交響楽団、ベトナム国立音楽院、ベトナム国立オペラ・バレエ団が共催し、「We Return」と題したコンサートが開催され、160名もの一流アーティストが参加しました。新型コロナウイルス感染症のパンデミックがほぼ終息に近づいたこの時期に、素晴らしい演奏を披露できたことは、私たちにとって素晴らしい思い出となりました。
 |
| 2020年6月19日夜、ベトナム国立音楽院で「We Return」コンサートが開催され、公安大臣のト・ラム氏が参加した。 |
2001年、私は「ハノイ国立交響楽団(VNSO)アップグレード・プロジェクトにおける音楽顧問兼オーケストラ指揮者」に任命されました。最初の契約は2005年まで有効で、VNSOをアジアレベルに引き上げることを目標としていました。そして2005年に締結された契約では、2010年までにVNSOを国際レベルに引き上げるという目標が設定されました。もちろん、これは容易な仕事ではなく、私一人では到底成し遂げられません。そのため、これまで定期的に優秀な音楽家をハノイに招き、共演しています。また、国際交流基金(日本)、ゲーテ・インスティトゥート(ドイツ)、フランス文化センター(フランス)、トランスポジション・プロジェクト(ノルウェー)からも長年にわたり支援を受けています。
音楽を通じてベトナムと日本の文化交流と相互理解を深めるためには何が必要か教えてください。
最近は音楽関係の人たちの交流も盛んになってきています。オーケストラやオペラ、バレエ団がベトナムから日本へ、あるいは逆に日本からベトナムへ公演することが当たり前になったら素晴らしいと思います。
日本とベトナムの外交関係樹立50周年を祝うために何か特別な計画はありますか?
3年をかけて構想を練った新作オペラ『アニオ姫』が、2023年9月22日~24日に初演されます。400年前のホイアンの王女(ゴック・ホア)と商人ナガサキ(荒木宗太郎)の恋物語を、ベトナムと日本を代表する一流オペラ歌手と舞台専門家が再現します。
 |
| オペラ「アニオ姫」は、約400年前、日本の江戸時代初期、ベトナムのホイアンのゴック・ホア姫と長崎の商人荒木宗太郎との真実の愛の物語に基づいています。 |
この劇には多くの特別な点があります。数々の名曲が使用され、音楽家トラン・マン・フンが作曲、演出、脚本を手掛け、詩人のハ・クアン・ミンが日本語とベトナム語で美しい歌詞を書いています。日本公演は11月4日に昭和女子大学人見記念講堂で開催されました。
ベトナムでの思い出に残る体験をシェアしていただけますか?
ベトナムの音楽家たちと作曲を共にする中で、不思議な美しさに出会いました。それは、他の国のオーケストラでは聴いたことのない音でした。これはベトナム人の感性によるものでしょうか、それとも言葉の美しさによるものでしょうか。心の痕跡のようなものが音に表れるのです。コンサートでは、言葉では言い表せないほど美しい音に出会うことがあります。
近年、若い音楽家の活躍は目覚ましいものがあります。才能豊かな生徒たちは、オーストリア、ハンガリー、ドイツ、スカンジナビア、アメリカ、ロシア、カナダといった国々に留学しています。注目すべき才能は数多くあり、ベトナムが世界の音楽大国に加わる日が来ると信じています。
指揮者の本名徹治氏は1957年日本生まれ。2000年にトヨタクラシックコンサートツアーでベトナムに来日。その後、ベトナム国立交響楽団の音楽顧問兼指揮者に就任。現在は同楽団の首席指揮者を務めている。同楽団に技術的・音楽的に多大な貢献を果たし、ベトナムへの研修プロジェクトや国際的なアーティストとの共演を数多く手がけてきた。 |
[広告2]
ソース






















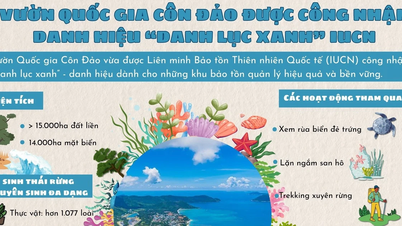
































































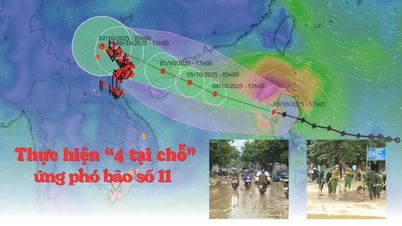


















コメント (0)