研究により、核実験や核事故による放射線が多くの動物の体内に蓄積されることがわかっています。
エニウェトク環礁のウミガメ
世界の放射能汚染の多くは、20世紀における核兵器開発競争の中で主要国が実施した実験に起因しています。アメリカ合衆国は1948年から1958年にかけてエニウェトク島で核兵器実験を行いました。
1977年、アメリカ合衆国は放射性廃棄物の除去作業を開始しました。その多くは近くの島のコンクリートピットに埋められていました。ウミガメの核放射能特性を研究している研究者たちは、除去作業によって汚染された堆積物が巻き上げられ、環礁のラグーンに堆積したのではないかと推測しています。この堆積物は、ウミガメが遊泳中に摂取したり、餌となる藻類や海藻類に影響を与えたりしたと考えられます。
研究対象となったカメは、浄化作業開始からわずか1年後に発見された。 パシフィック・ノースウエスト国立研究所の科学者で、この研究を率いたサイラー・コンラッド氏によると、堆積物中の放射能の痕跡がカメの甲羅に層状に刻み込まれていたという。コンラッド氏はカメを「泳ぐ年輪」に例え、木の年輪が年齢を記録するのと同じように、甲羅を使って放射線量を測定しているという。
ドイツ、バイエルンのイノシシ
核実験は、放射性物質の塵や灰を上層大気に放出することで汚染を拡大させ、地球を周回して遠方の環境に蓄積させます。例えば、バイエルンの森では、イノシシが極めて高い放射線レベルを示すことがあります。 科学者たちは以前、放射性物質の塵は1986年にウクライナのチェルノブイリ原子力発電所で発生したメルトダウン事故に起因すると考えていました。
しかし、最近の研究で、シュタインハウザー氏らは、バイエルン州のイノシシの体内に蓄積された放射能の68%が、シベリアから太平洋に至るまで行われた世界規模の核実験に由来するものであることを発見した。シュタインハウザー氏の研究チームは、放射性物質を含む様々なセシウム同位体の「核指紋」を調査することで、チェルノブイリが汚染源ではないことを明らかにした。イノシシは、近くの土壌に蓄積した放射性降下物から放射線を吸収したトリュフを食べて被曝した。
シュタインハウザー氏は、イノシシの肉(通常は舌から採取)のサンプルを研究し、肉1キログラムあたり1万5000ベクレルの放射線を検出しました。これは、欧州の安全基準である600ベクレル/キログラムを大幅に上回っています。
ノルウェーのトナカイ
チェルノブイリ原発事故は、放射性塵を大陸全土に撒き散らし、その痕跡は今もなお目に見えます。放射性塵の多くは北西方向にノルウェーまで吹き飛ばされ、雨となって降り注ぎました。塵の進路は天候に左右され、予測不可能でした。
ノルウェー放射線・原子力安全庁の科学者、ルンヒルド・ゲルスヴィク氏によると、放射性粉塵は菌類や地衣類に吸収される。菌類や地衣類は根系を持たず、空気から栄養分を吸収するため、放射性粉塵の影響を受けやすい。そして、それらはトナカイの餌となる。チェルノブイリ原発事故直後、一部のトナカイの肉には1キログラムあたり10万ベクレルを超える放射線量が含まれていた。
現在、放射性地衣類の大部分は動物に食べられており、ノルウェーのトナカイの放射能は欧州の安全基準を下回っています。しかし、野生キノコが例年よりも大量に生育する年には、トナカイの肉のサンプルの放射能濃度が2,000ベクレルに達することもあります。「チェルノブイリ由来の放射能は、土壌からキノコ、植物、動物、そして人間へと今も移行し続けています」とゲルスヴィク氏は言います。
日本のサル
日本では、アカゲザルも同様の問題に悩まされている。2011年の福島第一原子力発電所のメルトダウン後、近隣に生息するサルの体内のセシウム濃度は1キログラムあたり1万3500ベクレルにまで上昇したと、日本獣医生命科学大学の葉山真一教授率いる研究チームが報告している。
葉山氏の研究は、主にサルの後ろ足の組織サンプルに焦点を当てていました。その結果、サルは地元の木の芽や樹皮、キノコやタケノコといった様々な食物を摂取することで放射線を吸収した可能性が高いことが示されました。高濃度のセシウムから、研究者たちは事故後に生まれたサルは発育不全と小頭症に悩まされた可能性があると推測しました。
放射能汚染された動物を研究する科学者たちは、体内の放射線量が人間にとって脅威となる可能性は低いと強調しています。福島のサルのように、食料源ではないためリスクのない種もいます。一方、ウミガメのように、放射線量が非常に低いため危険ではない種もいます。バイエルンのイノシシやノルウェーのトナカイのように、安全でない肉が消費者に届かないよう厳重に監視されている種もあります。
アン・カン(ナショナルジオグラフィックによる)
[広告2]
ソースリンク





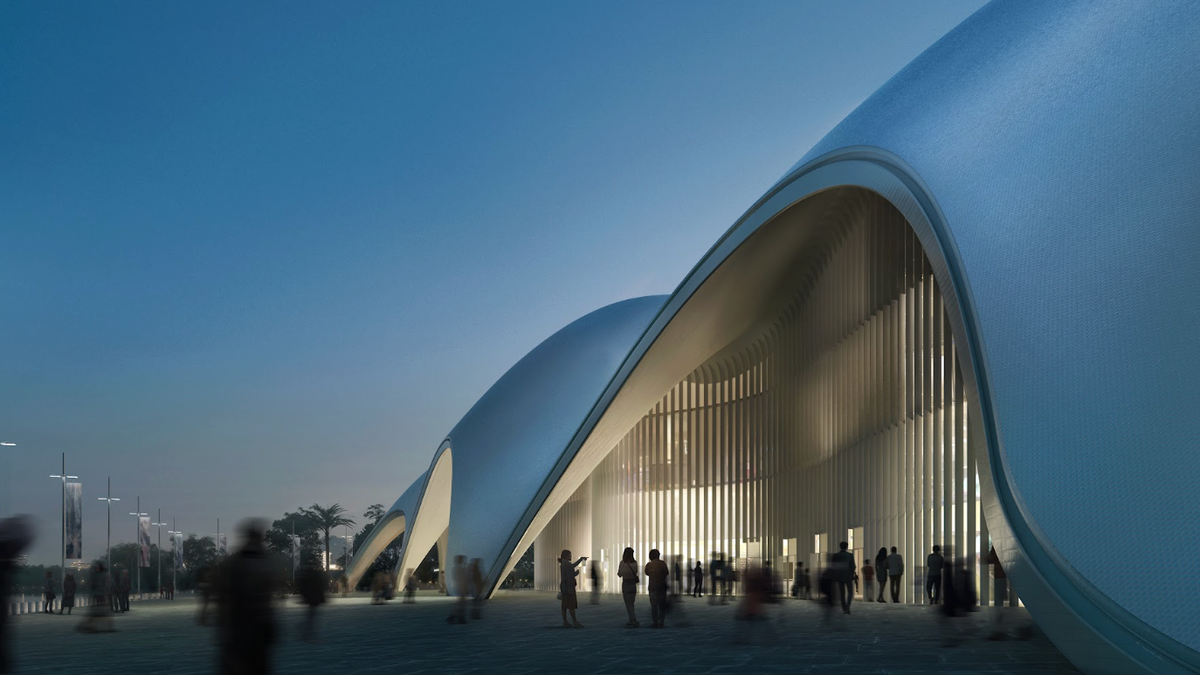

































































































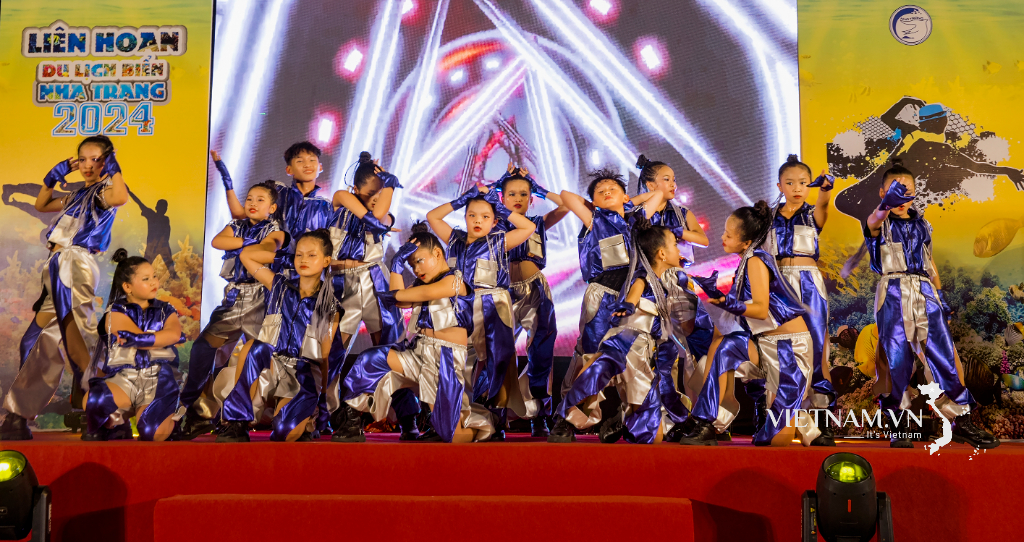

コメント (0)