 |
| 北京の周恩来首相とレ・ドゥック・ト同志。 |
ジュネーブ会議より
1954年5月8日、 ディエンビエンフーの圧倒的勝利の翌日、ソ連、アメリカ合衆国、イギリス、フランス、中国、ベトナム民主共和国、ベトナム国、ラオス王国、カンボジア王国の9つの代表団が参加し、インドシナ会議がジュネーブで開会された。ベトナムはラオスとカンボジアの抵抗勢力の代表者を会議に招待するよう繰り返し要請したが、受け入れられなかった。
会議に参加した関係者の文脈と意図について言えば、ソ連と米国間の冷戦が頂点に達していたことを強調できる。冷戦と並行して、朝鮮半島とインドシナ半島では熱い戦争が勃発し、国際的なデタントの潮流が生まれた。1953年7月27日、朝鮮戦争は終結し、朝鮮半島はかつてのように北緯38度線で分断された。
ソ連では、J・スターリンの死後(1953年3月)、フルシチョフ率いる新指導部は外交戦略を調整し、国際的なデタントを推進して内政問題に重点を置くようになりました。朝鮮戦争で損失を被った中国に対しては、中国は初の社会経済発展五カ年計画を策定し、インドシナ戦争の終結を望み、南方の安全保障を確保し、米国による包囲網と禁輸措置を打破し、米国をアジア大陸から遠ざけ、国際問題、とりわけアジア問題の解決において大国としての役割を推進しました。
8年間の戦争の後、人命と資源を失ったフランスは、名誉ある戦争からの離脱とインドシナにおける権益の維持を望んでいた。一方、国内では反戦勢力がホー・チ・ミン政権との交渉を求め、圧力を強めていた。イギリスはインドシナ戦争の拡大を望み、アジアにおける英連邦の統合に悪影響を及ぼし、フランスを支援した。
交渉を望まなかったアメリカだけが、フランスの戦争激化と介入拡大を支援しようとした。一方、アメリカはフランスをソ連に対する西欧防衛体制に引き入れたいと考え、フランスとイギリスの会議参加を支持した。
こうした状況下、ソ連はドイツ問題を協議するため、ソ連、米国、英国、フランスの外相による四カ国会議をベルリン(1954年1月25日から2月18日)で開催することを提案したが、失敗に終わったため、協議の場を朝鮮半島問題とインドシナ半島問題に変更した。朝鮮半島問題とインドシナ半島問題のため、会議はソ連の提案に基づき中国の参加を招請することに全会一致で同意した。
ベトナムについては、1953年11月26日、エクスプレッセン新聞(スウェーデン)のスヴァンテ・ロフグレン記者の質問に答えたホー・チ・ミン主席が停戦交渉に参加する用意があると表明した。
8回の全体会議と23回の小規模会議、そして緊密な外交交渉を経た75日間の困難な交渉を経て、1954年7月21日に協定が調印されました。この協定には、ベトナム、ラオス、カンボジアにおける3つの停戦協定と、13項目からなる会議最終宣言が含まれていました。米国代表団は署名を拒否しました。
協定の主な内容は、会議参加国がベトナム、ラオス、カンボジアの独立、主権、統一、領土保全を尊重することを宣言すること、敵対行為を停止し、武器や軍人の輸入、外国軍事基地の設置を禁止すること、自由な総選挙を実施すること、フランスが軍隊を撤退させて植民地体制を終わらせること、北緯17度線をベトナムの暫定軍事境界線とすること、ラオスの抵抗勢力がラオス北部に2つの集結地を設けること、カンボジアの抵抗勢力がその場で武装解除すること、国際監視委員会にインド、ポーランド、カナダが含まれることなどである。
1946年3月6日の暫定協定と9月14日の暫定協定と比較すると、ジュネーブ協定は大きな前進であり、重要な勝利でした。フランスは独立、主権、統一、領土保全を認め、ベトナムから軍隊を撤退させなければなりませんでした。我が国の国土の半分が解放され、後の完全な解放と国家統一のための闘争における重要な後方拠点となりました。
この協定は大きな意義を持つものの、同時にいくつかの限界も抱えている。この協定は、ベトナム外交にとって、独立性、自立、国際連帯、軍事力、政治力、外交力の融合、戦略研究、そして特に戦略的自立といった貴重な教訓を残している。
1953年11月26日、エクスプレッセン紙への回答で、ホー・チ・ミン主席は次のように断言した。「停戦交渉は、主にベトナム民主共和国政府とフランス政府との間の問題である」。しかし、ベトナムは多国間交渉に参加し、9カ国のうちの1カ国に過ぎなかったため、自国の利益を守ることは困難だった。上級中将でベトナム戦争研究家のホアン・ミン・タオ教授は次のように述べている。「残念ながら、我々は主要国が主導する多国間フォーラムで交渉を行っており、ソ連と中国にも我々が十分に理解していない計算があったため、ベトナムの勝利は十分に活かされなかった。」
 |
| ソ連共産党書記長ブレジネフは、1973年1月に帰国の途に着く途中、パリ協定に署名した後、レ・ドゥク・トー同志を迎えて会談を行った。 |
ベトナムに関するパリ会議へ
1960年代初頭、国際情勢は重要な展開を見せた。ソ連と東欧の社会主義諸国は引き続き体制を強化し発展を遂げたが、中ソ対立は激化し、国際共産主義運動と労働運動における分裂も深まった。
アジアとアフリカでは、民族独立運動が引き続き力強く発展しました。ピッグス湾(1961年)での失敗後、米国は「大規模報復」戦略を放棄し、民族解放運動に対する「柔軟な対応」戦略を提唱しました。
米国は南ベトナムで「柔軟な対応」戦略を適用し、米国の顧問、装備、武器を備えた強力なサイゴン軍を建設するための「特別戦争」を遂行した。
「特殊戦争」は破綻の危機に瀕していたため、1965年初頭、アメリカはダナンとチュライに部隊を派遣し、南ベトナムで「局地戦争」を開始した。同時に、1964年8月5日、アメリカは北ベトナムでも破壊戦争を開始した。第11回中央会議(1965年3月)と第12回中央会議(1965年12月)は、祖国を救うためにアメリカに抵抗する決意と方向性を再確認した。
1965~66年と1966~67年の二度の乾期における北方殲滅戦争に対する反撃が成功した後、我が党は「交渉しながら戦う」戦略への転換を決定した。1968年初頭、我々は総攻撃と蜂起を開始した。これは失敗に終わったものの、致命的な打撃を与え、アメリカ帝国主義者の侵略意志を揺るがした。
1968年3月31日、ジョンソン大統領は北ベトナムへの爆撃停止を決断せざるを得なくなり、ベトナム民主共和国との対話に代表団を派遣する準備を整え、パリ交渉(1968年5月13日から1973年1月27日)を開始した。これは極めて困難な外交交渉であり、ベトナム外交史上最長の交渉となった。
会議は二段階に分かれて行われた。第一段階は1968年5月13日から10月31日までで、ベトナム民主共和国とアメリカ合衆国の間で、米国による北ベトナム爆撃の完全停止に関する交渉が行われた。
1969年1月25日から1973年1月27日までの第二段階:ベトナム戦争の終結と平和の回復に関する四者会議。この会議には、南ベトナム人民軍(DRV)と米国代表団に加え、南ベトナム民族解放戦線(NLF)/南ベトナム共和国臨時革命政府(PRG)とサイゴン政府が参加した。
1972年春夏選挙での勝利と米国大統領選挙が近づく中、ベトナムは1972年7月中旬から協定署名に向けた実質的な交渉に積極的に動き始めた。
1973年1月27日、両当事者は、ベトナム政治局の4つの要求、特に米軍の撤退と我が国の軍隊の駐留を満たした、9章23条、4つの議定書と8つの了解事項からなる「ベトナム戦争終結と平和回復協定」と呼ばれる文書に署名した。
パリでの交渉はベトナム外交に多くの大きな教訓を残した。独立、自立、国際連帯、国家力と現代力の融合、外交の表舞台、交渉術、世論の闘争、独立と自立を中心とした戦略的研究などである。
1954年のジュネーブ会議の教訓を踏まえ、ベトナムは対米抵抗政策、そして独立と自治を掲げる外交政策と外交戦略を独自に立案・実行しましたが、常に友好国との連携を保ちました。ベトナムはアメリカと直接交渉しました。これが、祖国を救うための対米抵抗戦争における外交的勝利の最も根本的な理由でした。これらの教訓は今もなお生き続けています。
 |
| 1973 年 1 月 28 日のニューヨーク デイリー ニュースの表紙。内容は「和平調印、徴兵終了、ベトナム戦争終結」。 |
戦略的自律性
パリ交渉(1968~1973年)における独立性と自律性の教訓は、現在国際的な学者たちが議論している戦略的自律性の問題と関連しているでしょうか?
オックスフォード辞典によると、「戦略」とは長期的な目標や利益、そしてそれらの目標を達成するための手段を特定することであり、「自律性」とは、自らを統治し、独立し、外部要因の影響を受けない能力を指します。「戦略的自律性」とは、主体が自らの重要な長期的な目標や利益を決定し、実行する際に、独立性と自立性を発揮することを指します。多くの学者が戦略的自律性について一般化し、様々な定義を与えています。
実際、戦略的自治という概念は、ホー・チ・ミンによって遥か昔に肯定されていた。「独立とは、外部からの干渉を受けずに、自らのあらゆる活動を統制することだ」。1948年9月2日の独立記念日のアピールにおいて、彼はこの概念をさらに発展させ、「独立した軍隊、独立した外交、独立した経済を持たない独立。ベトナム国民は、そのような偽りの統一と独立を決して望んでいない」と述べた。
したがって、ベトナム民族は独立し、自主独立し、統一され、領土が保全されているだけでなく、国家の外交も独立しており、いかなる権力や勢力にも支配されてはなりません。国際共産党と労働者党の関係において、彼は次のように断言しました。「政党は、規模の大小を問わず、独立し、平等であると同時に、団結し、一致して互いに助け合っている。」
彼はまた、国際援助と自立の関係を明確にした。「ソ連と中国をはじめとする友好国は、我々が自立するための条件をより整えるため、無私かつ寛大に我々を援助するために全力を尽くしてくれた」。連帯と国際協力を強化するためには、まず独立と自治を促進しなければならない。「自立せず、他国からの援助を待つ国は、独立に値しない」。
独立と自力更生は、ホー・チ・ミン思想において顕著かつ一貫した思想です。その思想の根本原則は、「他者の助けを求めるなら、まず自らを助けなければならない」というものです。独立と自力更生の維持は、ホー・チ・ミン思想の指針であり、不変の原則でもあります。
ベトナムはジュネーブ交渉から学び、パリ協定交渉において、ホー・チ・ミンの外交政策の根本理念である自立と自主性の教訓を強調した。これは、現在国際的な研究者が熱心に議論している戦略的自主性でもある。
1. 上級中将、ホアン・ミン・タオ教授「ジュネーブ会議によるディエンビエンフー勝利」『ジュネーブ協定50周年の振り返り』、国立政治出版社、ハノイ、2008年、43頁。
出典: https://baoquocte.vn/tu-geneva-den-paris-ve-van-de-tu-chu-chien-luoc-hien-nay-213756.html










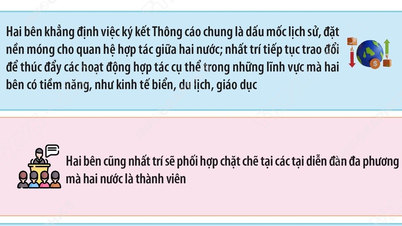

![[写真] 大統領がベトナム国連代表部を訪問](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/24/b97c02dea2634eb38b94b1d6145671e3)










































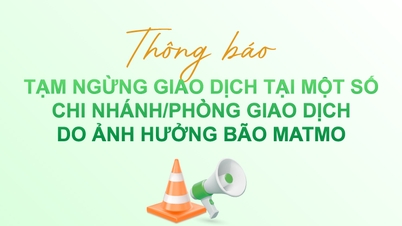



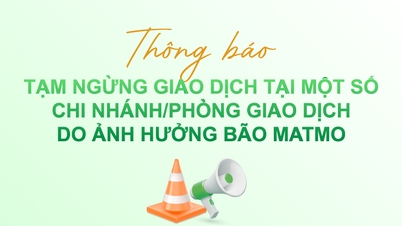







































コメント (0)