国立経済大学(NEU)は2024年に6つの新しい専攻を開設する予定です。そのうち4つは、ソフトウェア工学、情報システム、人工知能、情報セキュリティを含むコンピューターと情報技術分野です。4つの専攻はすべて、学士課程とエンジニア課程の2つの体系で教育を行い、専攻ごとに50~100人の学生を受け入れる予定です。
対外貿易大学(FTU)もコンピューターサイエンスの学生を入学させる予定で、今年の目標は30名で、今後数年間で増加する可能性があります。

かつては専門分野の育成に力を入れていた大学でも、今では多くの新しい専攻が開設されている。(イラスト写真)
大学の動向
国民経済大学研修管理学部長のブイ・ドゥック・トリウ准教授は、目標とデジタル時代に適応するために、科学技術分野でさらに多くの分野を開発することが、大学の当面の、そして長期的な課題であると説明した。
国民経済大学が開設を予定している技術・工学専攻もまた、経済学と経営学に重点を置いた志望志向を持つ点で他とは異なります。同校の専攻開設計画は4月13日までに完了し、教育訓練省への報告に向けて承認される予定です。
貿易大学副学長のファム・トゥ・フオン准教授は、テクノロジー分野の新専攻開設について、これは学校側のニーズと、時代とともに変化する社会の観点から生まれた避けられない傾向であると述べた。
かつて、発展レベルがそれほど高くなかった時代は、既存の、そして明確に見える問題をいかに解決するかが課題でした。しかし、発展レベルが高まった現在では、問題が生じて顕在化してから解決策を見つけるのではなく、社会の動向や問題を事前に予測し、解決していくことが重要になります。
さらに、世界の現在の教育動向を見ると、世界のトップ大学は経済学、ビジネス、テクノロジーの分野間の密接な連携も確立していることがわかります。これまで、世界のトップ大学は経済学とビジネス分野において科学技術開発専攻を育成してきました。
貿易大学がこの専攻の開設を思いついたのは今日になってからですが、過去3年間準備を進めてきました。 「市場調査を実施し、サテライトプログラムを開設して3年間で、雇用主と従業員からの需要が非常に高いことがわかりました」と副学長は述べています。
経済系の大学がテクノロジー専攻を開設することによる質への懸念に直面し、貿易大学研修管理部長のヴー・ティ・ヒエン准教授は、コンピューターサイエンス専攻を開設する計画は2021年から大学によって立てられたと語った。
枠組みができた後、学校はコンピュータサイエンスを3ヶ月で15単位の短期研修プログラムとして試行しました。修了時には、学内外の学生に修了証が授与されます。
さらに、貿易大学のコンピュータサイエンス専攻は、トレーニングの強みを活かすために、経済とビジネスの分野での応用を目的として構築されています。
ヒエン氏は、コンピュータサイエンス専攻の開設は熾烈な競争になると見ている。IT人材の需要は膨大である一方、この専攻を育成する大学も数多く存在する。しかし、各大学にはそれぞれ独自の候補者リストがあり、質の高い環境を整え、それぞれの強みを活かすことができれば、優秀な大学は「分野横断的」であるかどうかに関わらず、必ず入学できるとヒエン氏は考えている。
「多くの人が依然としてテクノロジーやエンジニアリングの学校の強みだと考えている専攻を開設することに、私たちは自信を持っています」とヒエン氏は断言した。

専門家は、登録や希望の選択をする前に、情報を慎重に調べるよう候補者にアドバイスしている。(イラスト写真)
トレーニングの質が心配ですか?
経済専門学校が新たなテクノロジー・研究専攻を開設するのは今年が初めてではありません。2020年からは、ダナン経済大学が「データサイエンスとビジネスアナリティクス」という新たな専攻を開設しました。
2021年には、バンキングアカデミーが新たな専攻を開設し、情報技術の学生を募集します。2023年には、ホーチミン市経済大学がEobotや人工知能、物流技術といった技術系専攻を含む一連の新たな専攻を開設する予定です。
逆に、技術分野の多くの大学でも経済学を専攻する学生を受け入れています。例えば、ハノイ工科大学では経営学、金融・銀行学、会計学の教育が行われています。また、水資源大学では法律と言語の教育が行われています。
一部の専門家によると、学際的な大学は世界共通のトレンドであり、学際的な教育の潮流と一致しています。ベトナムでは、持続可能な発展を確保するためには、大学の学際的・多分野化への発展が不可欠です。しかし、あらゆる面で十分な準備をせずに性急にこの潮流に追従すれば、特に教育の質において非常に危険な状況に陥るでしょう。
ハノイ国立大学(ハノイ工科大学)評議会議長のグエン・ディン・ドゥック教授は、専攻分野の設立は容易なことではないと述べました。十分な人材を確保するだけでは不十分であり、これは最低限の条件に過ぎないからです。
産業の構築には努力が必要であり、チームの構築、構築は学校の研究指向と開発戦略に結びついていなければなりません。
「私の見解としては、学校は開校前に明確な発展戦略を構築し、職員の育成、研究の方向性、質を確保するための基本条件、そして将来のキャリアプランのためのロードマップを策定する必要がある。無差別に開校すべきではない」とグエン・ディン・ドゥック氏は述べた。
ハノイのある大学の学長も、学際的な教育は不可欠だと述べました。しかし、新しい専攻を開設する際に重要なのは、市場のニーズと潜在力を正しく評価することです。多数派に追従して人材を過剰供給すれば、無駄になってしまいます。ベトナムの大学は、例えば金融や銀行の分野において、この点について多くの教訓を得ています。
ホーチミン市国家大学の試験・訓練品質評価センター所長、グエン・クオック・チン博士によると、トレンドを追って専攻を新設したり、「トレンド」に従って専攻名をつけたりすることは、本質的には昇進の一形態であり、志望者は慎重に調査する必要があるとのことだ。
マイクロチップ設計など、新しい名称で新しい専攻を開設する学校もありますが、研修内容は既存の専攻とほとんど変わりません。単に名称を変え、単語をいくつか付け加えただけの形式的なものであり、本質は変わっていません。
これは、新たに設計された研修プログラムで新しい専攻を開設することとは全く異なります。したがって、志望者は各学校の研修プログラムを慎重に検討し、自分の希望に合った専攻を選択する必要があります。
専門家によると、ほとんどの大学は自治権を導入しており、規定に従って独自の専攻を開設することが認められているが、教育訓練部は各段階に応じて適切な訓練専攻を開発する計画を立て、専攻の広範な開設が訓練の質に影響を与え、将来的に専攻と人材の構成に不均衡をもたらすのを避けるべきだという。
[広告2]
ソース





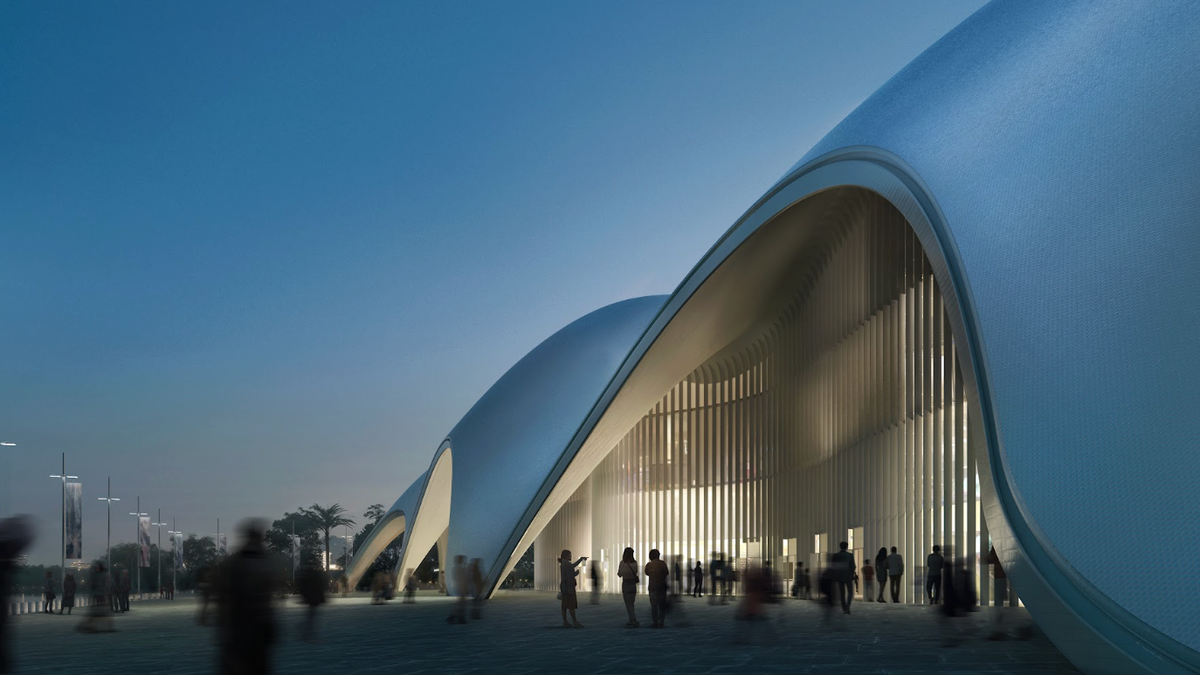





























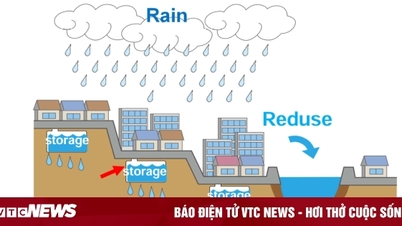



































































コメント (0)