インドのナレンドラ・モディ首相は、2024年10月22日、ロシアのカザンで開催された第16回BRICS首脳会議の傍らで、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領と会談した。写真:ANI/TTXVN
インドの外交政策の目的と原則
インドにとって、外交政策の二つの中核目標は、国家安全保障と国民の繁栄である(1) 。「インドの国益の追求と確保」という目標は、2019年にインド外務省によって正式に提唱された。ナレンドラ・モディ首相がかつて述べたように、「インドの世紀」を目指し、「インドを単なる世界的な均衡勢力ではなく、主導的な地位に置き」、「すべてのインド人の安全と繁栄のためにインドの改革と変革を促進する」ことを目指している(2) 。
言い換えれば、インドの外交政策の目標は、安全保障(領土と国民)、 経済発展、エネルギー安全保障、核能力と核不拡散、そして主要国になるという最終目標を達成するための国際的な地位とイメージに重点を置いています(3) 。
より具体的には、インド外務省によると、インドの外交政策には、1. 伝統的および非伝統的な安全保障上の脅威からインドを保護すること、2. インドの総合的な発展に資する外部環境を形成すること、3. 国際フォーラムでインドの声が聞かれ、尊重され、インドがテロ、気候変動、軍縮、世界統治機関の改革などの地球規模の問題に取り組む責任ある主体となることを確保すること、4. 海外のインド人コミュニティを保護すること(4)という 4 つの主要目標が含まれています。
持続可能な開発パートナーとしてのインドの役割へのアプローチが新たな協力の道筋を形作る中、インドの開発パートナーシップ・モデルは、信頼、尊重、主権、透明性、協力、そしてパートナー国の要求と利益の尊重に基づいています。したがって、インドの外交政策は、「2D-1H」アプローチ、すなわちインドの発展と世界の利益のための対話、外交、そしてハイフネーション(連携)という観点から定義することができます(5) 。1947年以来のインドの外交政策の実施において注目すべき特徴は、インドが常に憲法の原則に従ってきたことです。国際平和と安全の促進に関するインド憲法第51条の精神に基づき、インドは以下のことに努めています。1. 国際平和と安全の促進。2. 国家間の公平な関係の維持。3. 国際法および国際義務の尊重の促進。3. 仲裁による国際紛争の解決の促進。これらの憲法原則は、インドの外交政策の指針を通して明確に具体化されています。
一つは、平和共存(パンチシール)の原則である。これはインドの外交政策の指針とされている。この原則は、インドと中国の間で締結されたパンチシール協定において初めて言及された。それ以来、平和共存の原則は、インドと他国との二国間関係の指針となっている。平和共存の原則は、後に1955年にインドネシアで開催されたアジア・アフリカ会議で調印されたバンドン宣言にも盛り込まれた。これらは、非同盟運動(NAM)の中核原則でもある。この原則は、インドの外交政策を策定する過程で世界平和を重視する哲学から生まれたものである。この原則の内容は、1- 互いの領土保全と主権の尊重、2- 不可侵、3- 互いの内政不干渉、4- 平等と相互利益、5- 平和共存(6)などである。
第二に、世界は一つの家族(vasudhaiva kutumbakam)である。この概念は、ジャワハルラール・ネルーからナレンドラ・モディまで、何世代にもわたるインドの指導者によって唱えられてきた。古代インドの文献であるマハー・ウパニシャッドから引用された「vasudhaiva kutumbakam」の詩節は、インド国会の玄関ホールに刻まれており(7) 、世界は一つの家族であることを強調している。この概念の意味は多くの異なる文脈で用いられてきたが、最も一般的な見解は、「vasudhaiva kutumbakam」の理想は、インドの世界システムへの参加における利益よりも、他者の利益の尊重、地球規模での一体感と共有責任の促進といった価値観を指しているというものである。この視点はまた、気候変動、持続可能な開発、そして多様な文化や信仰の間の平和と寛容の促進といった差し迫った地球規模の問題への対処にも特に重点を置いている。 「世界は一つの家族」という理念は、人類の相互関係と団結の重要性を強調するものです。最近では、「世界は一つの家族」という視点が、インドが議長国を務める2023年のG20サミット(8)のテーマにも選ばれました。これを受けて、2023年のG20のテーマは「一つの地球、一つの家族、一つの未来」となります。
第三に、制裁・軍事行動を支持しません。国際政治において、インドは、国連が国際的なコンセンサスに基づき承認した場合を除き、他国または国家グループによるいかなる国に対する制裁・軍事行動も支持しません。したがって、インドは国連平和維持活動にのみ参加しています。この原則に基づき、インドは他国の内政干渉に反対します。しかしながら、いかなる国によるいかなる行動も、意図的か否かを問わず、インドの国家利益を侵害する恐れがある場合、インドは躊躇することなく迅速かつ迅速に介入します。
第四に、同盟の形成ではなく、パートナーシップの構築における戦略的自立性です。非同盟はインドの外交政策の最も重要な特徴です。この政策の核心は、いかなる軍事同盟にも参加しないことで外交における独立性を維持することです。非同盟とは、中立、不関与、孤立といったことではありません。積極的かつダイナミックな概念です。この原則は、インドが国際問題において、個々の事例に基づいて独立した立場を取り、いかなる軍事陣営の影響も受けないことを強調しています。
インドの現在の非同盟の原則は、多国間同盟と戦略的自治の概念を通じて継承され、発展してきました。インドの外交政策における戦略的自治とは、外交政策を実施する際の決定権と戦略的自治を指します。インドは独立以来、外交政策において戦略的自治の原則を維持してきました。今日、多極化した世界秩序の台頭という文脈において、インドの戦略的自治の原則は変わっていません。この原則は、外交政策の決定と国益の保護におけるインドの戦略的自治を確保するために、対外依存を抑制する方法として説明されています。それに加えて、常に相互依存している国際システムにおける意思決定の自治を最大限にするために、戦略的分野で大きな独立性を維持し、特により強い国への依存を回避します。 インドは戦略的自律性の観点から、同盟、特に軍事同盟ではなく、パートナーシップの構築に重点を置いています。一方、国際関係において戦略的自律性の原則を維持することは、すべての国々の共通利益の共有に基づく多国間主義と民主化に向けた国際システムの推進に貢献します。
第五に、地球規模の問題に関する地球規模の対話と合意。インドは、貿易自由化、気候変動、テロリズム、知的財産権、グローバルガバナンスといった地球規模の問題に関して、地球規模の対話と合意の原則を追求しています。
第六に、国際紛争の平和的解決。 1947年以来、インドの外交政策における一貫した視点は、国際紛争の平和的解決です。この原則は、国連憲章の原則の一つでもあります。国際紛争の平和的解決という視点は、領土紛争を抱える近隣諸国との国境問題、イランの核問題、中東紛争、ロシア・ウクライナ紛争などの平和的解決への支持といったインドの姿勢に明確に示されています。さらに、インドは国際問題の解決における外国の軍事介入に常に反対してきました。
上記の原則に加え、インドは国際法の尊重と優位性の原則を追求し、公正かつ公平な世界秩序を追求します。 プレス 国際法および/または国連が提唱する国家の主権平等原則、他国の内政不干渉の原則を尊重する。インドは、脱植民地化プロセスを支援し、国連平和維持活動に積極的に参加することで、世界平和の維持に重要な役割を果たしている。また、国連が追求する世界的な軍縮目標を支持し、国連安全保障理事会をはじめとする国連機関の改革を提案・支持している。
要するに、インドは外交政策を国家の発展、安全保障、そして繁栄のための手段と捉えています。インドの外交政策の主要原則は、国際舞台における対話と関与の支持、主権と領土保全の尊重、内政不干渉、世界の平和と安定へのコミットメント、そして南半球諸国との連帯です。
インドの外交政策の内容
外交政策の面では、インドは自国の成長と発展に資する多極化した世界を目指しており、互恵的なパートナーシップと課題に基づくパートナーシップのネットワーク構築を基盤として、あらゆる国々とバランスの取れた関係を維持することを目指しています。この目標は、インドを「主導的な大国」 (9)にすることであり、インド文明の輝きを取り戻し、国際システムにおけるより卓越した地位を確保することです。
1947年以来、インドの外交政策は継承と柔軟な調整の長い道のりを経てきました。
第 1 段階(1947 年 - 1962 年): インドは国際関係において理想主義を追求し、非同盟外交政策を徹底的に実施し、主権侵害に反対し、経済の再建に重点を置き、より公平な世界秩序に向けてアジアとアフリカ諸国の「指導的」役割を果たそうとしました。
第二期(1962年 - 1971年):この10年間は、インドの外交政策においてプラグマティズムが重視された時期であり、特に日中戦争(1962年)およびパキスタン戦争(1965年)以降、その傾向が顕著であった。これらの二つの出来事は、インドの安全保障政策が理想主義から実用主義へと転換した要因と考えられている。
第三期(1971年~1991年):インドはバングラデシュ人民共和国の建国に伴い、南アジア地域における役割を拡大した。この時期には、米中パキスタン連合の台頭、ソ連と東欧における社会主義モデルの崩壊、そして1991年の経済危機により、インドは内外政策の基本原則の見直しを迫られた。
第四期(1991年~1999年):インドは戦略的自立政策の実施に重点を置いた。ソ連と東欧における社会主義モデルの崩壊後、インドは経済を世界に開放した。これは、インドの新たな外交目標と戦略に明確に反映されていた。
第五期(2000年~2013年):この期間、インドの外交政策は「バランシング・パワー」としての特徴を帯びるようになった。インドは米国との核協定を締結し、西側諸国との関係改善、ロシアとの関係強化を図り、中国とは貿易と気候変動に関する共通認識に達した。
第六段階(2014年~現在):これはインドの「積極的外交」の段階とみなされています。世界有数の民主主義国として、インドは安定、発展、そして独立した世界観を持ち、ますます多極化する世界において、政治的・経済的に中核となる準備ができています。
1947年以来、インドは国際秩序の形成に大きく貢献してきました(10) 。その発展段階は、歴史的各時期におけるインドの中核政策の内容を反映するだけでなく、「新しいインドの新たな戦略」を形成する同国のダイナミズムをも示しています。
今日、インドは、政治倫理(11)を中核とする新たな一連の原則に基づき、人々を中心とする多極的な世界秩序、21世紀の現実に基づいた新たな世界秩序、すなわちナショナリズムとリベラリズムが共存し、南半球の国々が主な利害関係者となる秩序を粘り強く追求している。言い換えれば、インドはルールに基づく世界秩序に加えて、価値観に基づく世界秩序の構築を目指している。倫理と価値観は、人々が中心となる政治倫理に基づく世界秩序の構築に貢献する上で各国を導く一連の原則であると考えられている。インドのN・モディ首相はかつて、対応、認識、尊重、改革を含む4Rの枠組みを通じて、人間中心のグローバリゼーションに言及した。これにより、バランスのとれた包括的な国際アジェンダを構築することで、南半球の優先事項に対応している。
上記の側面に加えて、最近インドの外交政策で頻繁に言及されているのは、南半球諸国が徐々に繁栄する北半球へと向かっているという文脈での南半球諸国との連帯である(12) 。インドは、2023年1月に第1回南半球の声サミット、2023年11月に第2回、2024年8月に第3回を主催した。サミットで、インドのN・モディ首相は、世界的に不安定さが増す文脈で各国間の連帯を呼びかけ、同時に、各国に債務負担を課すことなく持続可能な成長に焦点を当てた「世界開発協定」を提案した。約125カ国が第3回南半球の声サミットに出席したという事実は、南半球諸国に対するインドの影響力を示している。
インドの外交政策のもう一つの側面は、インド系ディアスポラ(インド系移民)への対応です。インド系ディアスポラは世界で最も古く、最大のディアスポラ・コミュニティの一つであり、約3,200万人のインド系住民がいます。インドのインド系ディアスポラへのアプローチは、ケア(思いやり)、コネクト(繋がり)、セレブレーション(祝福)、コントリビュート(貢献)の4Cを特徴としています。これは、ディアスポラの幸福を保障し、彼らをそのルーツに結びつけ、インドの発展における彼らの功績と貢献を称えることを目的としています。
同盟を構築しないという原則に基づき、インドは国益に資する多国間同盟戦略を優先し、経済安全保障、エネルギー、安定、そして総合的な発展のための平和、対話、外交といったグローバルな課題を推進しています。インドは、国連、関税及び貿易に関する一般協定(GATT)、世界貿易機関(WTO)、世界保健機関(WHO)、ブレトンウッズ体制といった国際機関の改革に積極的に参加するとともに、南半球諸国との関係強化にも尽力しています。
インドの優先パートナー
インドの外交政策において、南アジアの近隣諸国は最優先事項とみなされている。これは、南アジア諸国との戦略的信頼関係を強化し、関係を再構築し、友好と互恵的な協力の架け橋を築くという、N・モディ首相と前政権の外交政策の延長である。2014年5月26日の就任式で、N・モディ首相は南アジア地域協力連合(SAARC) (13)に加盟している南アジア諸国のすべての首脳を出席させるなど、南アジア近隣諸国に対する特別な敬意を示した。また、最初の任期中、N・モディ首相はすべてのSAARC加盟国(政情不安のためモルディブを除く)を訪問した。南アジア諸国との協力を制度化するため、インドはSAARCやベンガル湾多分野技術経済協力イニシアティブ(BIMSTEC)のプロセスを通じて南アジア統合を促進することに尽力している。インドはパキスタンや中国などの大国にも関心を持っている。
2023年にインドネシアのジャカルタで開催された第43回ASEAN首脳会議および関連会議に出席したファム・ミン・チン政治局員兼首相とインドのナレンドラ・モディ首相。出典:baochinhphu.vn
次に、外交政策における周辺国への重点についてです。「アクト・イースト」政策と「コネクト・ウェスト」政策は、インドの周辺国への重点を最も明確に示している2つの政策です。「ルック・イースト」政策(LEP)が「アクト・イースト」政策(AEP)に調整された後、インドの優先パートナーには、東南アジア諸国(ASEANを中心とする)、北東アジア(中国、日本、韓国)、南太平洋(オーストラリア、ニュージーランド)、そしてロシアが含まれています。さらに、インドの段階的な拡大と連携に加え、AEPをインドのインド太平洋構想の重要な一部と捉え、インド太平洋地域における米国、オーストラリア、日本、韓国はインドの外交政策における主要なパートナーとみなされています。これにより、インドは東南アジアとの経済・外交関係の改善だけでなく、インド太平洋地域諸国との防衛・安全保障関係も強化しています。これは、インドがインド太平洋地域の安定に重要な役割を果たす準備ができていることを示しています。
インドの現在のパートナーは、東側諸国に加え、アデン湾からマラッカ海峡に至る西側諸国にも広がっており、中東諸国やアフリカ諸国も含まれています(14) 。したがって、インドは「西側を繋ぐ」政策(15)の枠組みの中で、アラブ湾岸諸国、イスラエルとイラン、そしてアフリカ諸国という3つの主要軸に重点を置いています。
インドの外交政策は、国際平和と安全保障における主要プレーヤーとしてのインドの地位を確立することを目指し、中央アジア、西ヨーロッパ、北アメリカ、ラテンアメリカ、北半球、太平洋諸島、カリブ海諸国を含む世界の他の地域にも向けられています。
インドは総じて一貫して独立した外交政策を追求し、国益に基づく戦略的自主性の維持を重視してきました。いかなる同盟構造にも参加していないものの、インドは相互信頼と協力に基づき、世界中に互恵的な関係とパートナーシップのネットワークを構築してきました。
インドの外交政策が示唆するいくつかの問題
数十年にわたり、地域情勢および世界情勢の複雑な変化にもかかわらず、ベトナムとインドの関係は常に持続可能な友好関係を維持し、あらゆる分野で良好な発展を遂げてきました。インドの外交政策実施の経験は、以下の点を示唆しています。
まず、国家の「対外アイデンティティ」の構築です。1947年から現在に至るまで、インドの外交政策の調整過程において、戦略的自主性と「世界は一つの家族」という二つの基本原則が一貫して堅持されてきました。これは、国際関係における「倫理的要素」を重視するインドの「対外アイデンティティ」を形作ってきました。これは、豊かな戦略的文化と深い価値観を持つインドの外交政策を反映し、多国間主義の推進を基盤とした多国間協調外交政策を展開するための基盤となっています。
第二に、南半球諸国と連帯し、包摂性、代表性、公平性の原則に基づくグローバルガバナンスを支持する。近年のインドの外交政策、特に2023年のG20議長国として「一つの地球、一つの家族、一つの未来」という理念を重視する役割において、インドは「世界の友人」(ヴィシュワ・ミトラ氏)となることを望んでいるだけでなく、 インドは、北半球と南半球の国々の間の溝を埋めるだけでなく、分断が深まる世界における分裂と紛争を克服するために、南半球諸国との連帯と共同行動を促進する姿勢を示しています。インドは、南半球諸国の利益と願望をG20の議題の中心に据え、これらの国々に国際フォーラムにおけるより大きな発言権と地位を与えることに貢献することを表明します。
第三に、バランスのとれた多角的な外交政策、すなわち利益と課題に基づくパートナーシップの構築です。インドの経験から判断すると、バランスのとれた外交政策こそが、インドの現在の成功、すなわち「均衡のとれた大国」を生み出したと言えるでしょう。現在、インドは東西関係における成功モデル、先進国と発展途上国の架け橋、そして南半球諸国の「主導国」としての役割を担っていると考えられています。
第四に、多国間機関を最大限に活用し、グローバル・ガバナンスにおける各国の願望を反映し、発言力と地位を高める。インドは、一方ではグローバル・ガバナンスにおける様々な課題に対するアイデアや解決策を提示し、他方では地域および世界共通の課題において積極的な役割を発揮するために、多国間機関を有効活用してきたことがわかる。
---------
* 本論文は、大臣級重点プログラム「新時代の統合と国家発展の目標に資するための2030年までの世界情勢の研究」に基づく大臣級科学課題「2030年までに大国の外交政策におけるベトナムの位置づけ」の研究成果です。
(1)ディネシュ・クマール・ジェイン「インドの外交政策」外務省、2014年2月25日、 https://www.mea.gov.in/indian-foreign-policy.htm
(2)インド外務省:「インド大使館長への首相メッセージ」、2015年2月7日、 https://www.mea.gov.in/press-releases.htm ?dtl/24765/Prime+Ministers+message+to+Heads+of+Indian+Missions
(3)スリーシュ・メータ「序文」『海の自由利用:インドの海洋軍事戦略』インド国防省(海軍)統合本部、インド政府、ニューデリー、2007年5月28日、3頁
(4)アチャル・マルホトラ「インドの外交政策:2014-2019:これまでの成果と今後の課題」外務省 インド政府、 2019年7月22日、 https://www.mea.gov.in/distinguished-lectures-detail.htm? 833
(5)インド世界問題評議会:インド外交政策75周年記念、サプルハウス、ニューデリー、2023年、 https://icwa.in/pdfs/INdia75%20Web.pdf
(6)インド外務省:「パンチシール」、https://www.mea.gov.in/uploads/publicationdocs/191_panchsheel.pdf、1ページ
(7) この 2 つの詩の原文はインド国会議事堂のロビーに刻まれており、「全世界は 1 つの大きな家族である」という意味です。 लघुचेतसाम्। (アヤム・ニジャ・パロ・ヴェティ・ガナナ・ラグセタサム) उदारज (ウダラカリタナム トゥ ヴァスダイヴァ クトゥンバカム)
(8) G20は、一般的に次のように知られています。世界の主要先進国および新興国(19カ国と欧州連合を含む)のグループ。最近、アフリカ連合(AU)がG20の最新メンバーとなりました。
(9)C.ラジャ・モハン著『モディの世界 ― インドの勢力圏拡大』ハーパーコリンズ、ニューデリー、2015年
(10)インド世界問題評議会:インド外交政策75周年を祝う、同上。
(11)インドの国際関係における道徳政治は、寛容、博愛、非侵略、そして他国への援助への意欲を重視する戦略的文化と密接に結びついており、世界的な責任を負うことができる友好的なインドというイメージを醸成しています。1947年から現在に至るまで、国際関係におけるインドの政治倫理への重視は、インディラ・ガンディー首相とジャワハルラール・ネルー首相の哲学の追求を通して示されており、道徳的威信の構築と発展途上国への支援を通じて、国際舞台におけるインドの役割を確立してきました。
(12)インド世界問題評議会:インド外交政策75周年記念、同書、41-42ページ
(13)アフガニスタン、バングラデシュ、ブータン、インド、モルディブ、ネパール、パキスタン、スリランカを含む
(14)ドゥルヴァ・ジャイシャンカール「東の実現:多極化したアジアにおけるインド」ISAS Insights、第412号、2017年5月
(15) C. ラジャ・モハン「モディと中東:リンク・ウェスト政策に向けて」インディアン・エクスプレス、2014年10月5日、http://indianexpress.com/article/opinion/columns/modi-and-the-middle-east-towards-a-link-west-policy/
出典: https://tapchicongsan.org.vn/web/guest/the-gioi-van-de-su-kien/-/2018/1115602/chinh-sach-doi-ngoai-cua-an-do--huong-den-mot-cuong-quoc-can-ban.aspx




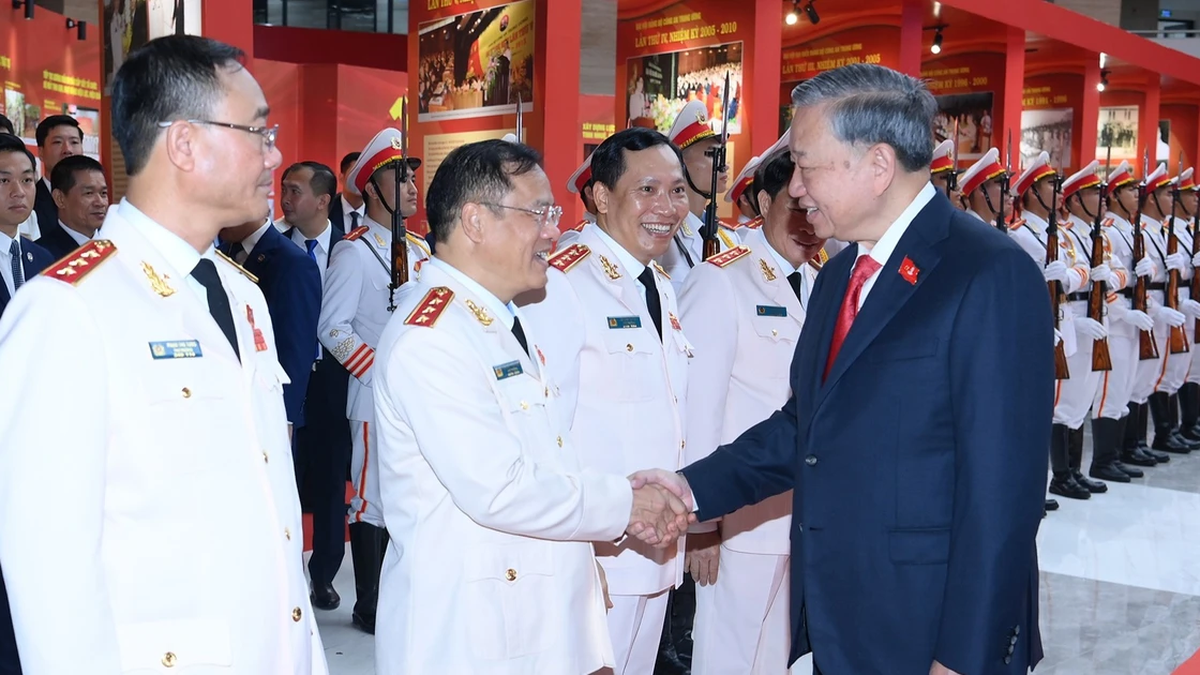

![[写真] 民族学博物館で賑わう中秋節](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/4/da8d5927734d4ca58e3eced14bc435a3)

















![[ビデオ] クアンチ省党委員会第1回大会準備会議の開会](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/4/8de59524ad91416c8d5166ec980bd007)

































![[ビデオ] ペトロベトナム50周年記念式典の概要](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/4/abe133bdb8114793a16d4fe3e5bd0f12)

![[動画] ラム事務総長がペトロベトナムに8つの黄金の言葉を授与:「先駆者 - 優秀 - 持続可能 - グローバル」](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/23/c2fdb48863e846cfa9fb8e6ea9cf44e7)


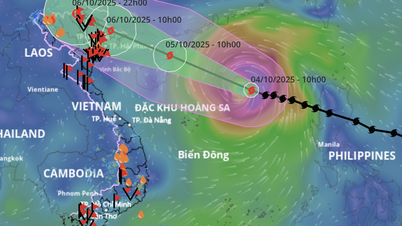

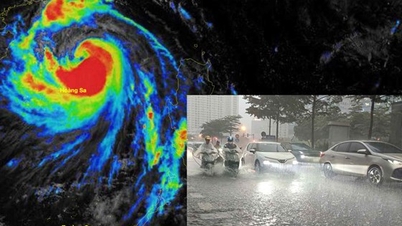


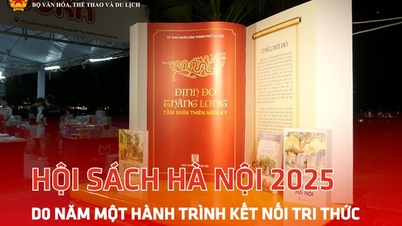







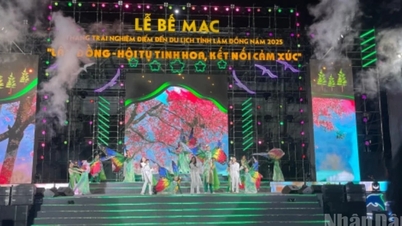


















コメント (0)