 |
| 研究者のトラン・ディン・ソン氏が翡翠と象牙で作られた工芸品を紹介しています。 |
ベトナムや東アジア文化圏の他の国々で精巧に作られたこれらの傑作はすべて、この博物館の所有者であり研究者でもあるトラン・ディン・ソン氏が過去数十年にわたって苦労して収集したものです。
博物館の十分なスペースには、所有者によって翡翠から象牙まで100点を超える工芸品が体系的かつ科学的に展示されており、鑑賞者は工芸品を通して歴史の旅に誘われます。
翡翠と象牙は、古代から現代に至るまで、多くの人々の生活に深く根付いてきました。しかし、これらの素材で作られた工芸品は、必ずしも大量生産されているわけではありません。なぜなら、これらの遺産は主に貴族の生活と結び付けられ、あるいは崇拝の像や魔法の武器といった精神的な儀式に用いられてきたからです。
仏像、ペン立て、三脚、花瓶、盆、印章、数珠など、17世紀初頭から20世紀初頭にかけて日本、中国、ベトナム、タイ、インドで作られたものが多くあります。どれも非常に精巧な浮彫が施されています。それぞれの工芸品には物語や逸話が込められており、製作者や所有者の地位を物語っています。
 |
| 日本産の象牙工芸品 |
骨董品愛好家のトラン・フォン氏( フエ市)は、翡翠や象牙、特に象牙で作られた工芸品を初めて目にした時、「ゾッとした」と語った。長い間、ベトナムの工芸品ばかりを鑑賞し、比較することなどほとんど考えていなかったが、日本、中国、インドの工芸品が並んでいるのを見て、その魅力に気づいたという。「古代の職人技は実に巧みでした。特に日本の工芸品は、洗練されているだけでなく、テーマも多岐にわたります」とフォン氏は語った。
今回、孫氏が展示した数々の工芸品の中でも、特に日本産の象牙仏像は来場者の強い印象を強く受けました。中程度の大きさながら、古代日本の職人たちの技が極めて洗練され、熟練していたことが伺えます。台座には龍の紋様が浮き彫りにされているほか、中央部分には仏像の浮き彫りが施され、さらに二つの扉が開く構造と、それに伴う様々なディテールが随所に施されていることから、この頃の仏像は最盛期を迎えていたと考えられます。
研究者のチャン・ディン・ソン氏は、自身が所有する機会を得た仏像について、「傑作だ」と評しました。一目見れば、日本の象牙工芸職人の技術の高さがはっきりと分かります。ソン氏によると、この仏像はもともと長距離の貿易旅行をする商人のために作られたもので、必要に応じてこの仏像を「招き入れ」、儀式を執り行わせていました。便利でありながら、非常に厳粛な儀式だったそうです。
孫氏は100点を超える展示品を通して、各国の趣味の違いについても比較しました。ベトナムや中国では神仏像ばかりが彫られているのに対し、日本の彫刻は牛飼い、木こり、清掃人など、実に多様であると孫氏は指摘しました。
そのため、今回の展覧会では、作品の歴史的、芸術的、精神的価値や翡翠や象牙彫刻の特色を一般の人々に紹介するとともに、各国の翡翠や象牙の芸術や遊び方を、類似点や相違点とともに比較検討する機会も設けています。
「この展覧会が、来場者が貴重な工芸品や骨董品に触れ、国や国々の文化遺産の多彩な姿を浮き彫りにする一助となることを願っています。そこから、文化遺産の価値を保護し、促進することへの意識が高まるでしょう」と、研究者のチャン・ディン・ソン氏は力強く語った。
出典: https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/ngoc-nga-ke-chuyen-thu-choi-xua-158128.html


![[写真] トラン・タン・マン国会議長が第8回国会議員常勤会議を主宰](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/29/2c21459bc38d44ffaacd679ab9a0477c)
![[写真] ト・ラム事務総長がベトナム駐在米国大使マーク・ナッパー氏を接見](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/29/c8fd0761aa184da7814aee57d87c49b3)

![[写真] ト・ラム書記長が汚職、浪費、ネガティブな行為の防止と撲滅に関する中央指導委員会の会議を主宰](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/29/fb2a8712315d4213a16322588c57b975)

![[写真] ハノイの多くの道路は嵐ブアロイの影響で冠水した](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/29/18b658aa0fa2495c927ade4bbe0096df)














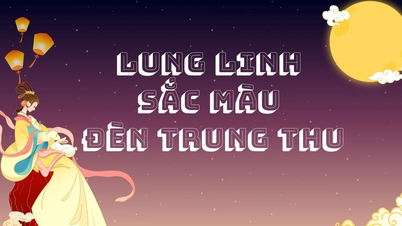

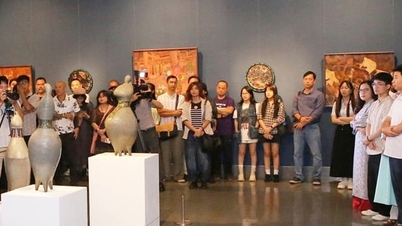









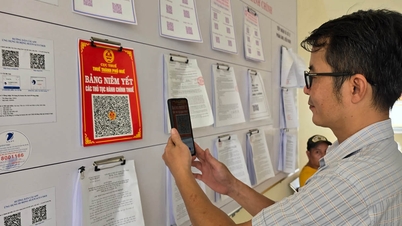










































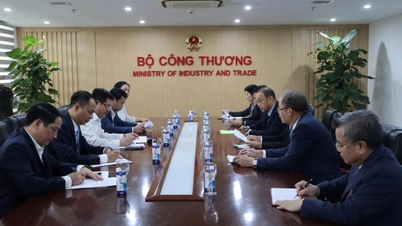



























コメント (0)