| ハノイ:安全な農産物や食品を市内の市場に届ける 首都ハノイの安全な農産物や食品を市内の市場に届ける |
最近では、各地方の農産物や旬の果物がソーシャルネットワーキングプラットフォームを通じて首都や全国の消費者にアピールしており、ライブストリーム販売のたびに数億ドン相当の注文が数百件入っている。
 |
| フォン・トアン果物流通チェーンの代表者がソーシャルネットワーキングプラットフォームでのプロモーション方法について議論している |
12月9日、ハノイで行われたハムイエンオレンジ需給連携会議( トゥエンクアン省)に出席した、果物流通チェーン「フオントアン」のオーナー、グエン・ティ・フオン氏は次のように述べた。 「ライブストリーム販売は、営業場所を必要とせず、中間コストを最小限に抑え、消費者に最も必要な情報を提供できるため、消費者にリーチする最も実用的な方法です。」
現在、ハノイに3店舗を展開するPhuong Toan果物流通チェーンでは、TikTokやFacebookプラットフォームでライブ配信セッションを毎回行い、消費者に最良の価格と製品品質で数百件の注文を受けています。
同時に、フンイエン省とハイズオン省のオレンジとライチの畑にライブ配信スペースを設け、消費者と生産地を近く親しみやすい雰囲気を醸し出し、各省の旬な商品情報を消費者に届けることに貢献しています。
明らかに、デジタル技術の活用を積極的に進め、多くの企業や協同組合がTikTokプラットフォームやFacebook、Zaloなどのソーシャルネットワークを通じて自社製品を宣伝しています。そのおかげで、売上が伸びただけでなく、協同組合や地域の農産物ブランドも多くの消費者に知られるようになりました。
各省市は、オンラインでのプロモーションの推進に加えて、ハノイ市場で伝統的な貿易プロモーション活動を積極的に実施している。例えば、ハノイでのトゥエンクアンオレンジプロモーション会議、ハノイでのイエンバイ省の農水産物紹介週間、フンイエンオレンジ週間、ライチャウ省の農産物展示紹介週間などがあり、首都の消費者に地方の農産物、特産品、一貫生産品などを紹介しています。
トゥエンクアン省におけるハムイエンオレンジの消費促進はその一例です。2023年には、同県全体のオレンジ栽培面積は5,100ヘクタールに達し、収穫量は7万5,000トンに達する見込みです。すでに全国的に広く消費されており、Winmart、Co.opmartといった大手スーパーマーケットチェーンでも販売されています。しかしながら、ハムイエン県におけるオレンジの栽培は現状、特に生オレンジの消費において依然として限定的です。
オレンジのシーズンは前年の11月から翌年の1月末まで続きます。生産量が多いと販売が難しく、販売価格も低迷し、オレンジの消費量は依然として業者に依存しており、生産地の住民の収入や事業収益に影響を与えています。
イエンラムグリーン農業協同組合のグエン・ティ・ティン理事長は、同協同組合はVietGAP基準に従って50ヘクタール以上のオレンジを栽培しており、今後は有機栽培に移行する予定だと述べた。オレンジの栽培面積は比較的広いものの、現在、協同組合にとって最大の課題は、生産量を保証するために企業との連携ができておらず、依然として業者に依存していることだ。
そのため、協同組合は、豊作なのに価格が低いという状況を避けるために、各レベルの当局と貿易促進団体がハノイ市場全般、特に国全体での消費のつながりを支援することを期待しています。
ベトナムの農産物や果物には、収穫期になると生産量が不安定になり、販売価格も低くなるという、ハムイエンオレンジのような問題が数多くあります。この問題の解決に向けて、ハノイ市は近年、地方自治体の努力に加え、省・市の農家との連携強化と生産支援に多大な支援を提供しています。
 |
| ハノイにおけるハムイエンオレンジの消費促進に関する会議での覚書の調印 |
したがって、2023年だけでも、ハノイ商工局は30以上の省や市と連携し、ハノイ市場とその他の地域にサービスを提供する商品の需要と供給のつながりを強化するための実践的な活動をさまざまな形で実施してきました。たとえば、クアンチ、バクカン、タイニン、ハイズオンなどの企業がハノイの流通システムと直接連携して、特産品や代表的な製品を紹介し、結び付けることなどです。
省内企業を組織・支援し、ハノイおよび他省で40以上の貿易連携活動、フェア、商品週間に参加し、30省市からの3,000種類の製品リストをハノイの流通システムに紹介・提供し、流通システムが積極的に連携できるようにします。
これまで、ハノイのスーパーマーケットやクリーン食品店チェーンでは、多くの農産物や省市町村のOCOP製品が「並び」、消費者から優先的に購入されてきた。
ハノイ市商工局は、ハノイ市の支援を受け、省や市の旬の産物や農産物を宣伝・連携させるために、地方自治体が直接販売やオンライン販売の形態を多様化し、デジタル変革を進め、デジタルプラットフォーム上で農産物ブランドを宣伝し、それによって特にハノイ、そして一般的には全国でその地方の農産物や特産品を広めていくことを推奨している。
[広告2]
ソースリンク










![[写真] ト・ラム書記長がハノイ市で有権者と面会](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/23/d3d496df306d42528b1efa01c19b9c1f)















































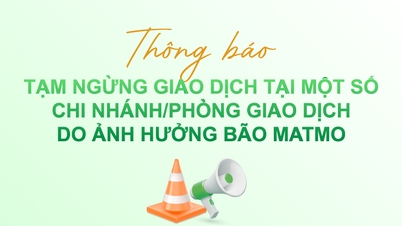
















































コメント (0)