
ある朝、ベンコンに、やつれた風貌の中年男性がスゲ袋を手に、島の村へ帰るための船を探していた。彼は水辺で竹籠で魚を洗っている女性に話しかけた。女性は少し驚いて、海門の方を指差した。
漁船は島の村まで人を乗せることができなくなりました。上の桟橋まで行かなければなりません…
男は一瞬ためらった後、静かに踵を返した。どうやら初めてこの場所に来た見知らぬ人のようだった。
いいえ!彼は見知らぬ人ではなく、何年も離れていた後に戻ってきた人です。
二隻の巨大な黒鉄の船が海を警備していた。埠頭では人々が船に荷物を積み込むのに忙しそうだった。船を探している乗客が出発案内板の前で立ち止まり、つぶやいた。「ツナ島行きの船は本日午後2時に出港します」
乗客は列車を待つ間、休憩できるカフェを見つけた。中央高地の森の片隅からこの海の片隅まで、古くてボロボロのバスに二日近く乗り込み、数百キロを旅してきたのに、長らく離れていた場所に戻るにはまだ数十海里を漂流しなければならなかった。何年も離れていた間、島の村も愛する人々も、彼の記憶から跡形もなく消え去ることがよくあった。時には突然消え、かすかに現れたり、ほんの一瞬だけ現れては霧の中に消えたりした。彼は思い出したり、忘れたりした。どこかからこだまするぼんやりとした呼び声に耳を澄ませるかのように、ぼんやりと遠くを見つめていることがよくあった。周りの人たちとは普通にコミュニケーションをとっていたにもかかわらず、彼は周囲で何が起こっているのかに注意を払っていなかった。
彼は中央高地の森の片隅に住む村人ではなかった。自分が誰なのかも、なぜ見知らぬ場所にいるのかも分からず、親戚もいないまま、突然現れた。この山間の村で誰も彼について何も知らないのと同じだ。
村人たちは彼を放浪する記憶喪失者として愛していたが、中には狂った老人、サイコパス、あるいは子供に「狂った老人」と呼ばせる者もいた。人々が何を言おうと、彼は気に留めず、ただ馬鹿みたいに笑っていた。人々は彼を哀れみ、食べ物やお菓子を与えた。時が経つにつれ、彼が温厚で無害な人柄であることを知ると、村の不幸な息子とみなされるようになった。ある老夫婦は、畑の小屋に彼を住まわせ、作物を荒らす鳥やリス、ネズミを追い払う手伝いをさせた。その見返りに、彼は衣食住の心配をしなくて済むようになった。
彼は農作業に精を出していた。数シーズンを経て、トウモロコシ、カボチャ、豆、ジャガイモが彼の質素な生活を支えるのに十分な収入をもたらしてくれた。村の市場で作物を売るのが好きだった。多くの人々と出会い、何気ない言葉でも交わし、断片的なイメージや記憶を頭の中で思い出すことも好きだった。彼は静かに、一人で暮らし、この森の片隅に来る前の日々を再び思い出そうとしていた。
ある日…
晴れ渡っていた天気が突然暗くなり、厚い黒雲が流れ込み、空を覆い尽くした。すると、風が四方八方から吹き寄せ、森や野原を擦り、高床式の家を揺らした…雨は激しい水柱を叩きつけ、あらゆるものに降り注いだ…そして、猛烈な流れが堤防を越え、岩や土、木々を流し去った…
この時、彼は恩人夫婦の老いた牛を小川から小屋まで連れて行っていたが、時すでに遅し、沸騰する小川が人々や動物を渦に巻き込んでしまった。
天地の怒りが収まった後、村人たちは彼が根こそぎにされた古木の傍らで老牛を抱きしめているのを発見した。村外れの小川を渡った古木の幹が二人の体を動かさず、奈落の底へと流されずに済んだのだ。しかし、意識を失っていたにもかかわらず、彼はまだかすかに呼吸を続けていた……
村人たちは心をこめて彼を世話し、丁重に扱った。ある夜、畑の小屋で、薄い毛布をかけた筵の上で、彼は耳元でブンブンという音が何度も繰り返されるのを聞いた。夜行性の鳥の羽ばたきの音も聞こえなくなった静かな夜、なぜその音が耳に響き続けるのかわからず、彼は数晩続けて静かに耳を澄ませていた。そしてある朝、まだ眠い頃、彼はふと、砂州に舳先を押し付けている小さな船の茶色い帆が見えた。周囲には、まるで待ち構えているかのように、大勢の人影がいた。耳元でブンブンという音が急にはっきりと聞こえ、それが穏やかな波の音だと気づいた。
臨死体験の後、彼の記憶はゆっくりとではあったが徐々に回復し、再生しても鮮明でない古いフィルムのようにぼやけた記憶もあったが、故郷と自分のアイデンティティは覚えていた。しかし、ぼんやりとした記憶の中に前世のフィルムが完全に再現されたのは、半年も経ってからだった。
サメ漁の最中、彼と数人の乗組員は捕らえられ、海軍艦艇の船倉に閉じ込められ、本土へ連行されました。その後、彼らは記録を取り、全員を士官学校へ送りました。数ヶ月の訓練の後、彼は戦争末期の中央高地の激戦地へと送られました。そして、軍隊生活初の戦闘で、新兵は砲弾の圧力に押しつぶされそうになりました。負傷はしなかったものの、一時的な記憶喪失に陥りました。ある日、彼は治療施設を離れ、彷徨い歩き、森の片隅で道に迷いました。そこで心優しい人々に保護されました。
徐々に記憶が回復していくにつれ、彼は自分に家族がいることを実感しました。ある日、彼は老夫婦と村人たちに、海の真ん中にある漁村の故郷で愛する家族のもとへ帰る許可を願い出ました。世話をしてくれた人々は、温かい送別会の食事を用意してくれました。省間バスターミナルへ向かう荷馬車に乗る前に、長年彼の状態を見守ってきた村で唯一の看護師が、彼を慰めました。
彼は重度の脳震盪を起こし、一時的に記憶を失いましたが、脳自体には損傷がなかったため、しばらくすると徐々に記憶が戻ってきました。これは以前にも起こったことなので、珍しいことではありません。ご心配なく…完全に回復したら、ご親戚のところへぜひお越しください!
*
遠くから見ると、Oは水辺に大勢の人が集まり、腕を振り回して指さしているのが見えた。ムックは飛び跳ねながら何か叫んでいたが、Oにはよく聞こえなかった。漁船が砂州に着く前に、ムックは船に飛び乗り、友人の耳元で大声で叫んだ。
お父さんが家に帰ってきた!お父さんが家に帰ってきた!
船に乗っていた全員が戻ってきて、何年もの亡命生活を経て父の息子が戻ってきたことを喜びながらおしゃべりをしました。
Oは、長年行方不明だった父親が、故郷の島の村に突然現れたことに衝撃を受けた。混乱し、どうしたらいいのか分からなかった。いつものように船倉を開け、仲間の船頭が昨夜釣った新鮮なイカを籠にいくつか入れて陸に上げ、ムックに促されるも聞かず、いつものようにひしゃくで海水をすくい、船室をこすり洗いした。
家に帰りなさい!お父さんに会いに行って、午後はボートを洗ってきて…
ムックは友達の手を引いて走った。ビーチからOの家までの曲がりくねった砂道は、いくつもの急な坂を越えなければならなかったが、ムックは友達の手を引いて風のように走った。まもなく、家の門となる二本のユーカリの木が見えてきた。二人はそれぞれユーカリの木に抱きつきながら立ち止まり…息を整えた。誰かが前庭にテーブルとたくさんの椅子を置いて、来客が座って話せるようにしていた。
ムックは友人の背中を押した。門から馴染みの家まではほんの数十歩だが、オーはまるで見知らぬ道を歩いているかのようにためらった。玄関先に座り込み、ポーチを指差す大勢の人たちの姿が、彼をさらに混乱させた。
オールドカットは彼を手招きして何度も呼びかけた。
ああ!入っておいで、息子さん!お父さんですよ!
Oさんが階段に上がると、中年の男が家から飛び出してきて、Oさんの肩を抱きしめ、揺さぶった。
私の息子よ!私の息子よ!
すると彼は突然泣き出した。
O は立ち止まっていた。まだ父親の顔をはっきりと見ていなかった。彼は胸元に立ち、痩せた胸に顔を押し当てると、何年も離れていた息子を見つけた父親の心臓の鼓動がはっきりと聞こえた。彼は息子を見上げ、想像していた顔に似ているかどうか確かめた。父親は骨ばった顔、頬は落ちくぼみ、鼻は高く、眉は太い。顔は丸く、頬は肉厚で、眉は薄く、額の前の髪は巻き毛だった。父親には全く似ていない?ああ!もしかしたら、鼻が高く、鼻先が少し尖っているところが似ているのかもしれない。
祖母がまだ生きているのに、なぜ父は帰ってこなかったのだろう。Oは祖母に、自分を育て、教育してくれる父親がまだいると安心させるために、自問自答し続けた。「祖母がいなくなったら、僕は誰と暮らせばいいんだろう?」小さく低く暗い二人暮らしの家の中、そよ風のような祖母の吐息が彼の耳に心地よく響いた。彼は父に、なぜもっと早く帰ってこなかったのか、祖母と母にも尋ねようと思った。孤児である自分のことを心配し、祖母が亡くなるまでずっと心配し、不安だったことを知っていたため、Oは激しく泣いた。
多くの人がOの父子を訪ねてきて、祖母の仏壇にお線香を焚いていたため、家は暖かくなっていた。隣人のトゥおばさんは、皆のために心遣いでお茶を淹れてくれた。Oはポーチに静かに座り、父親が皆と話す様子をじっと見つめていた。父親の穏やかな様子、話すよりも笑顔が多い様子に、Oは気づいた。数時間前までは見知らぬ人だった父親への温かい気持ちが、Oの心を満たした。
皆が一人ずつ帰っていき、最後にオールドカットが去っていった。彼は愛情を込めてOの父親の肩に腕を回し、毎朝コーヒーか紅茶を飲みながらおしゃべりをしよう、と何度も誘った。Oは父親がオールドカットをとても気に入っている様子に気づき、自分が生まれる前の母親と、オールドカットが母親に抱いていた感情を思い出した。彼は父親に、二人の間に起こったあの繊細な物語について尋ねてみようと思った。
杜叔母はOと父のために初めて皆で食事を作った。父は新鮮な魚の酸辣湯煮と蒸しイカを楽しんだ。長年山に住んでいた父にとって、海を懐かしんで体を丸めている新鮮な魚や、まだ光り輝く新鮮なイカは食べたことがなかった。父は、かつて自分を世話してくれたやつれた顔の老夫婦のことを思い出した。彼らはタケノコや山菜をふんだんに使った食事を共にし、いつか島の村に招待して海の幸をご馳走しようと密かに約束していた。Oは父を見つめ、ご飯を椀に盛って父に差し出す幸せな時間を少しでも長く残したかったので、少しずつ食べた。食卓に着くことは滅多になく、大きなご飯にすべての食材を混ぜ込み、一気に飲み込んで食べ終えるか、風と波に揺れる船の上でゆっくりと食事を咀嚼していた。杜叔母は嬉しそうに二人の隣人を見ながら、ささやいた。
明日の朝、祖父母の再会を祝って二人分の食事を用意します。
出典: https://baolamdong.vn/truyen-ngan-sum-hop-386205.html


![[写真] フート省党委員会第1回大会(任期2025~2030年)](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/30/1507da06216649bba8a1ce6251816820)
![[写真] 2025~2030年任期の第12回軍事党大会が厳粛に開幕](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/30/2cd383b3130d41a1a4b5ace0d5eb989d)






































































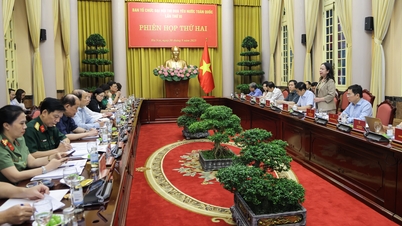



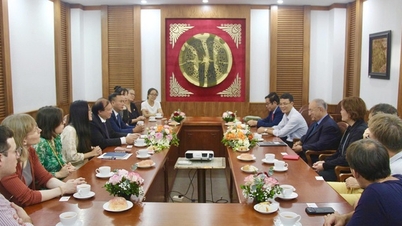


























コメント (0)