電話を手に取ると、私は飛び上がった。明るい画面には18件、不在着信が18件も表示されていた。心臓がドキッとした。嫌な予感がした。すべて同じ番号からだった。妻の番号だ。すぐにリダイヤルを押した。一度鳴った後、相手が出た。
 |
イラスト写真。 |
妻の声が、詰まったように、途切れ途切れに、まるで私の耳元で叫んでいるかのように、ただ一言だけ発せられた。
- 出産する!
恐怖で凍りつきました。どうしてこんなに早くそうなるのでしょう?昨日、妻を病院に連れて行ったら、胎児はまだ36週、出産予定日まであと4週間近くあると言われました。私立病院で最新の設備も整い、先生も一流の専門家なのに、まだ何かが間違っているのでしょうか?それとも…我が子は出産予定日や出産予定月を待つのではなく、自らの意思でこの世に生まれてきたのでしょうか?
着替える暇もなく、サッカーのユニフォームに着替え、風のように車を走らせ、病院へと向かった。暑い一日の後だったので、空は暗かった。街灯が午後の雨でできた水たまりを黄色い光で照らしていた。心臓はサッカー場の太鼓のように激しく鼓動していた。ただし今回はゴールのためではなく、出産のためだった。コーチも観客もいない試合、父親としての人生で初めてにして最大の試合だった。病院に着くと、分娩室に駆け込んだ。妻は顔面蒼白で、目は涙で腫れ上がって横たわっていた。
- 今この時間に到着したばかりですが、何のサッカーをしていますか?
妻は悲しみと痛みが入り混じった声で詰まった。隣で3回出産した妹が、すぐに妻を安心させるように声をかけた。
「まだ遅くはないよ。すぐに出産するわけじゃないんだから。落ち着いて、心配しないで。」
妻は顔をしかめ、痛みが激しくなるにつれて時折ベッドのシーツを握りしめました。夕食を作っている最中にお腹が痛み始めたと彼女は話しました。パニックに陥った彼女は、私に何度も何度も電話をかけましたが、誰も出ませんでした。他に選択肢がなく、妻は同じアパートに住む友人に電話し、さらに建物の医療スタッフに救急外来に連れて行ってもらうよう頼まなければなりませんでした。
妻の手を優しく握りしめた。胸に、針で刺されたような鋭い痛みがこみ上げてきた。罪悪感。サッカーの試合のせいで。ほんの数時間の個人的な活動のせいで、人生で最も神聖な瞬間、我が子が生まれる瞬間を逃すところだった。一時間以上にわたる継続的なモニタリングの後、医師は診察と指標の測定を行い、モニターを見て軽く首を横に振り、こう言った。
- 帝王切開が必要です。羊水が少なくなってきているんです。
一見短いその一言で、部屋の空気が一気に重苦しくなった。妻は震え上がった。医師は帝王切開の可能性を告げていたにもかかわらず、いざ手術となると妻は不安を隠せなかった。私は落ち着こうと努め、すぐに母に電話した。母はかつて外科看護師で、数年前に退職したが、今でも名医の名前を片っ端から覚えていた。母のコネのおかげで、ほんの数分で産科の名医を選ぶことができた。手術室の準備は整っていた。妻はストレッチャーに横たわり、顔は青ざめていたが、それでも私を見ようとしていた。私は手術室のドアまで妻の後を追い、しっかりと手を握り、ささやいた。
- 着きました。お医者さんは元気です。大丈夫です。
手術室のドアがゆっくりと閉まり、私は外に閉じ込められた。頭の中では様々な考えが渦巻いていた。妻と私は待合椅子に静かに座っていた。夜空は次第に薄い雲に覆われ、雨が静かに、そしてしつこく降り始めた。今シーズン最初の雨粒が病院の屋根を叩き、その音はまるでこれから起こる神聖な出来事の前奏曲のように、私の心に響き渡った。言葉では言い表せない感情が湧き上がった。不安と希望、そして胸が締め付けられるような感情が同時に湧き上がった。私は何度も何度も自分に言い聞かせた。「雨が降ってよかった。空が私を祝福してくれている。大丈夫。大丈夫。」
4階全体が静まり返っていた。黄色い光が白いタイルに散らばり、廊下に私の影を落としていた。時計の針はまだ動いていたが、一分一秒がサッカー場での過酷な試合よりも長く感じられた。私は立ち上がり、座り、そしてまた立ち上がった。廊下の突き当たりにあるドアから視線を離さなかった。そこは、人生の岐路に立つ二つの命と私を隔てる場所だった。
その時、ドアが開き、生まれたばかりの赤ちゃんを腕に抱いた看護師が出てきました。彼女は歩きながら、大声で叫びました。
- 赤ちゃんの父親はどこですか?
私は飛び上がり、一瞬心臓が止まった。看護師の腕の中でかすかに動く小さな生き物を捕まえようと、駆け寄った。小さなバラ色の体、目はまだ閉じられ、可愛らしい口は泣きたいように突き出ていた。小さな手足は、生まれて初めて支えを求めるかのように、弱々しく宙を蹴っていた。私は赤ちゃんを胸に抱きしめた。いつの間にか涙があふれ、温かい流れとなって頬を伝って流れ落ちた。その瞬間、私は悟った。私は本当に父親になったのだ。
産後ケアルームに通された。赤ちゃんを優しく保温ランプの中に置いた。紙のように薄い皮膚、淡い黄色の光が、生まれて初めて感じる温もりで赤ちゃんの体を包んでいた。用意されていた母乳を一口ずつ丁寧に与え、腸内環境をきれいにした。赤ちゃんは口を開け、哺乳瓶をしっかりと握りしめ、熱心に吸い付いた。私は赤ちゃんのそばに座り、目を離さなかった。小さな顔のあらゆる特徴が、ずっと昔から私の心に刻まれているようだった。まるで父親にそっくりだ、と私は思った。この鼻、この耳、そしてかすかに開いた眠そうな目さえも、まるであの頃の私の小さなコピーのようだった。私はかがみ込み、指先一つ一つ、つま先一つ一つ、小さな関節一つ一つを静かに確認した。静かな不安が忍び寄ってきた。おそらくどんな父親や母親も経験したことがある、目に見えない不安。赤ちゃんが健康ではないのではないか、何かがおかしいのではないかという不安。しかし、私は安堵のため息をついた。すべては大丈夫だった。赤ちゃんは完全に健康だった。まるで人生が奇跡を与えてくれたかのように、軽くて神聖な感謝の気持ちが私の中に湧き上がりました。
術後数時間の経過観察の後、妻は車椅子で病室に戻されました。顔色は依然として青白かったものの、目は以前ほどのパニック状態ではなく、穏やかになっていました。振り返ると、保育器の中で安らかに横たわる赤ちゃんの姿が見え、その目に涙が溢れました。
「赤ちゃんはどう?」妻は疲れて嗄れた声でささやいた。
「大丈夫よ。お父さんみたいにハンサムだし」胸に秘めた感情を隠しながら、冗談を言おうとした。
妻は子供を見つめ、かすかに微笑んだ。死の苦しみを味わった母親が初めて見せる微笑み。疲れ果て、弱々しく、それでいて不思議なほど輝いていた。私は妻の傍らに立ち、静かに母子を見守った。小さな部屋、温かみのある黄色い光、エアコンの音。すべてが一つの世界に縮こまっているようだった。私たちの世界。家族。愛。そして、始まったばかりの人生。しかし、その幸福感の中にも、まだ静寂が漂っていた。息子の祖父である父は、もうこの世にはいなかった。2ヶ月近く前、長い闘病生活の末、長男の孫を抱く機会もなく亡くなった。そのことを思うだけで、胸が締め付けられる思いがした。私はそっと囁いた。「お父さん、お孫さんが生まれました。白くて、元気で、お父さんそっくりです。あの空に見えますか?」
最初の頃は、妻も私も子供の世話という悪循環に陥っていました。子供は奇妙なほど「扱いにくい」子で、床に下ろすと泣き出し、抱き上げるとやっと泣き止みます。まるで、両親を一晩中忙しくさせることで愛情を測っているかのようでした。疲れ果てていましたが、子供を抱きしめるたびに、母子ともに無事で、どこかで父も微笑んでいるに違いないと、心の中で感謝していました。立ったまま眠ることも、ごく短時間の短い昼寝もできるようになりました。でも不思議なことに、疲れ果てていても、怒ったり癇癪を起こしたりすることはありませんでした。それどころか、いつも不思議な安らぎを感じていました。まるで父が静かに私に成長の仕方、真の男になる方法を教えてくれているようでした。
そのワールドカップシーズン、私はアルゼンチンがサウジアラビアに衝撃的な敗北を喫した初戦から、メッシが初めて栄誉ある金メダルを掲げたスリリングな決勝戦まで、すべての試合を観戦しました。誰のおかげで、私はすべての瞬間を観戦することができたのでしょうか?それは、一晩中私を寝かしつけてくれなかった息子のおかげです。息子を抱きしめ、一挙手一投足を目で追っていました。「息子も私と同じくらいサッカーを好きになるだろうか?」と。もしかしたら、将来サッカー選手になるか、献身的な医者になるか。あるいは、祖父が教えてくれたように、家族を愛し、思いやりのある優しい人になるかもしれません。
それが私の「サプライズゴール」でした。でも、人生という長いゲームに勝つためには、全身全霊で、忍耐と愛と犠牲を払って戦わなければならないと理解していました。そして、私は準備万端でした。
出典: https://baobacgiang.vn/ban-thang-dau-doi-postid419561.bbg





















































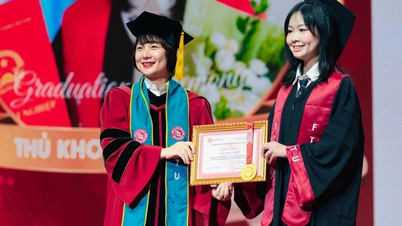















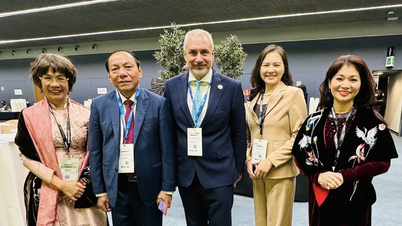










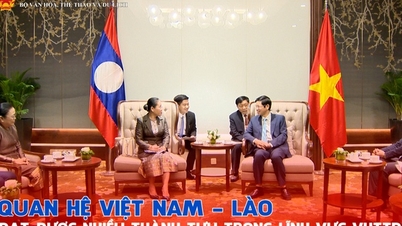
























コメント (0)