三重大学の研究チームは10月11日、気候変動の影響で1982年から2023年の間に日本の夏が約3週間延びたと発表した。
研究チームによると、夏と分類される日の数は年々着実に増加している一方で、春と秋の平均日数は短くなり、冬の長さはほとんど変わっていない。
三重大学環境理工学部の立花義弘教授と大学院生の滝川真生氏は、地球温暖化による海面水温の上昇が主な原因だと考えている。
同団体は、このまま放置すれば、夏が長くなり冬が遅くなる傾向が続く可能性があると警告している。
研究チームは、日本最北端の北海道から最南端の九州までの地域(周辺海域を含む)を約200のゾーンに分け、気象庁の観測データを用いてその期間の年平均最高気温を算出した。
その後、研究チームは、各地域の毎年の最高気温と最低気温のデータに基づいて、各地域の「夏の閾値」を決定しました。
ある地域の最高気温が20℃、最低気温が0℃の場合、「夏の閾値」は15℃(最高気温の4分の1)と計算されます。この閾値を超える気温の日が夏日としてカウントされます。
その結果、全国平均では夏の始まりが約12.6日早くなり、終わりが約8.8日遅くなっており、過去40年間で夏が約21.4日長くなっていることが分かりました。
具体的には、1982年の夏は92日間(6月29日から9月28日まで)続きました。2023年には、この数は121日間(6月11日から10月9日まで)に増加しました。
立花教授は、アジア大陸からの暖かい空気が日本近海を通過する際に冷やされ、春から夏への移り変わりを調節するのに役立つと説明した。
しかし、海面温度が上昇すると、冷却効果が薄れ、夏の到来が早まり、終わりが遅くなります。
一方、日本は依然として大陸からの強い寒波の影響を受けているため、冬の気温はあまり変動しません。
出典: https://www.vietnamplus.vn/bien-doi-khi-hau-keo-dai-mua-he-tai-nhat-ban-them-khoang-ba-tuan-post1069866.vnp







![[写真] 第1回世界文化祭でユニークな体験を発見](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/11/1760198064937_le-hoi-van-hoa-4199-3623-jpg.webp)















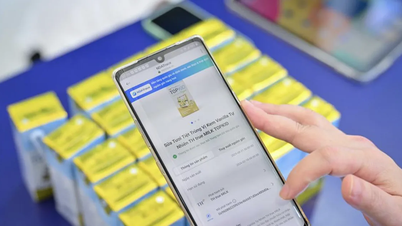








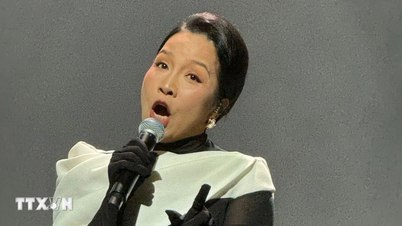






































































コメント (0)