旧態依然としたやり方への回帰を望む第一の理由は、教科書を「標準」とすることです。これは非常に古い教育観を反映しているのではないかと危惧しています。教育法の規定や党と国が国際的な教育動向に沿って言及した文書によれば、カリキュラムと教科書の革新によって、カリキュラムと教科書の関係は根本的に変化しました。カリキュラムだけが法的文書であり、全国で統一的に実施されます。一方、教科書はカリキュラムを規定する文書に過ぎず、教師はこれを参考に、統合し、生徒の学習活動を指導してカリキュラムの「標準」を達成するためのものです。

多くの国では、教科書は単なる参考資料であり、教師は生徒に最適な教材を独自に作成できます。「一つのカリキュラム、多くの教科書」という仕組みにより、学習アプローチと問題解決は常にオープンな状態にあり、学習者は模範授業に頼ることなく、暗記や見本テキストの学習に頼ることなく、真に自らの能力を伸ばすことができます。したがって、国が編纂機関に割り当てた全国共通の教科書セットに戻れば、教科書選択権はもはや存在しなくなります。そうなれば、教科書は法となり、不変のものとなり、カリキュラムを規制する機能と知識を伝達する機能という二つの機能を持つことになります。数十年にわたって続いた暗記、暗記、見本テキストの書き写しの状態に必ず戻るでしょう。そして、2018年カリキュラムの施行によって、この状況はようやく終わりを迎えたのです。
教科書が多すぎると、親が子どもにどのタイプの本を選べばよいか迷ってしまうため、全国で統一した教科書を1セットだけ用意して、簡単に選べるようにすべきだと主張する人もいます。しかし、この考え方や議論は、教科書を購入して使用する必要のある人から、賢い消費者になる権利を奪うことになります。しかし、教科書の選択は、親が学校と話し合い、一緒に決めます。生徒は必ずしも教科書セット全体を購入する必要はなく、教科ごとに異なる教科書セットから教科書を選び、残りの教科は教育訓練大臣が承認した教科書セットから選びます。このアプローチにより、親と学校が好きなものを選ぶ権利が常に尊重されます。教育訓練省が今日発行することを決定した教科書は、アプローチに関係なく、生徒が習得する必要のある知識が一般教育プログラムの規制に従わなければならないことに注意してください。
新旧のやり方への回帰を奨励する3つ目の理由は、費用を節約し、無駄をなくすという点で、非常に魅力的に聞こえます。しかし、現実にはそうではありません。社会化政策の下、教科書は主に出版社と提携した企業によって民間資本を用いて製造されているからです。 教育訓練省傘下の国営企業で、国費で書籍を製造しているのは1社だけです。さて、「専用教科書セット」の話に戻りますが、教育訓練省は省内の企業にそれを委託すべきではないでしょうか?もしそうなら、国家予算は節約できるでしょうか?国家予算で教科書を製造し続けたいと考えている人々は、第14期国会決議第122/2020号に「社会化方式による教科書の編纂において、各教科において教育法第43/2019/QH14号の規定に従って評価・承認された教科書が少なくとも1冊完成している場合、当該教科については国家予算による教科書の編纂は実施されない」という規定があることを忘れているようです。
2030年からすべての高校生に教科書を無償で提供するという大胆な提案もあることが知られています。国が豊かなら教科書を購入したり、企業が国費で教科書を製造したりして、計算なしに無償で子どもたちに教科書を配布するなら、これ以上の価値はありません!しかし、現在の経済状況で、国が毎年2000万人以上の高校生の教科書を補助できるでしょうか?どうしてそんなアイデアが思いつくのでしょうか?
過去5年間、国会決議88/2014に基づき、企業は数千億ドンを費やし、数千冊の教科書を編集・出版してきました。教師や学生もそれらの教科書を購入し、使用してきました。しかし、今後は「統一教科書セット」しか使用できないため、これまで出版・購入された数千万冊の教科書が廃棄されなければなりません。これは甚だしい無駄です。数千冊の社会化教科書を「参考書」に転用すべきだという意見もありますが、これは教育出版の本質を捉えたものではありません。教科書を参考書に転用することは、学生に参考書の購入を強制することにつながるのでしょうか?また、数百部しか印刷できず、多額の損失しか出ないと知りながら、あえて数百部しか印刷しない本を出版した出版社がかつてあったでしょうか?
全国統一の教科書に戻れば保護者の負担は軽減されるという意見があります。しかし、これは単なるポピュリストの誤謬です。教科書がいくつあっても、保護者は少なくとも学校と合意した教科書を1セット購入するだけで済むからです。
昔のやり方に戻りたい4つ目の理由は、聞こえは良いのですが、集団の利益に反するからです。これは実際には市場メカニズムを意図的に無視した意見です。独占だけが特定の企業の利益に資することは誰もが知っています。しかし、独占メカニズムが排除され、平等が社会化され、教師や一般の人々が自分に合った本を選べるようになると、集団の利益は排除されるでしょう。
つまり、全国で教科書が1セットしかない状態に戻ることは、ベトナムの教育を独占と後進性の時代に逆戻りさせ、教科書編纂分野における競争法則を消滅させることを意味し、消費者には何の利益ももたらさないと言えるでしょう。社会化政策に熱心に反応してきた投資家は、大きな損失を被るだけでなく、政策や法律への信頼も失うことになります。もし利益があるとすれば、少数の教育管理者が、異なる教科書を使用する教育機関を管理するために、多くの教科書を読む必要がなくなることでしょう。
出典: https://baoquangninh.vn/chuyen-sach-giao-khoa-loi-va-hai-3372207.html































![[写真] ホーチミン市初の国際金融センタービルのクローズアップ](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/19/3f06082e1b534742a13b7029b76c69b6)






















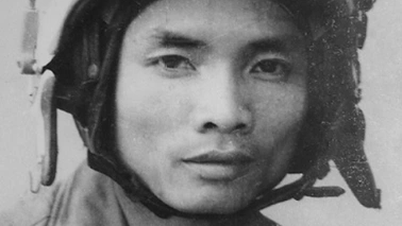





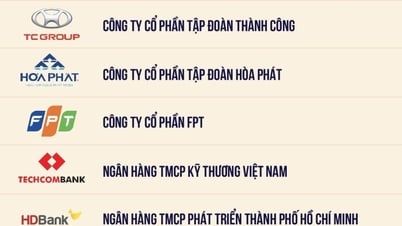



















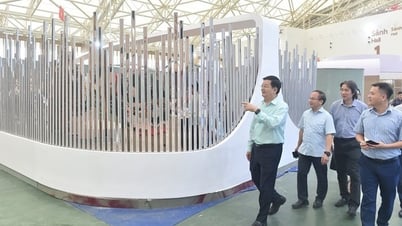























コメント (0)