9月5日午後、 経済都市新聞がハノイ保健局および教育訓練局と共同で主催した「学校給食の食品安全と品質の確保」をテーマにしたオンライン討論会には、多くの代表者や専門家の注目を集めました。
ここでは、現状の徹底的な分析に焦点を当て、学校給食の質を向上させ、国の未来を担う生徒たちの健康を守るための解決策を提案するなど、多くの心からの意見が共有されました。
 |
| セミナーに出席した代表者たち。 |
ハノイは現在、ベトナム国内最大の教育規模を誇る地域であり、約230万人の生徒と約3,000校の学校があらゆるレベルで存在しています。ハノイ市の教育訓練部門に関する最新の報告書によると、ハノイには126の市町村と区に1,160の幼稚園があり、そのうち813校が公立、347校が私立です。
さらに、市内には外資系学校が25校(うち幼稚園18校、幼稚園児を擁する中等教育学校7校)あり、独立系教育機関は2,702校あります。現在、就学前児童の総数は約49万5,400人で、給食の実施率は100%です。
市内の小学校は778校あり、そのうち704校が寄宿制を採用しており、寄宿率は約90.4%に達している。
76万3000人を超える小学生のうち、50万2000人以上が現在学校給食に参加しており、これは約65.8%に相当します。さらに、1日2コマ制の中学校でも多くの学校給食が実施されています。 ハノイでは、毎日100万人以上の生徒が学校で給食を食べていると推定されています。
ハノイ市教育訓練局の統計によると、現在、自主給食を実施している学校は1,455校、食品供給業者と提携している学校は647校、外部業者に給食を発注している学校は283校ある。市内では現在、2,385の共同調理場と学校食堂が運営されている。
セミナーでは、代表者たちが今日の学校における食品の安全性確保に関する重要な問題について率直に共有し、分析しました。
多くの意見では、給食供給業者の選択、投入材料の品質管理、加工・配送・監督のプロセスにはまだ欠陥があり、学校、州の管理機関、食品供給業者、そして特に保護者の間での緊密な連携が必要だと指摘されています。
多くの代表者が言及した注目すべき問題は、学生が頻繁に訪れる学校の門の周りのレストラン、屋台、屋台での食料不安の状態である。
これらの販売場所は、食品衛生、原産地の不明確さ、そして管理されていない添加物の使用など、多くのリスクを伴います。実際、学生たちはこれらの場所で販売される食品に簡単に惹かれてしまう一方で、管理は非常に困難です。
こうした状況に直面して、代表団は、学校周辺の環境による食糧不安のリスクを最小限に抑えるために、学校、地方当局、機能部隊の間で検査や監督の面でより緊密な連携をとるとともに、宣伝活動を強化するよう勧告した。
セミナーで、ハノイ市教育訓練局のヴオン・フオン・ザン副局長は、2025~2026年度に、ハノイ市が初めて、地域の小学生の寄宿食支援の仕組みを規制するハノイ市人民評議会決議第18/2025/NQ-HDND号を実施すると述べた。
これは非常に人道的な政策であり、若い世代の総合的な発展に対する市の配慮を示しています。
この政策は学校給食の質に良い影響を与え、保護者の経済的負担を軽減するとともに、ほぼすべての小学生が寄宿給食に参加するよう促すものと期待されている。
しかしながら、寄宿食の規模の拡大に伴い、食品安全管理はこれまで以上に強化・強化していく必要があります。
フオン・ザン氏によると、学校は、サプライヤーとのサービス契約の締結から、厨房の設置と運営、定期的な監視に至るまで、科学的かつ厳格な食事管理プロセスを開発する必要がある。
強調された重要な要素の一つは、給食の質の監視において、学校、保護者、地方自治体が連携して取り組むことです。これが、学校における食の安全確保における残りのボトルネックを解消するための「鍵」となります。
「教育省は保健局、関係機関、そして地方自治体と連携し、学校給食施設の検査と点検を強化します。食品の安全を確保するだけでなく、生徒の食事配給が削減される事態を徹底的に防止することが目標です。共通の目標は、生徒の健康と成長を向上させ、安全で快適な学校環境を構築することです」とフオン・ザン氏は強調した。
また、この議論の中で、ハノイ市保健局のヴー・カオ・クオン副局長は、市は学校内外における食品安全確保の取り組みを指導・強化するための多くの文書を発行してきたと述べた。しかし、実施プロセスは依然として多くの困難に直面しており、大きな課題の一つは、学校給食に供給される食品の原産地の追跡である。
「最大の問題は、校門周辺で食べ物を売る人が絶えず変わっていることです。地元当局はこの問題の調査と対処のために抜本的な対策を講じていますが、食べ物の出所が不明であるため、完全に解決するのは依然として容易ではありません」とブー・カオ・クオン氏は述べた。
議論の枠組みの中で、代表団は学校給食管理の有効性を高めるためにこれまで適用されてきた、あるいは現在も適用されている多くの優れたモデルや実践的な解決策も紹介しました。
これらには、一方通行の厨房モデル、3段階検査、食品品質の定期的な公表の実施、食事の受け取りから加工までの全プロセスに監視カメラを設置すること、食品の原産地を追跡するためにQRコードを適用すること、寄宿舎の食事の管理にテクノロジーソフトウェアを使用すること、そして特に保護者の監督役割を強化することが含まれます。
さらに、透明性のある学際的な検査プロセスの構築、研修の実施、学校の寄宿業務を担当する職員の専門能力の向上など、多くの戦略的勧告もなされました。同時に、保護者が学校給食の監視に効果的、透明かつ組織的に参加できるよう、法的枠組みを整備することも含まれています。
食品の安全性を確保し、学校給食の質を向上させることは、教育、保健、地方自治体の責任であるだけでなく、社会全体の共通の課題でもあります。
多くの方面からの同時的かつ抜本的、責任ある参加があって初めて、学校給食は、国の未来の担い手である学生たちの心身の総合的発達と知性の総合的発達のための真に強固な基盤となることができるのです。
出典: https://baodautu.vn/hang-trieu-suat-an-moi-ngay-va-trach-nhiem-khong-the-loi-long-d379274.html



![[写真] ホーチミン市は2025~2030年任期の第1回党大会前夜、国旗や花で華やかに彩られている](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/10/1760102923219_ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-43-png.webp)



![[写真] プー・ジャーのユニークな馬帽子編み工芸](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/10/1760084018320_ndo_br_01-jpg.webp)



















































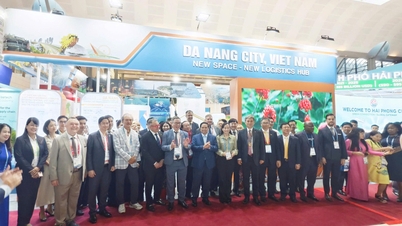










































コメント (0)