
国家イノベーション政策フォーラム - 写真: VGP/TG
科学技術省が国家イノベーションフェスティバル2025の枠組みの中で開催した国家イノベーション政策フォーラムでは、経営者、専門家、企業の全員が、イノベーションは開発の必須事項であり、ベトナムが今後10年間で飛躍的な発展を遂げるという願望を実現するための避けられない道であるという点で意見が一致した。
科学技術省イノベーション局長のグエン・マイ・ズオン氏は、イノベーション活動は党と国家の指導者から「高い」関心を集めていると述べた。現在の状況は多くの課題を突きつけており、政策と方向性を制度化し、イノベーション活動を実質的かつ効果的に推進するための実践的な行動が求められている。
グエン・マイ・ズオン氏によると、2025年6月に国会で可決された科学技術イノベーション法は重要な節目となる。イノベーションが初めて法律で明確に規定され、科学技術と同等の地位に置かれた。これは、イノベーションに基づく発展の促進に対する国家の認識と強いコミットメントを示すものだ。
現在、科学技術省は、政策が速やかに実行されるよう、特にイノベーションに関する具体的な規制など、法律の実施を導く文書を緊急に作成している。
企業はイノベーション システムの中心です。
イノベーション局のチュー・トゥック・ダット副局長は、企業が国家イノベーションシステムの中心であることを強調し、企業のイノベーションを奨励するために一連のインセンティブ政策が実施されていると述べた。
これらの政策には、税制優遇措置、融資金利の支援、研究資金の支援、技術革新などが含まれます。企業はまた、製品の商業化を促進し、消費者に新しいサービスや製品を体験してもらうための資金援助バウチャーを受け取ることもできます。
画期的な一歩として、革新的なスタートアップ企業に特化した証券取引所の設立と、国営ベンチャーキャピタルファンドおよび地方ベンチャーキャピタルファンドの設立計画が挙げられます。これらの金融商品は、ベトナムの革新的なスタートアップ・エコシステムに「血液を送り込む」ことが期待されています。
同時に、イノベーションセンターが接続点として形成され、研究成果の共有とエコシステム内の関係者間の緊密な連携を促進しています。目標は、各地域、各省庁、各セクターに少なくとも1つのセンターが設置され、大学や研究機関の参加を促進することです。今後2030年までに、全国で様々なレベルのイノベーションセンターを約100か所設置することを目指しています。
政令180号 - 官民連携の「てこ」
財政政策の面では、政令第180/2025/ND-CP号は、科学技術、イノベーション、デジタル変革の分野における官民協力の「てこ」となると考えられている。
財務省入札管理局の担当者は、この政令には、土地賃料の免除・減額、研究開発に対する税制優遇措置、リスク受容メカニズム、企業による研究成果の所有権の付与など、優れた優遇措置が多数盛り込まれていると述べた。特に、PPPプロジェクトへの国費拠出は、総投資額の最大70%まで認められる。さらに、国費拠出比率に算入することなく、国費から全額または一部を調達する仕組みも設けられた。
もう一つ注目すべき点は、減収差額の分配メカニズムです。このメカニズムにより、最初の3年間は減収差額の100%を分配することが可能です。これはオープンな政策とみなされており、企業が公共部門と安心して協力できるという信頼感を生み出しています。
「財務省は、科学技術イノベーション分野における官民連携(PPP)の実施において、関係機関、組織、企業を支援します。PPPハンドブックを作成し、各省庁、部局、地方自治体との直接対話を強化することで、困難を解消し、実施を促進していきます」と、財務省の担当者は強調しました。
ビジネスの観点から、ベカメックス・グループR&D研究所所長のダン・タン・ドゥック氏は、ベトナムにおけるイノベーションへの精神と決意は、今日ほど強いものはかつてなかったと述べました。法律、政令、通達による制度化は、国家が企業を支援するというコミットメントの証です。
ドゥック氏は、ベトナムは多くのグローバルテクノロジー企業の生産拠点となっているものの、その多くは組み立て段階にしか関与しておらず、製品価値のわずか1~3%を占めるに過ぎないと指摘した。課題は、製品における技術コンテンツをどのように高め、グローバルバリューチェーンへの参加を徐々に深化させていくかにある。
ドゥック氏によると、テクノロジー、経営、労働者のスキルに投資することで、企業は競争上の優位性を生み出し、テクノロジー集約型、さらには知的集約型へと進むことになるという。
国際的な教訓と現地の実践
宇佐川剛教授(熊本大学)は、国際的な経験に基づき、イノベーション・エコシステムを形成するには、政府、大学、企業の緊密な連携が必要だと考えています。宇佐川教授は、大学の研究からスタートアップ企業を創出すること、企業が研究を発注すること、そしてコミュニティのアイデアをコンペティションを通じて創出すること、という3つの共通の方向性を指摘しています。
日本は、実験室での研究と商業化の間に「ギャップ」を抱えています。これを克服するため、2004年以降、大学主導のクラウドファンディングを活用し、大学に自主性を与えることで、連携の拡大と知的財産の商業化を推進してきました。
ダナン市人民委員会のホー・クアン・ブウ副委員長は、現地の事例を紹介しながら、ダナンは14年連続でベトナムICT指数をリードしており、2021~2025年の期間に20億ドル以上の技術投資を誘致し、2万人の質の高い雇用を創出したと語った。
この地域は、技術系人材に対する免税、新興企業への支援、新しい技術ソリューションの制御されたテストの許可などの特別な政策メカニズムを適用しており、そのおかげで、ライセンスを受けた実験的な暗号資産変換プロジェクトなど、多くの画期的なプロジェクトが登場しました...
ダナンは、デジタルインフラ、ソフトウェアパーク、地域データセンター、AI、ビッグデータ、行政自動化プロジェクトの開発にも注力しています。「イノベーションは選択ではなく、開発の必須事項です」とホー・クアン・ブウ氏は断言しました。
専門家は、ベトナムが二桁台の高い経済成長を達成するために、イノベーションは避けられない道であると考えています。政策システムの連携強化、企業の積極的な参加、イノベーションセンターの設立、そして国際的な支援により、ベトナムは自信を持って新たな発展段階へと進むための十分な基盤を築いています。
トゥ・ザン
出典: https://baochinhphu.vn/lan-gio-moi-tu-chinh-sach-doi-moi-sang-tao-dong-luc-cho-tang-truong-102251002144847191.htm


















































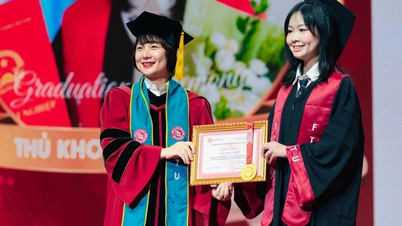














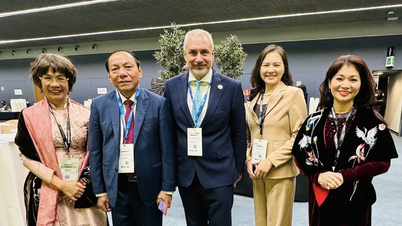








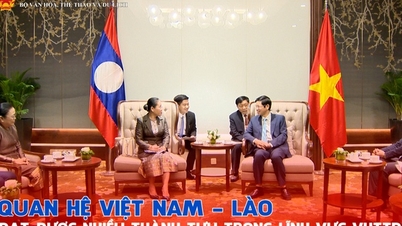



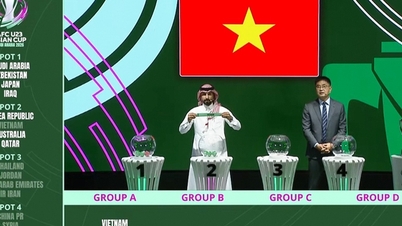





















コメント (0)