実際、一部の国の間では水面下で競争が繰り広げられてきました。そのため、近年、 経済先進国であるアジア諸国は、それぞれの国の特性を最大限に活かすため、様々なレベルでソフトパワーの構築と推進に積極的に取り組んでいます。

ソフトエコノミクス
ブランドファイナンスによる2024年ソフトパワー国ランキングで、中国は3位にランクインしました。ブランドファイナンスによると、このランキングは中国のビジネス、貿易、 教育、科学指標の変化に基づいています。「ソフトパワー」という概念が初めて明確に言及されたのは、2007年の第10回中国共産党大会でした。当時、胡錦濤前国家主席は「国の偉大な復興は、必ずや中国文化の力強い発展を伴うだろう」と述べました。2014年の共産党大会では、習近平国家主席も「我々はソフトパワーを強化し、中国の良いストーリーを提示し、中国のメッセージを世界により効果的に発信すべきだ」と述べました。
国際関係アナリストのジョシュア・カーランツィック氏は、中国は国際援助を通じてソフトな経済力を構築していると主張している。これには巧みな経済外交が含まれ、大規模な地域貿易協定や協力的な政府開発援助(ODA)の拡大に反映されている。東南アジア、アフリカ、中東、ラテンアメリカはいずれも中国のソフトパワーの直接的な影響を受けている地域である。中国の指導者たちは「一帯一路」(BRI)をソフトパワーの手段と位置付け、地域の連結性を促進することを求めている。中国がソフトパワーを拡大するためのもう一つの手段は、2004年に韓国のソウルに最初の孔子学院を開設した孔子学院である。
また、中国教育部傘下の非営利団体で、中国語講座、料理教室、書道教室、中国の国民の祝日のお祝いなどを提供するセンターもあります。
国家イメージの向上
日本はこのランキングで4位にランクインしました。平和国家のイメージを広め、日本の文化的価値の重要性を改めて認識させるだけでなく、ソフトパワーの向上は市場拡大や文化産業製品の海外輸出促進にもつながり、日本経済の回復と成長に貢献することが期待されます。
21世紀初頭以降、「ソフトパワー」という概念は、日本政府の議論や政策文書においてますます頻繁に言及されるようになりました。2003年には、外務省と国際交流基金が、欧米諸国との文化交流組織およびプログラムに関する包括的な調査を実施しました。その結果に基づき、2004年には、日本政府は外務省内にコミュニティ外交、すなわちパブリック・ディプロマシーを担当する専門部局を設置し、同時に、東アジア地域諸国への日の出ずる国の伝統文化の普及を組織するため、日本文化外交展開特別委員会も設置しました。「ソフトパワー」という概念は、同年の外交青書において正式に言及されました。
日本がソフトパワーの推進において現在成功を収めているのは、政府が「政治外交」から「パブリック・ディプロマシー」へと政策を転換したおかげです。文化の力の持続性と安定性を認識し、日本は音楽、料理、言語などを海外に広めることに注力してきました。特にマンガとアニメは、その重要な要素です。この「文化輸出」のプロセスは、経済的な勢いを生み出し、日本の地位を強化するだけでなく、近代的で豊かで平和を愛する大国という新たなイメージの魅力を高めることにもつながります。
日本は、定期的かつ継続的な援助活動に加え、気候変動対策や地域の安全保障問題への取り組みにおいても主導的な役割を果たしてきました。ポップカルチャー、外交政策、政治的価値観を融合させた日本の多面的なソフトパワー戦略は、東南アジアを含む世界の多くの地域で効果を発揮しています。
ブランドファイナンスは、ナショナルブランドの価値を評価する重要な要素の一つとして、毎年「グローバル・ソフトパワー・インデックス・レポート」を発表しています。これは、各国のソフトパワー評価に関する包括的な調査レポートとされています。最新の調査は、ブランドファイナンスが国連加盟国193カ国の17万人を対象に実施したもので、ビジネス、貿易、ガバナンス、国際関係、文化・遺産、メディア・ジャーナリズム、教育・科学、人々という柱のパフォーマンスに関する集計データに基づいています。さらに、ナショナルブランドの知名度、世界的な評判といった評価基準も設けられています。
タン・ハン
[広告2]
ソース

























































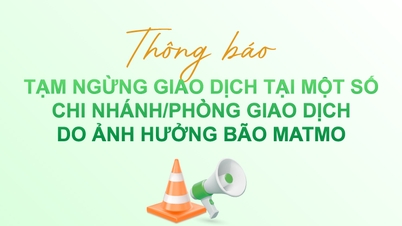



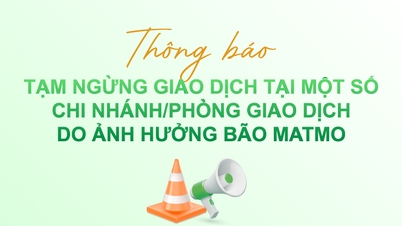






































コメント (0)