
SSEAYP 2024の代表団はホーチミン市到着初日の夜、2階建てバスで夜の街を散策した- 写真:THANH HIEP
ホーチミン市への寄港は、東南アジア10カ国(不参加のミャンマーを除く)と日本から参加した東南アジア・日本青年の船の若者たちにとって、S字型に広がるベトナムの人々の温かさと親しみやすさに触れ、多くの美しい思い出と印象を残す貴重な機会となりました。特に、時事問題に関する知識や視点を共有し、文化を学び、ベトナム料理を体験しました。
環境と持続可能な開発について議論する
ホーチミン市での2日目には、学生たちは6つの場所に分かれて、ソフトパワーと人民外交、持続可能な経済と地域社会の発展、地球環境と気候変動、リスク軽減と災害後の復興、健康と社会保障、デジタル社会などのテーマについて、講演者や市内の若者と交流し、 議論しました。
ホーチミン市経済大学における持続可能な経済とコミュニティの発展というテーマでは、発生源での廃棄物の分類、リサイクルと再利用の増加、使い捨てプラスチック製品の制限の重要性が強調されました。
グループディスカッションから、参加者は、持続可能な開発や環境コースに関する若い世代への教育方法を多様化するとともに、多くの企業や組織と連携して持続可能な開発モデルについて学ぶための現地視察を企画する必要があるという結論に達しました。
ホーチミン市にあるベトナム国立大学(ベトナム国家大学)では、リスク軽減と災害復興について議論が交わされ、プラスチック廃棄物が環境にとって最大の問題となっているという意見で一致しました。ベトナム代表団が共有したプロジェクトの一つは、アロエベラを食品ラップとして使用することでした。これは、ベトナム国立大学で開発された環境に優しい解決策です。
ウォルター・ジェームズ・A・ジュマオアス氏(フィリピン)は、生分解性廃棄物を地域社会でより有効活用できるよう最適化することが非常に重要だと述べた。「私たちは日々、自分たちが作り出し、使うものに責任を持たなければなりません。すべての人、特に若者は、ゼロ・ウェイストの意識に変わる必要があります」と彼は述べた。
ベトナムは、その誠実さと温かさで私の心に触れました。初めて訪れたのですが、この場所は私の心に忘れられない痕跡を残しました。ベトナム、里親家族、そしてこの国で過ごした短いながらも意義深い日々に寄り添ってくれたすべての方々に感謝申し上げます。
水口 優香(日本代表)
文化と人類の架け橋
SSEAYP 2024のハイライトの一つは、ホーチミン市トゥドゥック市と13の地区でホームステイを体験することです。参加者はホストファミリーと滞在し、ベトナムの食文化に触れ、歴史、文化、そしてベトナムの人々について、最も親密で本物の体験を通して学びます。
好奇心から初めてサトウキビジュースを飲んでいた日本人の友人もいました。また別の友人は牛肉麺と砕いたご飯を食べに連れて行かれました。多くのベトナムの若者は、近隣の民族連帯祭に外国人代表を連れて参加し、国際色豊かな若者たちにベトナム人とのコミュニティの繋がりを感じてもらう機会を提供しました。
トゥドゥック市青年連合のファン・ゴック・ドアン・トラン事務局長は、地元の人の家に泊まることはベトナム人の文化、習慣、生活様式をより深く理解するための貴重な経験が多くあり、特別で忘れられない経験になるだろうと語った。
「これは、国際的な若者とホーチミン市の若者や人々との間に、密接で深い関係を育む機会でもあります」とトラン氏は述べた。
ホストファミリーで過ごした2日間は短すぎるように思えましたが、代表団員の水口由香さん(日本)の心の中には忘れられない思い出が数多く残りました。ホーチミン市の人々が今年のプログラムの代表団に寄せてくれた温かい愛情を、彼女自身だけでなく、彼女自身にとっても「想像を絶するほど温かい歓迎」だったと彼女は語りました。
「電車を降りた瞬間から、皆さんの目と笑顔から温かさとおもてなしを感じました。グエン・ティ・ハンさんのご家族に4区にあるご自宅までお迎えいただき、初めて会ったという感じではなく、まるでずっと前から知り合いだったかのような気持ちになりました。ご家族全員が誠実で、自然体で、とても親密に接してくださったので、本当に感動しました」とユカさんは語りました。
ベトナムの人々の独特な文化について、たくさんの興味深いことを学んだと自慢していましたね。ユカさんは、言語や文化の違いにもかかわらず、魔法のように目に見えない糸が皆を繋いでいると言い、それを「皆が分かち合い、繋がることを目指しているからこそ、心の調和が生まれる」と表現しました。
そして、ユカさんにとってベトナムは単なる旅行先ではなく、素敵な親戚や忘れられない教訓や思い出がたくさんある第二の故郷のような気分にさせてくれる場所でもあります。

リー・ティ・グエット・アンさん(第7区)の里親家族が、2人の友人、アクイラ・ナターシャさん(ブルネイ)とジャムスリさん(タイ)を戦争証跡博物館に連れてきました。写真:タン・ヒエップ
東南アジア・日本青年船の代表団が歴史を探る
多くの代表団はベトナムの歴史について学び、戦争証跡博物館(第3区)を見学しました。ブルネイ代表のアクイラ・ナターシャ氏は、「この博物館に展示されている写真や遺物は、ベトナムが経験した戦争の激しさを部分的に示している」と述べました。しかし、喪失感や痛みよりも、ベトナム国民の連帯感と回復力の方がはるかに大きいと感じます。
ブルネイからの代表団は、ベトナム国民が戦争のトラウマを奮い立たせ、今日のように強い国を築き上げたことに深く感銘を受けたと述べました。帰国後、この経験を友人や家族に伝えたいと述べました。
ウォルター・ジェームズ代表(フィリピン)は、博物館を訪れたことで、平和と人権を守ることの大切さを改めて認識できたと述べました。ジェームズ氏によると、博物館が示す教訓は、ベトナムの人々だけでなく、訪れるすべての人々に戦争の結末を思い出させるものでもあるとのことです。
「この旅は、ベトナムの歴史をより深く理解することができただけでなく、戦争のない、誰もが平和で人間らしく暮らせる世界を築くには、若者が先頭に立たなければならないことを実感しました。SSEAYPを通して、国々の間の連帯と相互理解の精神がさらに強化されることを願っています」とジェームズさんは語りました。
一方、代表のジャムスリ氏(タイ)は、「戦争の結果は常に壊滅的だが、こうした出来事は、独立と自由の価値をより深く理解する助けとなる」と述べた。
オンライン診療受付システム
ホーチミン市医科薬科大学では、世界的な医療へのアクセス、心身の健康の現状と解決策について、学生たちから健康と幸福というテーマが取り上げられました。
意見では、患者の待ち時間を短縮するため、オンライン診療受付システムの構築に注力する必要があると述べられており、高齢者、妊婦、子ども、障害者を優先的に受診できるようにすべきである。また、診療施設の設備と人的資源の質の向上も求められている。
高齢者への医薬品の無償配布・配達政策も提案されました。同時に、医療アプリをアップデートし、人々が医師の診察や医師からの情報へのアクセスを最大限便利に行えるようにする必要があります。
 SSEAYP代表団がベトナムに別れを告げる
SSEAYP代表団がベトナムに別れを告げる





![[写真] 第1回政府党大会の厳粛な開会](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/13/1760337945186_ndo_br_img-0787-jpg.webp)

























![[写真] ト・ラム書記長が第1回政府党大会の開会式に出席](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/13/1760321055249_ndo_br_cover-9284-jpg.webp)












































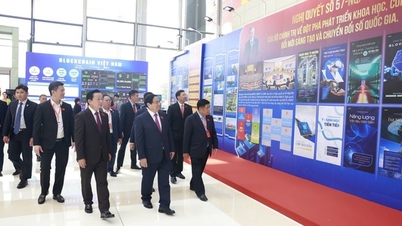




























コメント (0)