8月5日午前、 教育訓練省は、二階層地方自治の実施における教育の国家管理の分権化の展開に関する会議を開催した。ファム・ゴック・トゥオン常任副大臣が議長を務めた。会議には、教育訓練省傘下の各部署の指導者や専門家、34の教育訓練局の指導者、教育訓練局傘下の専門部局・課、関連部局・部門・セクターの代表者、コミューンレベルの人民委員会の指導者、コミューンレベルの教育関係者、就学前教育機関、一般教育機関、職業教育・継続教育機関の代表者が出席した。
この会議は全国で対面式とオンライン式の両方で開催され、5万人以上が参加し、そのうち約90%がコミューンレベルの参加者でした。
地方自治体は積極的かつ創造的な精神を奨励する
ハノイ市教育訓練局長のトラン・テ・クオン氏は、人材に関する最大の懸念を共有し、「ハノイ市では、 文化社会局の公務員347人のうち、教員免許を持つ職員が教育担当に任命されているのは212人です。中には、専門分野は就学前教育であるにもかかわらず、小学校と中学校の両方を担当しているケースもあり、非常に困難です」と述べました。
ハノイの経験では、各クラスターは基本的に以前の地区と同じ範囲で、支援、問題解決、競技会の開催、教師の採用、 教育関連目標の割り当てなどの活動を実施しています。加えて、専門的な業務に依然として困難を抱えるコミューン/区を支援するために、草の根レベルの教育職員を派遣し、コミューンレベルの教育職員の研修を強化しています。コミューン/区レベルの大会を活用し、大会決議に教育関連の内容を盛り込んでいます。情報技術とデジタルトランスフォーメーションを徹底的に活用し、特に小学校の入学選考に活用しています。
ホーチミン市教育訓練局長グエン・ヴァン・ヒュー氏によると、教育訓練省の各部局は、教育の国家管理の分野における地方分権、権限委譲、二級地方自治体の権限分割に関する法的文書をまとめ、地方自治体による監視と実施を支援している。
ホーチミン市教育訓練局は、新学期の準備として、168の区・町村の教育職員を対象とした研修を実施します。研修では、施設、設備、教材、教員、教育管理職員などの状況の見直しに重点が置かれます。グエン・ヴァン・ヒュー氏は、多くの困難にもかかわらず、教育訓練局は区、町村、特別区、町村と効果的に連携し、2025-2026年度に向けて最善の準備を整えてきたと述べました。
ホアソン区(ダクラク省)人民委員会のフイン・ヴィエット・チュン委員長は、二層制の地方自治体による教育管理には多くの利点があることを認めつつ、仕事量が多すぎる場合、職員数が少なすぎる場合、教育に関する専門知識がない場合の困難についても言及した。
これらの困難に直面したホアソン区は、幼稚園、小学校、中学校の3つの専門グループ(それぞれ文化社会局の専門家と教育施設管理職員を含む3~4名)を設立し、教育訓練局の以前の専門家に助言を与え、交代させるという解決策を講じました。
フイン・ヴィエット・チュン氏は、業界の文書とデータのシステムを連携させる問題や、特に困難な地域、少数民族地域での教師不足を克服するための解決策など、作業をより効果的に実行するための希望や提案もいくつか共有しました。
タンザン区(カオバン)人民委員会のグエン・ミン・チャウ委員長は、草の根レベルの教育運営のニーズに応え、非常に実践的でタイムリーな会議を開催してくれた教育訓練省に感謝の意を表し、「タンザン区には幼稚園から中学校まで、12の教育機関があり、124クラス、生徒数3,541名を擁しています。学校は不均一に分布しており、多くの学校や複式学級は区の中心から10~15km離れた場所にあります」と述べた。

グエン・ミン・チャウ氏は、新政府モデルの導入に伴う教育管理における利点と課題について、コミューン政府と区政府は地域に直結しているため、住民、保護者、生徒の状況、ニーズ、具体的な要望を最もよく理解できると述べた。教育訓練局の規模縮小は、職員の削減と組織の合理化に加え、コミューンレベルの自治権と柔軟性の向上にもつながる。コミューンレベルに直接管理権限が付与されることで、コミューンは地域教育開発計画の策定、施設の管理・運用、計画の見直し、新設、修理、設備購入などにおいて、より積極的に取り組むようになる。
「コミューンレベルで直接管理することで、学校での新プログラムに沿った教育と学習の組織化により深く関与し、施設や教員の面での新プログラムの要件をよりタイムリーに満たすようになり、その結果、施設でプログラムがよりよく実施されるようになると確信しています」とグエン・ミン・チャウ氏は述べた。
タンザン区人民委員会委員長は、困難点について、コミューンレベルの職員135人のうち、教育学の資格を持つのはわずか36人だと述べた。コミューンレベルの指導者は主に行政管理の経験があり、教育管理の専門知識を持つコミューンレベルの指導者はごくわずかである。一方、教育管理には独自の特徴があり、行政管理だけでなく、プログラム、教授法、生徒心理、教員管理など、多くの専門分野への理解が必要となる。
グエン・ミン・チャウ氏は、これまで実施してきた活動について共有し、タンジャン区が数人の主要教師と面会し、地域の数人の教育専門家から意見を聞いて状況を把握したと伝えた。同時に、地域にある12校の主要教員との作業セッションを組織し、直接現場に出向いて数校の施設の状況を把握した。
「我々はまた、この期間中の中央政府の方針に沿って、この地域で柔軟な寄宿学校のパイロットモデルを構築するための初期調査と調査を実施しています」とグエン・ミン・チャウ氏は付け加えた。

組織と実行における「4つのノー」を徹底する
会議の締めくくりの挨拶で、副大臣は、会合の会場に5万人以上が集まった際、教育訓練局、コミューンレベルの人民委員会、コミューンレベルの教育責任者、教育機関の管理者らが示した責任感と配慮を評価し、感謝の意を表した。
副大臣によると、今回の会議だけでなく、教育訓練省と省・市、教育訓練省と教育訓練局、そしてコミューン間のあらゆる日常業務において、共通の精神は「傾聴し、理解し、共有し、問題を解決し、共に創造する」ことである。管理職が傾聴し、共有し、理解し、共に問題解決に取り組み、共に創造しなければ、コミューンレベルの課題は困難を極めることになるだろう。
副大臣はまた、これまでうまく実行されてきた「4つの積極的措置」を指摘した。それは、状況をタイムリーに積極的に把握すること、訓練と指導を積極的に提供すること、困難を積極的に排除すること、割り当てられた責任とタスクに従ってタスクを積極的に実行することである。
今後、副大臣は、文書システム、特に教育訓練省がデジタル化して地方に送付した文書を精査し、実施体制を整備して作業を開始し、問題点や課題を整理して、速やかに所管官庁に報告する必要があると強調しました。そうすることで初めて、あらゆる問題点や課題を把握し、そこから解決策を見出すことができるのです。
組織実施においては、管理内容の空白がない、管理内容の重複がない、管理内容が不明瞭、管理方法が不明瞭という「4つのノー」の精神を徹底的に把握する必要がある。
副大臣は「管理方法」を強調し、情報技術やデジタル化の活用など、管理思考、リーダーシップ、そして管理手法の革新が必要だと述べた。特に、コミューンレベルの指導者は、管理下にある各部署の校長と副校長の選任計画を綿密に策定する必要がある。これらの校長と副校長は、能力、責任感、そして実務経験を備えた人材でなければならない。
副大臣は演説の中で、党と国家の指導者が徹底して理解している「6つの明確化」の精神、すなわち「人を明確にする」「仕事を明確にする」「責任を明確にする」「権限を明確にする」「時間を明確にする」「成果を明確にする」を改めて強調した。会議では地方から提案・提言されたいくつかの問題についても議論され、副大臣は回答した。
会議では、一般教育部、法務部、教員・教育管理者部、就学前教育部、職業教育・継続教育部、財務計画部の代表者が、担当部署の分野における二級地方自治に基づく教育の国家管理の実施について指導を行いました。同時に、村レベルの人民委員会傘下の教育訓練部、文化社会部が二級地方自治に基づく教育の国家管理を効果的に実施できるよう、提案、提言、留意事項を発表しました。
出典: https://giaoducthoidai.vn/4-khong-trong-quan-ly-giao-duc-khi-thuc-hien-chinh-quyen-dia-phuong-2-cap-post742851.html





![[写真] 朝鮮労働党創立80周年記念パレードに書記長が出席](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/11/1760150039564_vna-potal-tong-bi-thu-du-le-duyet-binh-ky-niem-80-nam-thanh-lap-dang-lao-dong-trieu-tien-8331994-jpg.webp)
![[写真] ホーチミン市は2025~2030年任期の第1回党大会前夜、国旗や花で華やかに彩られている](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/10/1760102923219_ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-43-png.webp)































































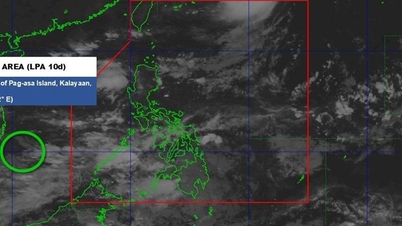
































コメント (0)