懸念されるのは、質の低い科学というよりも、科学の運営方法である。論文数、引用数、ランキングが、実質に取って代わっている。こうした状況において、科学的誠実性は、単なる倫理規範ではなく、科学が自己破壊的なスパイラルに陥らないための糸として、生き残りを左右する問題となる。
「学術的誠実性」は長年にわたり盛んに議論されてきたものの、実際にはほとんど何も行われてきませんでした。大学、研究機関、そして規制当局は、規制、基準、そしてコミットメントを定めてきました。しかし、多くの研究者は依然として、剽窃、論文の売買、そして目標を達成するためのデータの歪曲といった近道を選んでいます。その結果、多くの隠れ蓑はあっても魂のない科学が誕生しました。
科学的誠実さは、壁に掲げられたスローガンでも、発見されることへの恐怖でもありません。それは、すべての研究者の内なる資質、すなわち自尊心、真実を語る勇気、そして容易だが非倫理的な道を拒む勇気として育まれるべきものです。
人工知能(AI)が多くのタスクを「代行」してくれる時代において、人間に残された唯一のものは誠実さです。AIは論文を書き、データを統合し、統計を分析し、一見合理的な結果を「生み出す」ことさえできます。しかし、それはまだ科学と言えるのでしょうか?それとも、アルゴリズムによって色付けされた「人工物」に過ぎないのでしょうか?この問いは、私たちを根底から問い直すよう促します。科学とは、単に新しい情報を生み出すだけでなく、真実を探求することなのです。そして、真実は誠実さがあって初めて現れるのです。
さらに危険なのは、論文発表へのプレッシャーと定量評価のシステムが、人々をAI濫用のスパイラルに陥れてしまうことです。目標が「真実の発見」ではなく「論文を一つ手に入れること」になった時、AIはその空虚さを埋めるための完璧なツールとなってしまいます。これが最大のリスクです。
この時代において、私たちは異なる視点を持つ必要があります。誠実さは制約ではなく、真のイノベーションの源泉です。AIがほぼ無限に複製できる世界において、真正性と結果に対する説明責任だけが価値を生み出すのです。
ここでの誠実さとは、「不正行為をしない」ということではなく、機械化時代における創造性を再定義する能力です。誠実な人は、自らの限界を認めることを恐れません。たった一つの誤ったデータ、たった一つの歪んだ数字が、コミュニティ全体を盲目にしてしまう可能性があることを知っています。誠実な人は、知識が単なる個人の財産ではなく、人類の遺産の一部であることを理解しています。
その意味で、誠実さとは、たとえ不都合なことがあっても、たとえ個人の成長を遅らせることになっても、真実に正直である勇気です。そして、この姿勢こそが真の創造性、つまりAIでは再現できない創造性への道を切り開くのです。
誠実さを実現するには、科学研究のための新たなエコシステムが必要です。評価方法を変える必要があります。論文数を数えるのではなく、実質的な影響、新規性、そしてコミュニティへの貢献を考慮する必要があります。倫理と技術を両立させる必要があります。つまり、各研究は、データの出所、処理方法、そしてAIの役割について明確なコミットメントを持つ必要があります。
同時に、誠実性教育を初期段階から教え込むべきです。学生はレポートの書き方を学ぶだけでなく、倫理的な状況を経験し、成果よりも真実を選ぶ勇気を身につけます。オープンデータ、コミュニティが監視し責任を共有できるオープンプロセスなど、オープンで透明性のある研究を推進します。誠実性が文化規範になれば、誰も科学を「疑う」必要はなくなります。なぜなら、透明性が答えを与えてくれるからです。
出典: https://thanhnien.vn/liem-chinh-khoa-hoc-thap-sang-su-that-185251002204147723.htm



![[写真] ファム・ミン・チン首相、嵐10号の影響克服に向けた会議を主宰](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/3/544f420dcc844463898fcbef46247d16)
![[写真]ビンミン小学校の生徒たちは満月祭を楽しみ、子ども時代の喜びを受け継いでいる](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/3/8cf8abef22fe4471be400a818912cb85)









































































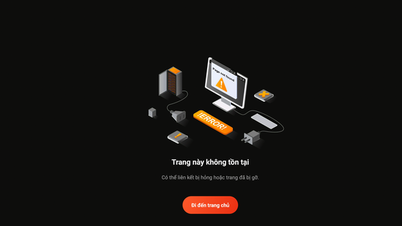
































コメント (0)