私は田舎生まれなので、幼少期は故郷の田んぼのかび臭い匂いや、強い藁の匂いに包まれていました。友人たちは皆、今はそれぞれ別の場所にいます。生計を立てるために外国へ行った人もいれば、北の国に嫁ぎ、夫と共に南の国へ急ぎ移った人もいます。私は都会で暮らし、働いています。午後の風に漂う新米の香りを感じるたびに、故郷への郷愁が強く胸を突き刺します。

イラスト:LNDUY
ああ、遠い昔の午後、青い煙に混ざった藁の匂いが懐かしい。胸が痛むほど遠い。記憶の中の田園風景は、まるで色とりどりの絵のようだ。堤防の斜面に咲き乱れる野の花々は、毎朝、揺らめきながら太陽を待ちわびている。通り過ぎる人々の足元に、また来ると約束するかのように、しつこく寄り添う野草の群落。収穫期には、早朝から田園風景は笑い声で賑わう。
当時の農業は、今日ほど近代化されていませんでした。母や姉妹たちは、背中を汗だくにしながら、白い帽子を田んぼに揺らしながら、慌ただしく稲刈りをしていました。まるでコウノトリが季節の到来を告げるように。田舎道では、荷車に積まれた稲が、天日干しのために慌ただしく運ばれていました。
村ができた当初から、どの家にも黄金色の稲がいっぱいの庭があり、私たち子供たちはよく田んぼを歩き回り、「稲を耕す」と言って、稲を早く乾かしていました。時折、太陽が照りつけ、強い風が吹き、暗い雲が立ち込めると、家族全員が食卓を囲み、慌てて立ち上がり、気まぐれな午後の雨と競い合いながら「稲を守ろう」としました。
農作業は毎日続く。稲が乾いて初めて、新米の入った釜のそばで一息つける。
あっという間に畑は刈り取られ、畦道にまで藁が敷き詰められました。収穫が終わると、故郷ではどの家の庭の隅にも藁が積み上げられていました。故郷の藁の香りが大好きでした。
鼻先にしがみつくような、スパイシーで温かい香りが長く続く。麦わらの香りと、背中を焦がす太陽に毎日鍬を担いで畑へ向かう農民たちの汗が混ざり合った香り。母の苦労と苦労の香り。豊作の喜びの香りと、不作のたびに農民たちの目に深く刻まれた悲しみの香り。
藁の匂いは、田舎の人にとって忘れられない田んぼの匂いです。昔を懐かしむ、藁の香ばしい匂い。だから私にとっては、「故郷に着いただけで/藁の匂いが/もうすっかり/私を夢中にさせている」(邦璜)。都会の喧騒の中で、生活の苦労の中で、ただ深呼吸をして、思い出に浸りたいと思うことが何度もあります。
裸足で黄色い藁にくるまり、友達とかくれんぼをしていた子供の頃を思い出す。故郷の思い出は、いつも畑の香りと風の中に深く刻まれている。そこには、ほのかに漂う藁の香りが、懐かしい土地にゆっくりと広がっていた。どこかに忘れ去ったかのような藁の香りが、ふと、胸を躍らせるような感覚とともに蘇ってきた。
何年も経ち、自分がもう若くないことに気づいた時、田舎の田園風景は忘れられない記憶の一部となっていた。それは、人生における無垢で純粋な幼少時代だった。藁の匂いを思い出しながら、私は愛を集めたいという欲望と夢を胸に抱き続けた。そして、今日の午後、突然、太陽の光と風に、黄金色の藁が舞い上がっていた…
アン・カーン
ソース






![[写真] 民族学博物館で賑わう中秋節](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/4/da8d5927734d4ca58e3eced14bc435a3)
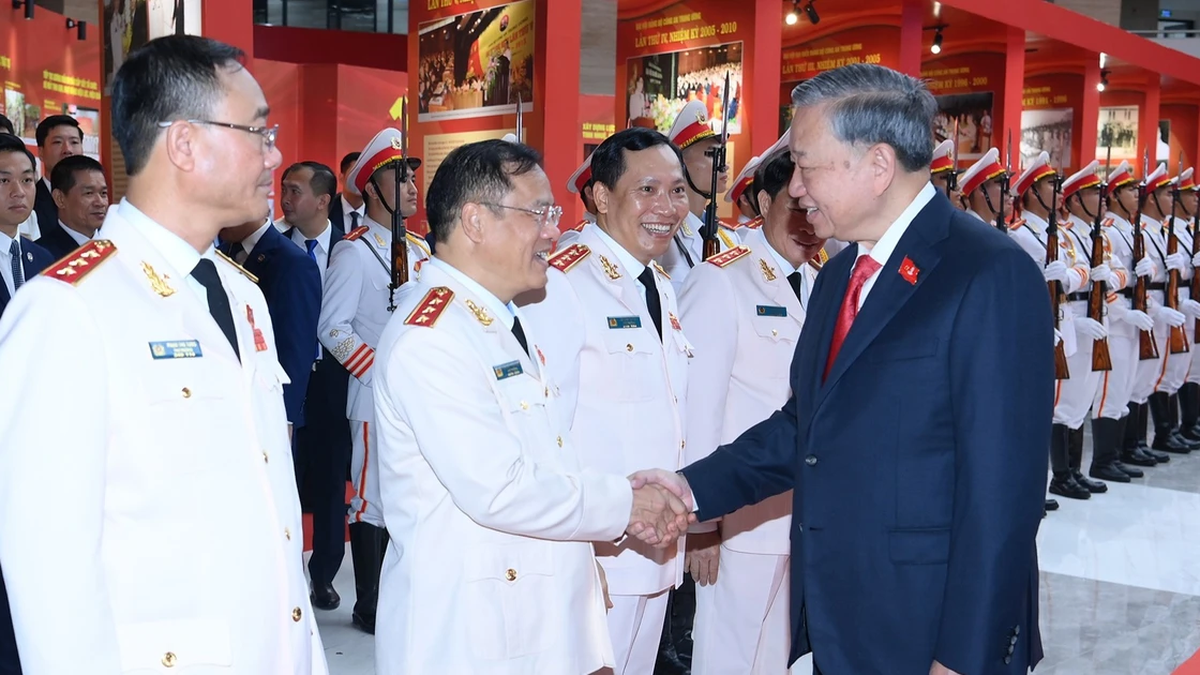




















































![[ビデオ] ペトロベトナム50周年記念式典の概要](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/4/abe133bdb8114793a16d4fe3e5bd0f12)
![[動画] ラム事務総長がペトロベトナムに8つの黄金の言葉を授与:「先駆者 - 優秀 - 持続可能 - グローバル」](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/23/c2fdb48863e846cfa9fb8e6ea9cf44e7)




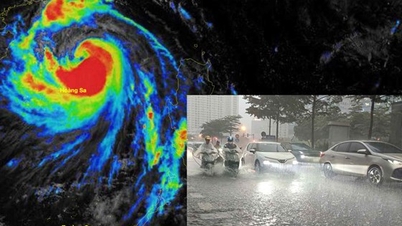


















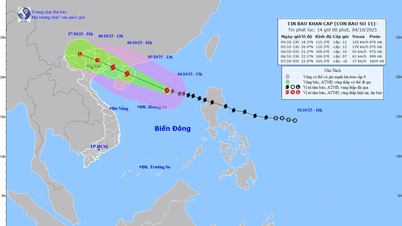









コメント (0)