ヴァンが帰ってきた日、故郷では収穫の真っ最中だった。藁と新米の香りが辺りに漂い、かつてヴァンの思い出の詰まったホウオウボクも花を咲かせていた。
ヴァンの故郷はロアン村と呼ばれていた。なぜそう呼ばれているのか、ヴァンは理解できなかった。村を出る前、ヴァンは村の人たちに尋ねてみたが、誰も彼女の質問に答えられなかった。「別にいいわ。別に気にする必要はないわ。ロアン村はそれでもいい村なのに」とヴァンは思い、それ以上誰にも尋ねなかった。
ロアン村の入り口には、古木のホウオウボクがあります。その広い樹冠は、広大な土地に日陰を落としています。子供たちや村人たちは、その周りによく集まり、涼しい風に吹かれながら、おしゃべりを楽しみます。
ホウオウボクの花が咲き、村人たちは夏の到来を悟りました。子どもたちは学校が休みになるのを心待ちにしていました。ホウオウボクがいつからそこにあったのか、誰も知りませんでした。村の長老たちは「ずっと前からそこにあったんだ」と言いました。
故郷を離れて3ヶ月、村に戻った日、彼女はホウオウボクの木の前を通り過ぎました。ヴァンは家に戻るまで、長い間その木の下に立っていました。彼女にとってホウオウボクの木は思い出の一部でした。嬉しい時も悲しい時も、彼女は木の下で遊んでいました。母親が亡くなった時、それはまるで心の支えのような存在でした。
ヴァンの母親は、彼女が16歳になったばかりの頃、事故で亡くなりました。あの運命の日の午後、ヴァンがホウオウボクの木の下に座っていたところ、村人たちが落雷の知らせを届けに駆けつけました。ヴァンは飛び上がって皆の後を追いかけました。到着すると、母親は古いマットにくるまっていました。ヴァンは叫び声を上げ、そして気づかないうちに気を失いました。目が覚めると、ヴァンは自宅のベッドにいました。外では、近所の人たちが葬儀の準備のためにテントを覆っていました。
 |
イラスト:中国。 |
母が亡くなった後、ヴァンはいつも酒浸りの父親と暮らしていました。それから1年以上経ち、父親は再婚しました。隣村に住む、既に子供がいる女性と結婚したのです。ヴァンの人生は生き地獄のように感じられるようになりました。「たくさん勉強しても上達しない。生活のために仕事を探す心配は無用よ」と、継母は毎日ヴァンの耳元で囁き、時には声を荒げました。日に日に、ヴァンはもはや教育のために戦うことができなくなりました。彼女は夢と野心を捨て、家を出ることを決意しました。
「仕事を見つけて生計を立てなさい」その日、継母の怒りの声がまだ響いていた。しかし、ヴァンはどんな仕事を探せばいいのか分かっていた。誰も彼女を助けてくれなかった。父親は一日中酔っぱらっていた。継母は結婚式の日を除いて、彼女に幸せな一日を与えたことがなかった。
ヴァンはそのことを、一番近い隣人であるフォン夫人に話しました。「髪の切り方を習ったらどう?」とフォン夫人はアドバイスしました。
「私は視力が悪いので、その職業を学んだらお客様の髪を台無しにしてしまうかもしれません」とヴァンさんは答えました。
「もしそうなら、裁縫学校に行きなさい。学校を卒業したら、とにかく働いてお金を稼ぎなさい。資金が貯まったら、故郷に戻ってお店を開けばいいのよ。」
「いいえ、裁縫を学ぶのは好きではありませんし、それに私たちの村にはすでに仕立て屋がいくつかあります。」
「もういいわ。あなたにはもううんざりよ。どんな職業であれ、あなたは議論ばかりするのよ」とフォン夫人は言い、立ち上がり、帽子を振りながら立ち去った。
「これからどんな職業に就こうかしら?」とヴァンは独り言を呟き、歩き去った。彼女は考え事をしながら、いつの間にかホウオウボクの木へと辿り着いていた。
母が亡くなる前、二人はいつもホウオウボクの木の下で涼しい風を感じていました。「将来は医者になるんだ」とヴァンは母に言いました。「お父さんはこんなに若いのに夢を見ている。まずは勉強に集中しなさい。ちゃんとした教育を受けさせてあげるから、苦労しなくていいんだよ」。母がまだ生きていた頃、ヴァンの母はいつもそうアドバイスし、励ましていました。しかし、母が亡くなったことで、その計画もヴァンの夢もすべて葬り去られてしまいました。
フォン夫人に裁縫学校に行くように勧められた日、ヴァンは反論した。しかし結局、彼女はこの職業を選ぶことにした。ヴァンには他に選択肢がなかったのだ。
母が亡くなってから1年以上が経ち、ヴァンは荷物をまとめて街へ出て、技術を学ぶ場所を探した。フォン夫人に別れを告げに行った。「そこに着いたら気をつけて。誰も信用しちゃダメよ、分かった?」とフォン夫人は言い、ポケットから10万ドンを取り出してヴァンの手に握った。「もう持っているの。受け取らないわ」とヴァンは彼女の手を払いのけた。「お父さん、受け取って。お金持ちになったら返して」とフォン夫人はヴァンの手に握らせようとしたが、そのまま立ち去った。ヴァンはフォン夫人の影を長い間見つめ、涙がこみ上げてきた。「今、母がいてくれたらなあ」
誰も彼女を知っていなかったので、ヴァンは街に足を踏み入れると、途方に暮れた。「ねえ、どこへ行くの?田舎から来たばかり?どこか行きたいなら、連れて行って」と、バスターミナルに立っていたバイクタクシーの運転手たちが熱心に誘い、からかってきた。「どこにも行かないわ。誰かが迎えに来てくれるのよ」とヴァンは答え、荷物をしっかりと抱えながら歩き去った。
彼女は通りを歩き回り、泊まる場所と裁縫の見習いを募集している店を探しました。通りの入り口で、見習い募集の看板を掲げた仕立て屋を見つけました。彼女は思い切って店に入り、仕事を依頼しました。
仕立て屋の店主は銀髪の中年男性だった。ヴァンは店に入るなり、尋ねられるのも待たずにこう言った。「お店で弟子募集の張り紙を見ましたので、仕立てを習わせてもらえないかと伺いに来ました。」
仕立て屋の店主はヴァンの周りを歩き回り、彼が歩くのを見ながら辺りを見回した。彼女は相変わらずハンドバッグを胸に抱え、店主の足取りを目で追う癖があった。しばらく尋ねた後、店主は再びヴァンの疲れ切った様子を見てため息をつき、そっけなく言った。「わかった、入って」
***
ヴァンは見習いとして採用され、仕立て屋から500メートルほどのところに部屋を借りた。3ヶ月後、彼女は故郷、故郷、そして村の入り口にあるホウオウボクの木が恋しくなった。ヴァンは上司に帰らせてほしいと頼み、バスに乗って故郷へ戻り、2日後に町へ戻る予定だった。
村に帰ってきた彼女を見て、フォン夫人は声をかけた。「都会の裁縫学校に通っていなかったの?どうして今ここにいるの?」
「とても家が恋しいです。数日帰ってきてください」とヴァンは答えた。
「まあ、とても会いたくて、たった今帰ったばかりよ」と、フオン夫人は続けた。「私の家に来て、お母さんにお線香をあげて。それから、今夜は私の家で夕食を食べなさい」。
ヴァンは頷き、立ち去った。家に戻ると、庭は彼女の姿が消えて何ヶ月も放置されていた。父親は相変わらず酔っぱらっていた。フォン夫人を通して、ヴァンは継母が夫と口論した後、実家に帰ったことを知った。ヴァンは父親に挨拶をし、返事が返ってくるかどうかは気にせず、家の中に入り、祭壇へ行き、母親のために線香をあげた。
「今帰ってきたばかり。お母さん、すごく会いたい」ヴァンは祭壇にお香を焚きながら囁いた。目に涙が浮かんでいた。ヴァンは家の中を歩き回ったが、服はそこら中に散らかっていた。台所も状況は変わらず、お椀や箸がそこら中に散らばっていて、誰も片付けようとしなかった。父親は片付けさえしなかった。継母は出て行ってしまい、父親は手に入るものを何でも食べていた。「どうして片付けるんだ?」と、庭のテーブルと椅子に寄りかかりながらヴァンは言った。
ヴァンは父親の言葉に耳を貸さず、涙を拭いて片付けを始めた。しばらくして、母親がいなくて寂しくてたまらないヴァンは、家族がこんなひどい状況になっているのを見るのも耐えられず、フォン夫人の家へと駆け出した。ヴァンの父親は涙を浮かべながら、彼女を見守っていた。
玄関に入るなり、ヴァンはフォン夫人を抱きしめ、大声で泣き出した。「お母さん、会いたいのに」とフォン夫人はすすり泣いた。フォン夫人はただ彼女を抱きしめ、背中をさすってあげた。「泣かないで。大丈夫よ。ここにいて、一緒に夕食を食べなさい」
その日の午後、ヴァンはフォン夫人の家に夕食を共にした。食事を終え、片付けを終えると、ヴァンは家に帰って寝たいと許可を求めた。
フォンさんの家から彼女の家まではそれほど遠くなかったが、人影はまばらだった。フォンさんは色々な考えを巡らせ、しばらくホウオウボクの木の下で座ってから家に帰ろうかと考えた。しかし、数歩歩いた後、考えが変わり、引き返して家に帰ろうとした。驚いたトラックの運転手は反応する間もなく…ヴァンは遠くへ投げ出された。意識を失う直前、どこかで誰かが話しているのが聞こえた…。
***
「ヴァンが事故に遭ったのよ」とフォン夫人は門を入るなり叫んだ。ヴァンの父親はそれでも気に留めなかった。フォン夫人は近づき、父親を揺さぶり、雷のような平手打ちを放った。「ヴァンが事故に遭ったのよ」
父親は突然目を覚まし、娘を見上げ、立ち上がって走り出した。走りながら娘の名前を呼んだ。フォン夫人は父親を追いかけた。二人が病院に到着した時には、ヴァンさんは既に救急室に入っていた。
「お医者さんは何て言ったの?」父親はヴァンを拾ってきた二人の若者に走って尋ねた。
「医者はまだ何も言っていません」と二人の若者は答えた。
彼はドアに駆け寄り、娘をじっと見つめた。しばらくして医師は、ヴァンに輸血が必要だが、彼女の血液型は珍しいと告げた。フォン夫人と二人の若者が検査したが、ヴァンと同じ血液型だったのは父親だけだった。しかし、父親は酔っていて、今は採血できない。医師は緊急で、病院の血液バンクにはその型の血液がないと言った。
「どうやって血を採ればいいんですか?どうしたらいいんですか?」父親は医師に何度も尋ねました。
「まず酔いを覚ましてください。血中アルコール濃度が高すぎると採血できません」と医師は答えた。
彼は庭の蛇口まで走り、ひたすら飲み続け、口をすすいでは吐き出した。フォン夫人の制止を無視して、まるで狂人のように振る舞った。アルコールを洗い流すために風呂にも入ったが、それでも効かなかった。フォン夫人は彼の酔いを覚まそうと、ホットレモネードを一杯買ってあげた。
「なんてことだ!酒のせいだ!ヴァン、お前をダメにしてしまった!」父親は病院の庭の真ん中で叫び、倒れ込んだ。
約1時間後、医師はヴァンに血液を採取し、輸血することができました。幸運にも間に合い、ヴァンは一命を取り留めました。父親は娘が起きるのを待ちながら、数晩眠れぬ夜を過ごしました。空が明るくなり始めた頃、フォン夫人はヴァンにお粥を持ってきました。
「家に帰って少し休んで、赤ちゃんは私に任せなさい」とフォン夫人はヴァンの父親に言った。しかし、父親は聞く耳を持たず、フォン夫人を押しのけた。「放っておいて」
ヴァンは目を覚ました。父親は娘の手を握りしめようと駆け寄り、目を赤くした。ヴァンは父親がこんなに弱っているのを見たことがなかった。ヴァンは父親を抱きしめた。フォン夫人は彼の傍らに立ち、彼を押しのけようとした。「まだこの子は弱っているのよ。そんなに強く抱きしめないで」
彼は子供のように泣いた。彼女の手を握り、酒をやめ、一生懸命働き、彼女を愛すると約束した。ヴァンは父親を見た。涙が彼女の頬を伝った。
***
午後。ヴァンが病院で横たわっていると、突然雷雨が降り始めた。ヴァンは何かが起こりそうな予感がした。彼女は立ち上がり、外を見た。空は渦巻き、雨が激しく降り注いでいた。しばらくして雨は止み、フォン夫人がお粥を持ってきた。外はまだ暗かった。
「村の入り口にあるホウオウボクの木に雷が落ちて、幹が真っ二つに折れて倒れたんです」と、ヴァンが横たわっていた場所に着くと、フォン夫人はすぐに告げた。その知らせを聞いたヴァンはショックを受けた。彼女はお粥の入った椀を脇に置き、ホウオウボクの木へ駆け寄ろうとしたが、フォン夫人に止められた。
退院の日、ヴァンは父親に連れられてホウオウボクの木の前を通り過ぎました。木の幹は枯れていました。村人たちは木の周りに集まり、木を崇拝する食事の準備をしていました。木は掘り起こされ、その場所に別のホウオウボクの木が植えられました。
ヴァンは父親に許可を求め、近づき、土をひとつかみすくい、新しく植えたホウオウボクの木の根元に植えました。
出典: https://baobacninhtv.vn/goc-phuong-dau-lang-postid421697.bbg







![[写真] ファム・ミン・チン首相が地方との政府オンライン会議を主宰](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/5/264793cfb4404c63a701d235ff43e1bd)
































































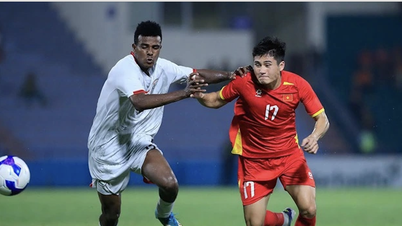





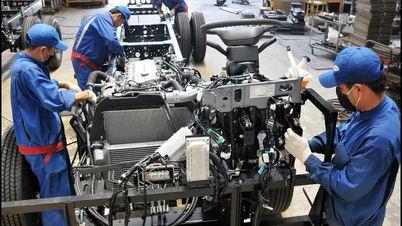


























コメント (0)