従来、飼料や種苗に多額の投資を要するソウギョやコイの養殖が主流でしたが、近年、省内の一部の養殖業者は、オオテナガエビの養殖モデルに取り組んでいます。オオテナガエビは、養殖が容易で、投資コストが低く、消費しやすく、 経済価値の高い水産物です。
低コストで育てやすい
ザップティンの旧正月を前に、私たちはレ・ニュー・クイン氏の巨大淡水エビ養殖モデルを視察するため、ノークアン県ランフォン村ダトゥオン村を訪れました。連日の厳しい寒さの後、今日は晴天となり、クイン氏の家族はクアンニン省の商人に中国への輸出用にエビを収穫する準備をしていました。ホアンロン川沿いの田んぼでは、何十人もの人々が叫び声を上げながら網を大きな音で引っ張り、エビの入った重たい籠が次々と岸に揚げられ、オーナーは大喜びでした。
クインさんはこう打ち明けた。「ここ数日、気温が低くて、家族はエビが一匹も浮いていないのを見てとても心配していました。全部死んでしまうのではないかと心配していましたが、今日はこんなにたくさん獲れて本当に嬉しいです。これは、オオテナガエビの生命力が強いことを証明しています。収穫も同じで、一度に全部を収穫する必要はありません。毎日漁をして大きなエビを捕まえて販売できますし、池に残ったエビも順調に成長しています。」

クインさんは長年養殖業に携わってきたが、これまではソウギョ、コクレン、オオムニ、コイなどの伝統的な魚類のみを放流してきた。近年、飼料価格の高騰により生産が芳しくなく、生産物は売れにくく、販売価格も低い。2022年には、少量のオオテナガエビを養殖池に放流する試験的な取り組みを始めた。その高い効率性を見て、今年はエビ養殖に特化することにした。1.6ヘクタールの面積に10万匹のエビの稚魚を放流した。これは、省農業普及センターが種子やふすまを提供し、養殖過程全体を通してエビの病気予防技術や世話について熱心に指導してくれたおかげだ。そのため、生存率は高く、養殖開始から6ヶ月で、エビは1kgあたり20尾の大きさに成長し、生産量は約2トンと推定されています。販売価格は1kgあたり20万ドンで、経費を差し引いた後、クイン氏は約2億ドンの利益を得ました。
「淡水エビの養殖は、飼育が簡単なだけでなく、手間がかからず、市販の飼料にあまり依存する必要がないという利点もあります。なぜなら、エビの栄養補給には、米ぬか、魚類、カタツムリなど、入手可能な飼料源を利用できるからです」とクイン氏は語った。

クイン氏と同様に、ディン・ヴァン・ティン氏も、ザーヴィエン県ザーミン村の低地水産養殖業を営むベテラン農家です。しかし近年、新型コロナウイルス感染症の流行と糠価格の高騰の影響で、生産は多くの困難に直面しています。成功するために何に転換すべきか、途方に暮れていました。そして、幾度となく検討を重ねた末、養魚池の一部をオオテナガエビの養殖に転用することを決意しました。
ティン氏は次のように語りました。「私はオオテナガエビの養殖を選びました。これは高付加価値の作物であり、生産市場も有利だからです。特に、天然の食料源を有効活用し、種子と飼料のコストは魚の養殖のわずか3分の1です。2022年には、ソウギョの池に15万個の種子を放流する実験を行いました。種子と飼料の総コストは約4,000万ドンでしたが、9,000万ドンを販売し、5,000万ドンの利益を上げました。今年は、ハイテク農業貿易振興センター(農業農村開発局)が信頼できる種子の供給元を提供し、体系的かつ科学的な農業技術を提供してくれたので、自信を持って5万個の種子を放流しました。現時点では収穫はありませんが、生産量と価値は昨年より確実に高くなるでしょう。」
複製の可能性
2024年の計画について尋ねられると、クイン氏とティン氏はともに、引き続きオオテナガエビを主力作物として養殖していくと答えた。同時に、地区内の他の養殖農家に技術移転を行い、消費を促進するためのエビ養殖協同組合を設立する基盤を整えていくと述べた。

専門家の視点から、ハイテク農業貿易促進センター(農業農村開発省)のファム・デュイ・フー副所長は次のように述べています。「オオテナガエビは栄養価が高く、美味しく、カロリーが低く、健康に非常に良い水産物であり、消費者に非常に人気があります。オオテナガエビやオオテナガエビほど飼育が難しくなく、淡水域でも汽水域でも元気に暮らすことができます。それだけでなく、オオテナガエビは輪作、稲との間作、単一栽培でも良好な結果を出しています。特に、これは雑食性の水産物であり、原生動物、多毛類、甲殻類、昆虫、軟体動物、藻類、有機性残渣など、自然界に存在する多くの食物を有効活用できるため、オオテナガエビの飼育コストは魚の飼育コストよりもはるかに低くなります。」
「淡水エビは、今後、特にノークアン郡、ジャーヴィエン郡、タムディエップ市などの稲作と魚作を一貫生産する地域で、自然生産、気候変動への適応、農家の収入の安定と増加を目指しながら、地域で開発される有望な養殖種である」とファム・ズイ・フー同志は意見を述べた。
しかし、オオテナガエビの養殖を成功させるために、ハイテク農業貿易促進センターは次のように推奨しています。農家は信頼できる生産施設から種苗を選び、池や畑に放す前に種苗を育てなければなりません。冬の寒さの影響を避けるため、毎年3月から10月が養殖のベストシーズンです。それでも冬越しをしたい場合は、2~3メートルの深さの池が必要です。池を改修する際は、雑魚や捕食魚などの害虫を駆除し、損失を防ぐことに細心の注意を払う必要があります。また、オオテナガエビには、栄養不足、水質悪化、底の汚れなどが原因で、藻類エビとエラが黒くなるエビという2つの基本的な病気があります。簡単な解決策は、水を交換し、石灰を追加し、栄養価の高い餌を増やすことです。
したがって、オオテナガエビのような新たな養殖の可能性を秘めた対象については、今後、各地域が適切なモデルを選択し、迅速に生産体制を整え、インフラに投資し、生産性と製品の品質を確保するための技術指導を行う必要があります。さらに、同様に重要な課題として、製品の生産量に対する解決策を講じることも挙げられます。なぜなら、現在、オオテナガエビのほとんどは国内市場で生鮮品として消費されており、輸出用の加工工場に持ち込まれていないからです。
文と写真:グエン・ルー
ソース
































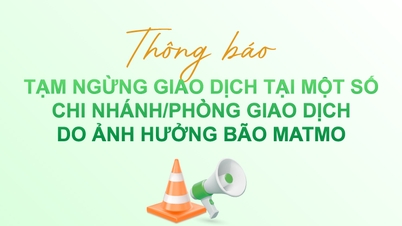
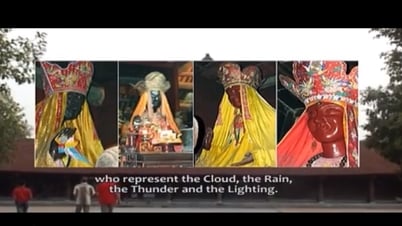























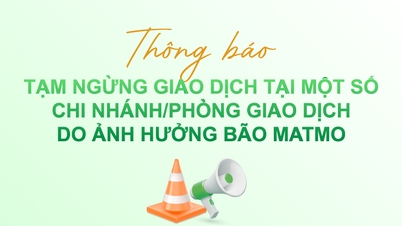






































コメント (0)