
日本とイタリアが共同開発した英国の次世代戦闘機モデル「テンペスト」
日経アジアによると、日本政府は6月20日、国産の防衛装備品を生産する際に米国と欧州の基準に従うことを求めるガイドライン案を発表した。
この案の目的は、維持費を削減し、日本の防衛企業のビジネスチャンスを増やすことだ。
この計画は、防衛装備品のセンサーやレーダー技術の高度化により、保守や部品交換のコストが増大していることを受けて策定された。
日本の2023年度の維持費は2兆円(148億ドル)と予想されており、これは防衛関連費の約30%に相当する。この数字は1990年には10%強だった。
装備コストの上昇は、運用寿命の延長につながります。例えば、自衛隊のF-15戦闘機は1981年から運用されています。装備が古くなると、安全検査や部品交換の頻度が増え、メンテナンスコストが高くなります。
これまで自衛隊が保有する装備品のほとんどは独自の規格に基づいて製造されており、他軍との部品交換が困難だった。2022年度版防衛白書によると、小ロット生産の複雑化がコスト上昇の一因となっている。
新たなガイドライン案は、国内企業に対し、北大西洋条約機構(NATO)加盟国やオーストラリアなどの同盟国と互換性のある装備品の開発・製造を求めている。
この計画は、日本がインド太平洋地域などで共同訓練を実施する関係者間で装備を標準化することを目的としている。
この新たな戦略は、価格を下げ、国産化を進めるだけでなく、部品の不足で装備品を移動できないといった事態を防ぎ、自衛隊の継続的な活動能力を高めることにもつながる可能性がある。
米国はウクライナ向け砲弾生産のため日本からTNT爆薬を購入するよう要請?
日本の防衛産業には、戦闘機や戦車の生産に携わる企業が1,000社以上、護衛艦の生産に携わる企業が8,000社以上ある。
現在、日本の規制では殺傷能力のある装備品の輸出が制限されています。しかし、政府は輸出拡大のため規制緩和を検討しており、統一規格は企業の販路確保に役立つでしょう。
[広告2]
ソースリンク


































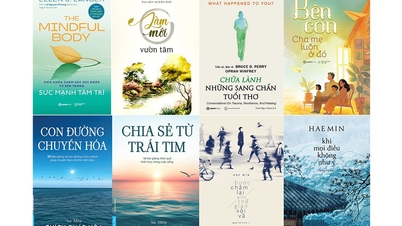























































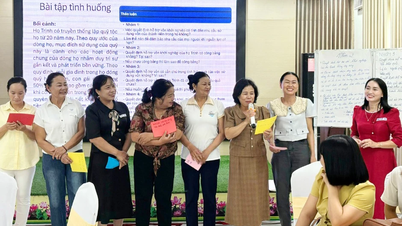


















コメント (0)