「女の子でも男の子でも、二人で十分」というスローガンは、ベトナムの人口政策において長年存在してきました。戦後の人口爆発という文脈において、人口政策と家族計画は「国家の課題」とみなされており、社会保障の負担を軽減し、持続可能な開発のための条件を整えるための戦略的課題となっています。
計画的な出産に向けたコミュニケーション、支援、サポート策を同時に適用した結果、ベトナムの出生率は大幅に低下し、人々の生活の質が向上し、医療と教育も大幅に改善しました。
 |
| 人口・家族計画局がバンメトート医科大学病院と共同で実施した、結婚前健康診断カウンセリングに関する研修。写真:ヴォ・タオ |
しかし、発展の新たな段階に入ると、その政策は徐々にその欠陥を露呈しました。ベトナムは現在、地域で最も急速に高齢化が進む国の一つであり、多くの地域で出生率は深刻なレベルまで低下しています。加えて、出生時の男女比の不均衡も深刻で、一部の地域では男児を産むことへのプレッシャーが依然として非常に強いのが現状です。また、多くの若い夫婦は、育児費用の高騰や経済的プレッシャーに直面しており、これ以上子供を持つことに意欲を失っています。
国会常任委員会が「各夫婦は1人か2人までしか子供を産むべきではない」という規定を削除する改正人口条例を正式に承認したことは、必要な変化である。国家は「人数管理」から支援・同行の役割へと移行した。夫婦は、自身の健康状態、経済状況、そして子育て能力と合致する限り、子供の数、出産時期、出産間隔を決定する完全な権利を有する。
ダクラク省は多くの少数民族が居住し、地域間の格差も大きいため、人口政策の変更に伴い難しい問題に直面しています。統計によると、近年のダクラク省の出生率は依然として全国平均を上回っており、これは人口増加の絶好の機会であると同時に、生活の質を確保する上での課題でもあります。
 |
| ヤ・ト・モット・コミューン保健所(エア・スップ郡)における人口問題対策と家族計画に関する広報活動。写真:ヴォ・タオ |
この分野で長年の経験を持つ専門家である、元人口・家族計画部(省人口・家族計画部)部長のH'Le Nie博士は、次のように述べた。「新たな政策は正しく、人々のエンパワーメントは不可欠です。しかし、広報活動が徹底されていなければ、政府は多くの子供を持つことを奨励していると誤解されやすいでしょう。これは制御不能な人口増加につながり、生活の質に影響を与え、医療制度、教育、貧困削減への取り組みへの圧力を増大させる可能性があります。」
草の根レベルの人口幹部は、「産児制限」の推進から、生殖に関する健康に関するアドバイスの提供、現代の家族計画の支援、特に出生前スクリーニングと新生児スクリーニングの推進といったより踏み込んだ役割を担うようになり、人々が責任ある選択を行えるよう支援しています。
保健局のグエン・チュン・タン副局長は、「『子どもを十分に産み、しっかり育てよう』というメッセージを通して、私たちは徹底したコミュニケーションを重視しています。『十分』とは、1人か2人という数ではなく、家族の実情と真の希望に合った数の子どもを持つことを意味します。関係部署や支部と積極的に連携し、特に僻地、へき地、少数民族地域において、地域社会におけるコミュニケーションやカウンセリングプログラムに人口問題を盛り込むよう努めます」と強調した。
地域間の大きな格差、高まる経済圧力、そして容易に変えられない伝統的な考え方といった状況において、新政策は、具体的で、同期的で、かつ綿密な支援策を伴って初めて真に効果を発揮します。各省当局はまた、中央政府に対し、遠隔地の道路網、学校、医療施設への投資強化、児童の授業料および医療費の免除・減額、貧困からの脱却と合法的な富裕層への成長を支援するための優遇政策と資金支援の強化といった具体的な支援策を講じるよう提言しました。
「子どもは1人か2人しか産んではいけない」という規制の撤廃は、現状を放置することを意味するのではなく、人口管理の考え方を行政的なものから人道的なものへと大きく前進させるものです。管理レベルから国民一人ひとりへの意識改革こそが、新たな政策が持続可能な形で社会に浸透し、新時代の幸福で主体的、そして文明的な家庭を築くための「鍵」となるでしょう。
出典: https://baodaklak.vn/xa-hoi/202506/tu-ke-hoach-hoa-gia-dinh-sang-dan-so-va-phat-trien-cf111c4/



![[写真] ルオン・クオン大統領がベトナム弁護士の伝統的な日の80周年記念式典に出席](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/09/1760026998213_ndo_br_1-jpg.webp)
![[写真] ト・ラム事務総長がキエンサン幼稚園とホーおじさんの名前が付けられた教室を訪問](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/09/1760023999336_vna-potal-tong-bi-thu-to-lam-tham-truong-mau-giao-kieng-sang-va-lop-hoc-mang-ten-bac-ho-8328675-277-jpg.webp)

![[写真] ファム・ミン・チン首相が、台風11号後の自然災害の影響克服に関する政府常任委員会の会議を主宰した。](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/09/1759997894015_dsc-0591-jpg.webp)




























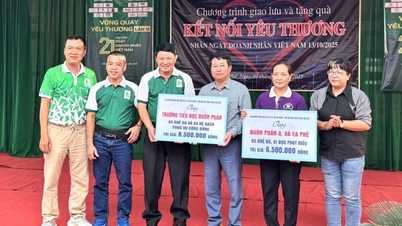















































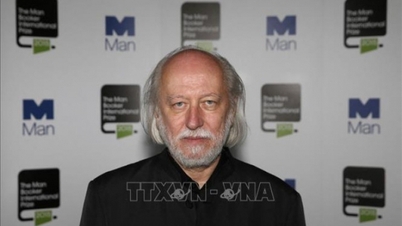
























コメント (0)