まず、各単語を分析してみましょう。
「比」という字は、殷の時代に甲骨文字に初めて登場しました。多くの研究者は、 「匕」という字が「スプーン」を意味することから、「比」は二人が並んで立っている、あるいは二本のスプーンが並んでいるように見えると考えています。また、「匕」は「腕」の原形ではないかと推測する学者もいます。 「匕」という字を二つ並べると「比」となり、二本の腕が並んでいることを意味します。このように、どのような解釈がなされても、 「比」の本来の意味は「隣り合う」ことにあると結論づけられます。
そこから、 「ti 」は「近い、または平行」 (詩経、周同)という理解につながり、さらに別の意味は「比較」 (周立、田観、能徳)となり、または「例」 (詩経、Boi Phong、Bac Phong)にまで広がり、「ti chieu」(比較)と「phong chieu」(利用可能なものに基づいて)になります...
「譬」は象形文字で、原義は「詩奴」 (例)、 「辣地」(詩、小野、小弁)であり、後に「知らせる、理解させる」 (後漢書)の意味で用いられるようになった。この字は秦以前の古典によく登場し、「如」(如)と合わせて用いられることが多い。例えば、「鹿を捕る」(例:鹿を捕る)など。左伝。襄公14年。
ここで「ví」という単語が出てきますが、これは「~として、~ならば、~と仮定して、~けれども」という意味の文字です。
「ヴィ」はベトナム語の漢語ではなく、3つの表記法を持つノム文字です。「𠸠」(純粋なノム文字)、「彼」と「啻」は中国語からの借用語です。トラン・テ・シュオンはかつて、次のようなノム詩を書きました。「ヴィ(啻)は、国家があなたに与える通行手当に等しい。それでは、あなたは月にどれだけのお金を稼ぐことができるだろうか?」(Vi Thanh Giai Cu Tap Bien) 。
次に「喻」という字があります。これは篆書で初めて『朔文街子』に登場した文字で、 「口」と「俞」 (川門を通過する船)という二つの文字が組み合わさっています。 「喻」の意味は、川門を通過する船は必ず申告し、川門の責任者による検査を受けなければならないということです。つまり、 「喻」の本来の意味は「説明する」「知らせる」であり、後に「意思疎通」「理解」へと意味が広がりました。そして、本稿では「例え、直喩、比較」という意味になります。
例(ひょう)は、例、例文、比較、比較とも呼ばれます。この用語は修辞技法の一種で、2つの事物間の類似性に基づき、事物Bを事物Aと比較するために使用されます。
今日では、隠喩には、隠喩(拡張比較)、倒置(逆比較)、寓意(証拠との比較)または対比(反対との比較)、仮説(連想との比較)、あるいは寓意(皮肉な比較)とサブ隠喩(暗示的な比較、言及)など、多くの形式があります...
「譬喻」は『荀子』に初めて登場する言葉で、戦国時代の費十子では、現代の例や例文と似た用法が使われていました。
「例えば、例えば、例えば」という言葉は互換的に使用できますが、私たちの意見では、「例えば」という言葉を使用するのが最も合理的です。 「例えば」は古い言葉になり、めったに使用されませんが、 「例えば」は「半分太って半分痩せた」言葉(名詞+漢語)であるためです。
また、「例えば、例えば、例えば」と同義またはほぼ同義の漢ベトナム語には、「cu le、hao ti、hao tu、huu nhu、kham tu、le nhu、nhu dong、thi nhu、ti phuong」などがありますので、ご注意ください。
出典: https://thanhnien.vn/ti-du-thi-du-vi-du-185250718215610368.htm


![[写真] ルオン・クオン大統領がベトナム弁護士の伝統的な日の80周年記念式典に出席](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/09/1760026998213_ndo_br_1-jpg.webp)

![[写真] ファム・ミン・チン首相が、台風11号後の自然災害の影響克服に関する政府常任委員会の会議を主宰した。](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/09/1759997894015_dsc-0591-jpg.webp)


![[写真] ト・ラム事務総長がキエンサン幼稚園とホーおじさんの名前が付けられた教室を訪問](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/09/1760023999336_vna-potal-tong-bi-thu-to-lam-tham-truong-mau-giao-kieng-sang-va-lop-hoc-mang-ten-bac-ho-8328675-277-jpg.webp)















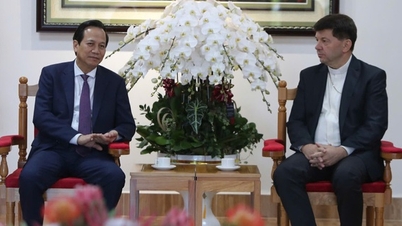









































































コメント (0)