丸い氷が入ったレモネードのグラスが、スプーンでゆっくりとかき混ぜるたびに、心地よくカランと音を立てて溶けていく。ナム・タン氏は時計を見ると10時を過ぎていた。約束の時間まではまだかなり時間が残っていた。
午前8時過ぎ、彼は小さなバッグを静かに抱え、車に乗り込み、色あせた緑のシャツの後ろに座った。すぐに強い塩辛い匂いが鼻を突いた。振り返らずとも、義理の娘の笑顔と夫を見つめる瞳がはっきりと目に浮かんだ。きっと二人は言い合いたかったのだろう。「老いとはこういうものなのか?」
 |
| AIイラスト |
老人は早く寝て早く起きる。若い頃ほど長く深く眠れない。だから彼は、どこかへ出かけなければならない時や用事がある時は、いつも数時間早く出発する。義理の娘に聞かれても、彼は何度も黙り込んでしまった。きっと老人性痴呆症だと思ったのだろう。
老いとは、単に皮膚に現れるシワのことだけではありません。70歳にもなって、幾重にも重なる記憶、憧れ、後悔、そして深い恐怖さえも、心の奥底に秘めていない人はどれほどいるでしょうか。
何か月も何年もかけて、かき立てられたり静寂に沈んだりする生命のあらゆる騒音は、独特の形と形状を持つ洞窟の鍾乳石と何か違うのでしょうか?
一緒に彫らず、指紋を残さず、傷跡や血痕を残さずにいなければ、あの鍾乳石に手を置くのはまるで部外者!だからこそ、人生には仲間が必要なのです。
冷たく酸っぱくて甘い水をスプーンですくい、口から喉を通り、胃へと流れ込む。ワイン通や紅茶通のように。店の外の木から黄色い葉が優しく揺れ、テーブルに落ちる様子を、まるで飼い主に馴染んだ子犬のように見つめていた。早くここを出て、ここに座って眺め、川の河口に浮かぶウキクサのように、自分の思いを漂わせていたいと思った。
人生において、特に男にとって、老いほど、それも伴侶のいない老いほど悲惨なものはない。日を追うごとに、彼はそのことを心の底から感じていた。若い頃、妻が傍にいてくれた時には想像もできなかったことだ!
この段階では、輝かしい過去があったにもかかわらず、それは通り雨のように過ぎ去っていった。すべてが記憶の霧の中に消え去っていた。毎日呼び合っていた昔の友人の名前、決して消えることはないと思っていた昔の顔。でも今は、時々思い出そうとしても思い出せない。
子供たちを心から愛しています。1人は何かあった時に何度か来てくれますが、もう1人は隣に住んでいて、一日中二言三言しか話しません。何を食べても、どこへ行っても、いつも子供たちのことばかり考えてしまいます。血圧は上がったり下がったり、膝や腰、関節は夜になると虫が出てくるように痛みます。
家の中をうろうろ歩き回り、妻の痕跡が残る家の中には、彼と彼の影だけが残っていた。妻はまるで落ち葉のように、冷たい地面に消えていった。
葉っぱは静かに去っていきます!静かに去っていきます!
まるでどこかで囁き声が聞こえたかのようだった。まるでオウムが人間の言葉を習得するかのように、自分の思考を真似て、彼自身にも聞こえるほど大きな声で囁く。いずれ最終列車で皆出発する。乗客が準備万端であろうと、まだしがみついているであろうと、旅は変わらない。出発の時が来たら、誰も抵抗できない。
彼はそれを信じていた。背中に巨大なムカデのように長く交差する手術痕を信じていたように。めまいも、そして一日三回、スズメバチの蛹ほどの大きさの錠剤を胃に詰め込むことさえ信じていた。
電話はテーブルの上に静まり返っていた。彼は一日に何度も手を伸ばし、まだ使えるか壊れているか確認した。今日も他の日と同じように音沙汰はなかったが、それは電源を切っていたからだ。娘2人と息子1人の3人の子供たちに電話をかけないと、丸一ヶ月も連絡が来ないこともあった。
週末になると、隣に住む次男は子供たちと妻を連れて外食したり遊んだりします。ベビーシッターは断るように誘いますが、彼らは聞き入れません。三男はもっと大変で、補習授業で忙しいんです!そう、彼も忙しいんです!都会に住む末娘は、ナムさんの命日には友達とヨガか何か自然の中で色鮮やかなシルエットの写真を撮ったりして忙しかったと言っていました。そう、彼女も忙しいんです。
彼は自分を慰めた。若い時は、やらなければならないことが山ほどある。まるで百本の見えない腕が常に自分を引っ張ろうとしているみたいに。親が最優先事項になることは滅多にない。
彼は枝に生えた若葉を見上げ、それから根元に悲しげに横たわる黄色い葉を見下ろした。今はまだ見えているけれど、明日か明後日には、あっという間に腐って泥に溶け込み、消えてしまう葉だ! 自分も幼い頃の子供たちのようだっただろうか、と思い出そうとした。
人の人生は、何十個ものかけらに砕かれたケーキのようなものだ。年老いた両親もその一つに過ぎない。乾いたかけらは隅に置き去りにされ、時には長い間触れられることなく、家の隅のテーブルや椅子のように静かに佇んでいる。人生があまりにも馴染み深いものになると、退屈になってしまう。
涙は永遠に流れ続けるだろうと、彼は自分に言い聞かせた。たとえほんの数分の電話での温かい会話でも、子供に何かを期待する親がいるだろうか?
子どもがどんな人間であろうと、どんな風にあなたを扱うとしても、子どもを身ごもり、産み、育てる人たちは、いつまでも尽きることのない愛情でその心の空虚を埋めてくれるでしょう。
テトにゴーヤの餡を作る女性たちのように、あるいは5月5日にバインセオを作る女性たちのように。餡の量がどれだけ多くても少なくても、最終的に出来上がるケーキが全て完璧であれば、多すぎても少なすぎても問題ないのです!
彼は通りの向こうに視線を向けた。色あせたカーテンの隙間から太陽の光が差し込み、彼の腕を熱くしていた。
大小さまざまなまだら模様の茶色い斑点や傷跡は、まるでファンタジー映画に出てくる生き物の群れのように、命を吹き込まれ、生き生きと踊り出しているようだった。
まるで、目に見えない、抗えない不思議な力が、彼の指をこすり合わせさせようと仕向けているかのように。まるで盲目の老人が知り合いを見つけるように。指は密集しており、彼が徐々に命綱を失いつつあることを如実に物語っていた。
しかし、なぜ、いつ、肉の上にあったのかを思い出すのは、まるで絡み合った泥沼に足を踏み入れた足のように、はっきりとは思い出せない! 人間の人生には不思議なほど良いところがある。昔の悲しい出来事は、記憶から忘れ去られてしまうことがよくある。あるいは、たとえ覚えていたとしても、それはただ漠然とした、癒えた傷跡に触れる手のように、時には目が素早く通り過ぎて、何も見えない。肌と同じ色で、痛くも痛くもない! 時々、もし滑らかで無傷の肉があったら、きっと何かが欠けていて、不快なんだろう、という奇妙な考えがどこかで浮かんでくる。
街のすぐそばにある小さな路地なのに、車がまるで織機のように行き交っている。道路は今や混雑しすぎている。かつてのタマリンド、サン、綿花畑はほとんど姿を消してしまった。
近い将来、人々が呼吸するために空気を売る日が来るのだろうか?それは誰にも分からない!まるで、彼の故郷の川沿いに住む人々が、生まれてこのかた、自分たちがまだ水に囲まれ、乾季にはバケツ一杯の水を使い切り、入浴や洗濯のために新鮮な水を買わなければならないとは、想像だにしていなかったかのようだ。
ある日、運河、川、湖、そして澄んだ青い水の真ん中に立つと、まるで足のかかとから頭のてっぺんまで小さな蛇が這っているかのような不気味な感覚に襲われるなんて、誰が想像しただろうか。ただ見ているだけで、舌先から脳裏に塩辛さと苦味が駆け巡る。ほんの数日前まで果物やサトウキビで満ちていた畑や庭園は、人生の終わりを迎える前に、岸辺は桑畑に変わるのだ。
彼はふと、また子供たちのことを考えた。子供たちは成長し、少しずつ変わっていく。そうでしょう?人の心にある親への愛は、時とともに変化するものなのでしょう?彼と妻は、世界中の多くの親たちと同じように、子供たちを産み、ゆりかごを作り、靴を買い、ミルクを買い、学校に通わせ、仕事を始め、結婚することなどを考えていたのです…
しかし、おそらく現実になるであろう、子供たちが私たちから永遠に完全に去ってしまうという考えに、誰も備えていないようです。その代わりに、時には打算的で冷たく、時には利己的な、奇妙な大人が現れるでしょう。
彼女が去ってから2年間、彼は毎日、鋭い石が脇腹を軽く切り裂くような孤独感を感じていた。しかし、それは次第に鋭い痛みへと変わっていった。毎朝、目が覚めてドアを開け、庭を眺めると、黄色い落ち葉が重なり合うのが見えた。まるで人里離れた、霞がかかったような場所で迷子になったような気分だった。人の顔も見えず、ましてや親戚の居場所も分からなかった。そして長い時を経て、ようやくここが故郷だと気づいた。
彼はぼんやりとほうきを手に庭を掃きながら、祖母が隣に立って掃きながら、夏なのにまだ子供たちを連れて帰っていない、子供たちの声以上に欲しいものはない、などと言っているのを想像していた。雨が降れば雨、晴れれば太陽、季節を感じさせない天気だった。庭のヤシの木はひどく乾いていて、心配そうにリに拾ってほしいと頼んだ。でないと、あちこちに倒れてしまうからだ。
そういうことだよ、おい。乾いてる時は触っただけで簡単に剥がれる。乾いてない時はちょっと汗をかかないと剥がれないけど、鎌が折れてもまだ毅然と立っているんだ!俺たちを育ててくれたこの木と大地を、俺たちが見捨てなければ、大地も見捨てないってことか、おいおい!
彼女の話し方――まるで歩道に落ちる雨粒のように、空気のように軽やかでありながら土を浸食し、揺らめく空間にココナッツの根をぽつんと立たせているような話し方。優しく、ゆっくりと動き、甘酸っぱく、とても女性的な話し方は、信じられないほど力強かった。あまりの力強さに、彼はある時、半分冗談、半分本気で、彼女と一緒にいるのはまるで鉢の中を這う蟻のようだったと笑った。彼女はこっそりと微笑み、その瞳は何年も前と同じように輝いていた。
トリウ・ヴェ
出典: https://baovinhlong.com.vn/van-hoa-giai-tri/tac-gia-tac-pham/202510/truyen-ngan-di-chuc-fb90557/






![[写真] 第1回世界文化祭でユニークな体験を発見](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/11/1760198064937_le-hoi-van-hoa-4199-3623-jpg.webp)





















![[写真] 朝鮮労働党創立80周年記念パレードに書記長が出席](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/11/1760150039564_vna-potal-tong-bi-thu-du-le-duyet-binh-ky-niem-80-nam-thanh-lap-dang-lao-dong-trieu-tien-8331994-jpg.webp)


































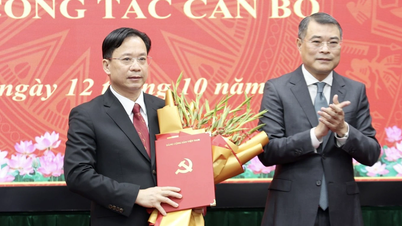








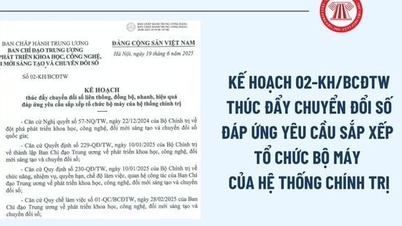























コメント (0)