中国、人材誘致のためVISA Kを導入
最近、米国政府はH-1Bビザの料金を値上げすることを決定しました。これは、米国で働くことを希望する高度なスキルを持つ労働者にとって非常に重要なビザです。新たな料金は10万ドルにまで引き上げられ、すべての企業や労働者にとって負担できる大きな障壁となっています。才能と資格を持つ人々でさえ、米国市場への扉が少し狭まったようです。
しかしそのわずか2日後、世界第2位の経済大国である中国は、科学技術分野の若手専門家向けに新たなビザ「VISA K」を導入すると発表しました。このビザは、才能ある人材が中国で学び、働くことを歓迎するためのものです。この新たな扉は、チャンスを求める労働者を歓迎するのでしょうか?そして、知力とインテリジェンスが経済力を生み出す時、中国への知力の流入を促進するのに十分なのでしょうか?
中国外務省は、Kビザが既存の12種類の一般ビザに追加されるとし、この政策は中国と海外の科学技術分野間の国際交流と協力を促進することを目的としていると付け加えた。
中国外務省の郭家坤報道官は、「中国と海外の科学技術専門家間の国際交流と協力を促進するため、中国はこの分野の若手専門家向けの一般ビザにKビザを追加することを決定しました。手続きに関する詳細は、在外中国大使館および領事館から近日中に発表されます」と述べた。
李強首相が8月に署名した決定によると、Kビザは10月1日から正式に発効する。他の種類のビザと比較して、Kビザは入国回数が多く、有効期限と滞在期間が長く、労働者をスポンサーする企業からの招待状の要件も緩和されている。
この新たな政策により、Kビザ保有者は教育、文化、科学技術、そしてスタートアップやビジネスにおける交流活動に参加できるようになります。これは、開発目標達成に貢献する若く質の高い人材をより多く誘致するための一歩と考えられています。
中国、ビザ政策を拡大
10億人規模の経済圏は、魅力的な投資先を目指し、人材の流入を歓迎し、経済発展と科学技術発展の基盤を築いている。中国は今後、外国人専門家の流入と長期滞在を奨励する環境を構築することを目指している。
近年、中国は旅行やビジネスの円滑化を図るため、ビザ政策を継続的に緩和してきました。昨年12月、入国管理局はトランジットビザ免除政策を改善し、滞在期間を10日間に延長し、適用範囲を24の省市に拡大しました。
中東は外国の専門家の誘致に努めている
中国だけでなく、中東も優秀な人材にとって新たな肥沃な土地として台頭しています。サウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタール、クウェートといった湾岸諸国は、国際的な人材や専門家の獲得に熾烈な競争を繰り広げており、実際に多くのグローバルな才能がこれらの国々に集まっています。
これらの国々は多くの優遇政策を実施しています。最も顕著なのは、例えばアラブ首長国連邦の「ゴールデンビザ」プログラムです。このプログラムは、人工知能、IoT、クラウドコンピューティングといった分野、あるいは医療、教育、環境、交通開発といった分野の専門家を多く惹きつけることに重点を置いています。これらはアラブ首長国連邦が注力すべき戦略的分野です。
サウジアラビアにも同様のプログラムがあり、国際的な人材を惹きつけるための「グリーンカード」とも言える制度があります。長期ビザ政策と安定した居住権に加え、税制、住宅支援、医療、家族福祉など、魅力的な優遇措置が数多くあります。
湾岸諸国が国際的な専門家の誘致を推進する戦略的な理由は数多くあります。例えば、外国人専門家が新たなスキル、技術、近代的な経営をもたらし、石油・ガス以外の産業の発展に貢献することで経済の多様化を図ることや、湾岸諸国が強みを持たない主要分野における優秀な人材の補充などが挙げられます。
さらに、国際競争力の強化、投資誘致、ガバナンスと国際基準の改善といった目標も掲げられています。これらの政策は、知識基盤型経済の構築、世界的な人材の誘致、そして多分野にわたる専門職コミュニティのための安定した生活環境の創出という、湾岸諸国の長期ビジョンを明確に示しています。
留学生は多くの選択肢に直面する
世界の知力の流れに変化が訪れようとしているのでしょうか?米国市場がもはや理想的な投資先ではなくなる時が来るのでしょうか?この問いに答えるには、もっと深く掘り下げる必要があるかもしれません。つまり、高等教育市場と大学院教育に目を向ける必要があるのです。
これまで、アメリカは常に留学生にとっての最大の留学先でした。しかし、依然として学費が高騰し、奨学金制度が逼迫し、政治的混乱も続く中、留学生たちは才能獲得をめぐる世界的な競争の中で、ドイツ、カナダ、中国といった他の選択肢を検討し始めています。
アメリカは数十年にわたり、留学生にとって最高の留学先であり続けています。2023年だけでも、アメリカの大学における留学生の割合は全学生数の約6%に過ぎないものの、その絶対数は100万人を超えました。インドが30万人以上でトップを占め、次いで中国が27万人以上、韓国とカナダが続きます。
高等教育はアメリカ経済にとって最大の輸出品の一つとなった。しかし、急速に変化する政治情勢によって、その伝統的な魅力は損なわれつつある。長らく学術交流の象徴とされてきた名門交換留学プログラムでさえも圧力にさらされ、奨学金は縮小している。
留学生のヴィンスさんは、「アメリカは依然として高等教育を受けるのに最適な場所の一つだと考えていますが、最近の情勢は留学生にとって懸念材料となっています。このような状況下では、私たちのような人にとってネガティブな反応を引き起こす可能性があります。しかし、私たちは前向きな姿勢を保ち、現状に適応し、現状の中で何ができるかを考えようとしています」と述べました。
一方、ドイツは新たな明るい兆しとして浮上している。「長年にわたり、留学生はドイツを留学先として選んできました。教育の質は高く、授業料はほぼ無料です」と、ケルンにあるドイツ経済研究所所長のウィド・ガイス・トーネ氏は述べた。
2023年には、ドイツの大学入学者総数の16%、つまり約50万人を留学生が占める見込みです。その魅力は、質の高い教育と開かれた移民政策にあります。ドイツへの留学生が最も多い国は、インド(約5万人)、中国(4万2000人以上)、そしてトルコ、シリア、オーストリアとなっています。
ドイツの大きな差別化要因は、優秀な人材の確保能力にあります。留学生の約45%が10年後もドイツで就労しており、これはOECD加盟国中で最も高く、カナダをも上回っています。この数字は、2030年までに約200万人の高技能労働者が不足するという、ドイツ経済の喫緊の課題を反映しています。こうした状況において、大学は単に学ぶ場であるだけでなく、労働市場への入り口でもあるのです。
しかし、ドイツやヨーロッパの労働市場、つまり学生にとっての産出量は、米国のものほど魅力的ではないと考えられています。
「米国は人材を容易に吸収できる柔軟な労働市場で知られています。対照的に、欧州は長らく硬直的で断片化された市場と見なされてきました。しかし、近年の改革により、ドイツをはじめとするEU諸国は、特に米国ではアクセスが難しい高度な研究分野において、徐々に追いつくことができました」と、OECD教育技能局長のアンドレアス・シュライヒャー氏は述べています。
米国における障壁がますます明確になるにつれ、留学の選択は慎重に検討すべき課題となっています。一方で、米国はブランド力と卒業後のキャリア機会の面で依然として大きな優位性を有しています。しかし一方で、ドイツ、カナダ、さらには中国からの留学機会の拡大は、単に学ぶだけでなく長期滞在を希望する学生を惹きつけています。
アメリカからヨーロッパ、中国、そして中東に至るまで、各国が才能ある人材に対して門戸を開いているか、それとも閉じているかが見て取れます。知力がどちらの方向を選択するかは、それぞれの経済における機会、生活環境、そして長期的な発展戦略に左右されます。
出典: https://vtv.vn/chat-xam-toan-cau-dich-chuyen-dau-se-thanh-diem-den-moi-100251003090138445.htm


![[写真]ビンミン小学校の生徒たちは満月祭を楽しみ、子ども時代の喜びを受け継いでいる](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/3/8cf8abef22fe4471be400a818912cb85)
![[写真] ファム・ミン・チン首相、嵐10号の影響克服に向けた会議を主宰](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/3/544f420dcc844463898fcbef46247d16)














































































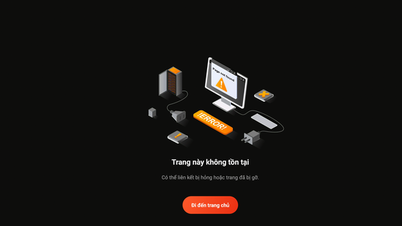























コメント (0)