「プロレタリア文学運動」の作家の中には政治的に活動的な者もいたが、大半はプロパガンダ作品を執筆していた。中には、日本の「使命」を謳い文句にし、芸術的価値の低い作品を書いた者もいた。
明治文学
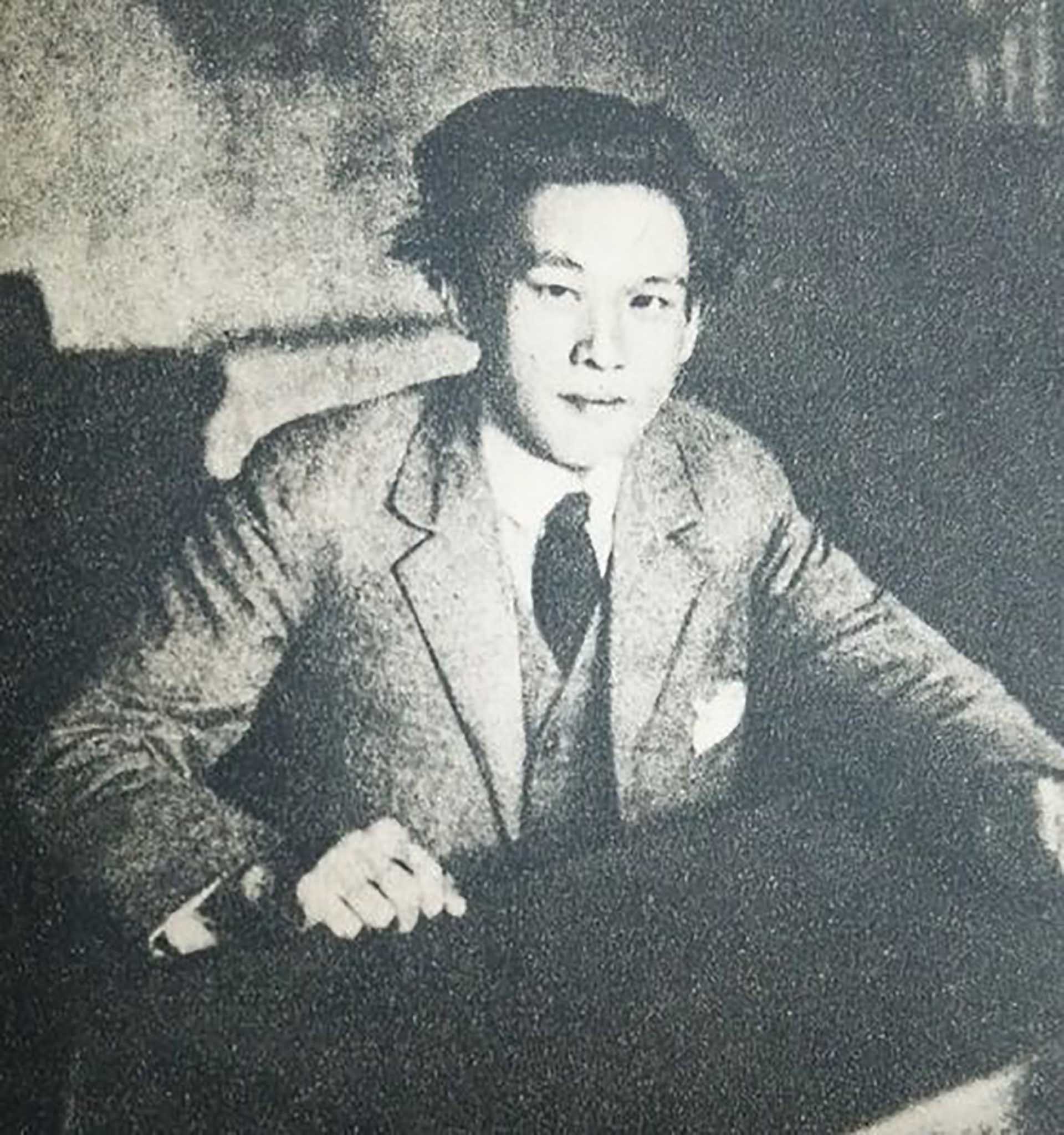 |
| 作家の横光利一。 |
横光利一(1898-1947)は、 「プロレタリア学派」や俗悪なリアリズムに反対し、「新しい感性」を志向したモダニストで実験的な作家であった。
彼は心理小説の巨匠であり、小説、短編小説、戯曲を執筆し、象徴主義的な物語で世に出た。フランス象徴主義とシュルレアリスム詩のイメージと視覚効果に魅了され、「ニュー・センセーショナリズム」派のリーダーを務めた。
1920年代半ば、彼の作風はより写実的になり、小説『上海』(1928-1931年)では、中国革命(1925-1927年)につながる1925年5月30日運動を描いている。
代表作には、 『都市』 (1916年)、 『日輪』(1923年)、 『蝿』(1923年)、 『春は馬車に乗って』 (1926年)(末期の病を抱える妻を描いた叙情的で繊細な物語)、人間の行動を支配する機械的原理という考えに対する執着が深まっていく様子を描いた『機械』 (1930年)、『時間』 (1931年)などがある。
常に作文理論に興味を持っていた彼は、1935年に発表した『純粋小説論』の中で、芸術的でありながら大衆的な小説の重要性を強調し、文壇で大きな反響を呼んだ。
1936年から半年間ヨーロッパに滞在し、その経験を基に未完の傑作『旅愁』 (1937-1946年)を執筆した。1930年代には、マルセル・プルースト(フランス)やジェイムズ・ジョイス(アイルランド)の影響を受けていた。
川端康成(1899-1972)は、小説、短編小説、詩を執筆しました。1968年にノーベル文学賞を受賞し、73歳で自殺しました。日本とイギリスで文学を学び、古典詩に情熱を傾けました。同時代の多くの作家とは異なり、彼は古き良き伝統に根ざした美的感覚を持っていました。彼は自らを「 世界を放浪する哀しき旅人」と称していました。
彼は物質主義に抗い、感情的な生活の波動を熱烈に擁護した。彼の作品は主に内面を表現しており、彼の態度は人生から疎外され、いくぶん保守的であった。
『伊豆の踊子』(1926年)は、学生と旅芸人の叶わぬ恋を描いた物語で、詩的な表現で印象派の作風を体現した最初の作品です。 『雪国』 (1935-1937年、1947年完成)は、雪の美しさ、四季の美しさ、女性、そして日本の北国の厳かな伝統を称え、川端康成の古典的傑作として、彼を日本を代表する作家の一人に押し上げました。
第二次世界大戦中、彼は孤独な生活を送っていました。 平和後は、茶の湯を舞台にした悲恋物語『千羽鶴』 (1949-1952年)、 『古都』 (1962年)、 『山の音』 (1954年)、 『眠れる美女』 (1961年)、 『美しさと悲しみと』(1965年)といった傑作を次々と発表しました。これは最後の長編小説となり、情熱と悲しい結末を描いた物語です。川端自身は、他の作品とは対照的な短編小説『囲碁の名人』(1951年)を最高傑作と考えていました。
この物語は、彼が毎日新聞で取材した1938年の囲碁対局を脚色したものです。秀才・秀斎にとって最後の対局となったこの対局は、年下の挑戦者に敗れ、1年後に亡くなりました。物語は表面的な、クライマックスの激戦へと至る闘いの記録に過ぎないように見えますが、第二次世界大戦における日本の敗戦のメタファーと解釈する読者もいれば、伝統と近代性の葛藤と捉える読者もいます。
「プロレタリア文学運動」の作家の中には政治的な側面を持つ者もおり、その多くはプロパガンダ作品を執筆した。中には日本の「使命」を謳う作品を書いた者もいたが、芸術的価値は低かった。典型的なプロレタリア作家には以下のような人物がいた。
1920年代の日本の「プロレタリア文学」運動の最初の作家である徳永直(1899-1958)は、作品『太陽のない街』(1928年)の中で、東京の労働者の絶望的で長期にわたるストライキを描写しました。
1945年の日本の敗戦後、彼は数人の作家とともに、戦前の社会主義文学団体の後継として新日本文学界(新日本文学会)を設立した。
葉山芳樹(1894-1945)は、貨物船の劣悪な労働環境を描いたプロレタリア小説『海に生きる人々』 (1926年)と、日本のプロレタリア文学の先駆ともいえる短編小説『娼婦』(1925年)で最もよく知られています。晩年は満州国の山岳建設現場で生活しました。
小林多喜二(1903-1933)は農家の生まれで、事務員として働き、非合法に共産党に入党しました。彼は多くの短編小説や小説を執筆し、プロレタリア階級の感情や思想を表現し、封建主義、地主、資本主義、そして軍国主義に対する日本の人々の闘争を浮き彫りにしました。
彼の代表作は『蟹工船』 (1929年)で、蟹漁師と船員たちの悲惨な生活を描いています。彼らは野蛮な船長に反抗しますが、失敗に終わります。小林は30歳で捕らえられ、拷問を受けて死にました。
プロレタリア作家への弾圧は早くから始まりました。投獄された者もいれば、方向転換を余儀なくされた者もいれば、筆を折られた者もいました。
[広告2]
ソース


![[写真] ファム・ミン・チン首相が、台風11号後の自然災害の影響克服に関する政府常任委員会の会議を主宰した。](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/09/1759997894015_dsc-0591-jpg.webp)
![[写真] ルオン・クオン大統領がベトナム弁護士の伝統的な日の80周年記念式典に出席](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/09/1760026998213_ndo_br_1-jpg.webp)
![[写真] ト・ラム事務総長がキエンサン幼稚園とホーおじさんの名前が付けられた教室を訪問](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/09/1760023999336_vna-potal-tong-bi-thu-to-lam-tham-truong-mau-giao-kieng-sang-va-lop-hoc-mang-ten-bac-ho-8328675-277-jpg.webp)
























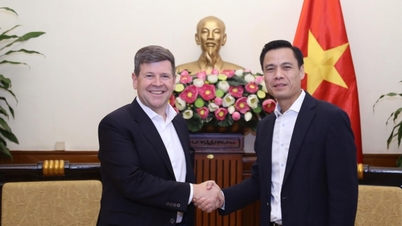















































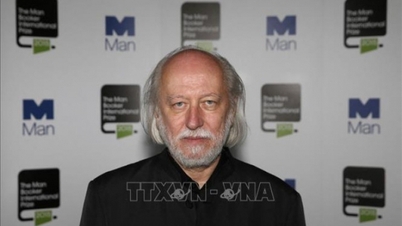


























コメント (0)