私は田舎で生まれ、田舎で育ち、田舎に住んでいますが、それでも故郷が恋しいです。故郷を恋しく思うのは、遠く離れた時だけ、というわけではありません。故郷を最も恋しくさせるのは、時とともに薄れていく思い出、馴染みのある光景、あるいは昔から変わらない風景なのに、そこに昔の人々がいない時です。
故郷の砂地の村道を覚えています。東の空に太陽が頬をピンク色に染め始めた早朝、母に呼ばれて畑へ行き、眠たそうに目を覚ましました。裸足で砂道を歩く感触は、なんとも素晴らしいものでした。柔らかく、白く、滑らかで、柔らかな砂粒が、小さな足の下で溶けていくようでした。足を砂にこすりつけ、砂が足全体を覆い、ひんやりとした砂の感触が肌に染み込むのが大好きでした。かつて学校へ通い、牛を放牧し、母に付き添って毎日市場へ行った村道は、今では記憶の中にしかありません。村の道はすべてコンクリートで舗装され、道は広くなりました。道の両側には家々が密集し、高い柵と閉じた門が建てられ、赤いハイビスカスの列や緑茶の列はなくなりました。長い間故郷を離れていた人たちは帰ってきて故郷の豊かさや美しさを褒め称え続けますが、私のような田舎の人間はどこか空虚で寂しい気持ちになります。
家の裏にある村の田んぼを覚えています。故郷は中山間地で、コウノトリが一直線に飛び交う田んぼも、どこまでも続く緑の田んぼもありません。でも、だからといって母の田んぼが嫌いなわけではありません。当時の私たちは、授業以外では家にいるよりも田んぼで過ごす時間の方が長かったのです。田んぼはまるで大きな友達のように私たちを守り、夢を育み、失敗を許してくれる存在でした。幼い頃から、母は私を田んぼに連れて行きました。担いだ棒の片側には稲の種籠、もう片側には私がいました。ニレの木陰で、私は一人でゆったりと遊び、時には古いニレの木の下で丸くなって眠りに落ちました。少し大きくなった頃、村の田んぼはかくれんぼや縄跳び、目くらまし遊びをする場所でした。村の煙の中から、夢を乗せた凧が大空へと舞い上がる場所でした。時々、昔を思い出しながら、私はよく村の田んぼへ出かけました。
私は静かに座り、土の強い湿った匂い、若い泥の刺激臭を吸い込み、ティとテオの黒い顔、日焼けした髪、人々に投げつけられて痛みを与えたとげのあるパンダンの葉で作られたボール、そして田舎の午後の陽気な笑い声を思い出しました。今、薄暗い午後、私は長い間待っていましたが、子供たちが遊びに駆け出そうと呼び合う声はもうなく、昔の遊びをする人ももういませんでした。私は長い間畑のそばに座っていました。私は黙っていました。畑もまた静かで、風が稲の波を揺らし、戯れる音だけが聞こえました。時折、突風が目に吹き込み、目が赤く刺すような痛みを感じました。
香りの良い庭のある祖母の茅葺き屋根の小屋を覚えています。子供の頃からずっと宝物だと思っていた庭で、故郷に帰るたびに都会に住む叔父の子供たちと一緒に誇らしく思っていた場所でした。夏には、畑から涼しく爽やかな風が吹き込んできました。祖母の子守唄を聞きながらぐっすり眠る少女の午後の夢の中に、カユプテの芳しい香りが風に運ばれてきました。熟したグアバ、ジャックフルーツ、ハヤトウリ、そしてシムの香りが、夏の午後のお昼寝に深く浸透していました。眠るのを拒み、兄弟の後をこっそりと裏庭に行き、グアバの木に登ってグアバを摘んだ午後もありました。グアバには、実が熟しているかどうかを確認するために兄弟たちがつけた爪痕がびっしりと残っていました。そして、眠れない午後が続いた結果、木から落ちた長い傷跡が膝に残りました。その傷跡を見るたびに、私は祖母を恋しく思い、仙人の庭がとても恋しくなりました。石の井戸、井戸の横に置かれた壺、祖母がいつも壺の口にココナッツの殻を置いていたことを思い出しました。いたずらをして遊んだ後、私たちは井戸に走って壺の水をすくい、お風呂に入り、顔を洗いました。また、その壺の横で、柄杓で水をすくい、祖母の髪にかけたのも覚えています。水を注ぎながら、「おばあちゃん、おばあちゃん、大好きだよ。あなたの髪は白い、雲のように白い」と歌っていました。おばあちゃんは亡くなり、子供の頃の庭もなくなり、井戸も、壺も、ココナッツの殻も過去へと流れていきました。古い庭の香り、祖母が髪を洗っていたムクロジの香りだけが、今でも私の中に残っています。
子供の頃の懐かしい音を思い出します。早朝のニワトリの鳴き声、母牛を呼ぶ子牛、午後の空の柱に鳥が絡まる音。暑い夏の正午に聞こえる「壊れたアルミ、プラスチック、鍋、フライパン、売ってくれる人いませんか?」という声は、母が古い自転車で高原まで塩を運び、それを売って私たちの養育費を稼いでいた頃を思い出させます。時折、夢の中で路地の入り口で鳴り響くベルと「アイスクリーム、アイスクリーム」という声が聞こえてきます。貧しい子供たちが、牛の世話をしながら集めた壊れたサンダル、割れた洗面器、金属くず、薬莢を持って、冷たくておいしいアイスクリームと交換するために走り出していたことを思い出します。
故郷を遠く離れた人が皆、故郷を恋しく思うわけではありません。故郷を最も恋しくさせるのは、時とともに薄れゆく思い出、見慣れた光景、あるいは昔のままの風景、しかしそこに昔の人々がもういないことです。私も村の道の真ん中を歩き、田園地帯の真ん中に座り、昔を懐かしく思い出します。祖母の台所から朝晩立ち上る煙が懐かしいです。「明日は今日から始まる」と知りながら、故郷はこれからも大きく変わっていくでしょう。ただ、誰もが心の中に、遠く離れても帰りたくなる場所、思い出し、愛せる場所、幸せの時に帰りたくなる場所、辛い時に帰りたくなる場所を持ち続けてほしいと願うばかりです。
(Lam Khue/tanvanhay.vn による)
[広告2]
出典: https://baophutho.vn/giua-que-long-lai-nho-que-227647.htm







![[写真]ビンミン小学校の生徒たちは満月祭を楽しみ、子ども時代の喜びを受け継いでいる](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/3/8cf8abef22fe4471be400a818912cb85)
![[インフォグラフィック] 3ヶ月間の「国の再編」後の注目すべき数字](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/4/ce8bb72c722348e09e942d04f0dd9729)





























![[写真] ファム・ミン・チン首相、嵐10号の影響克服に向けた会議を主宰](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/3/544f420dcc844463898fcbef46247d16)
































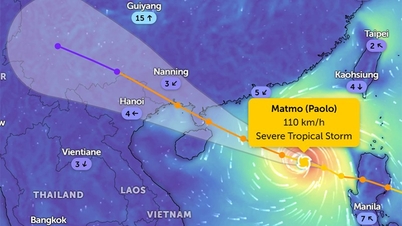


![[インフォグラフィック] 3ヶ月間の「国の再編」後の注目すべき数字](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/4/ce8bb72c722348e09e942d04f0dd9729)
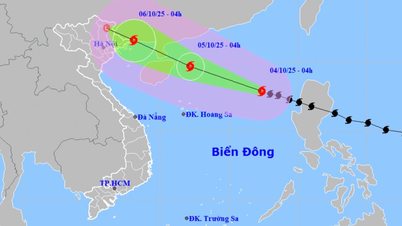









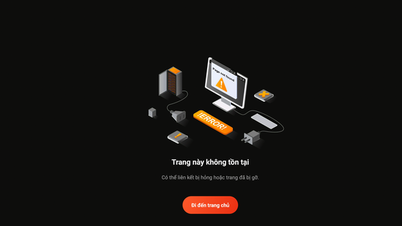




















コメント (0)