肝生検は原因不明の病変を診断・評価し、良性か悪性かに分類するのに役立ちます。
ハノイのタムアン総合病院消化器科長のヴー・チュオン・カーン医師は、肝生検は血液検査や画像診断では原因が正確に特定できない肝臓疾患や病変の良性か悪性かを診断するために行われると語った。
肝生検は、病気の重症度(病期)と進行速度(分類)を判定し、がんの種類、病期、グレード、そして予測される治療結果(予後)に基づいた治療計画を立てるのに役立ちます。肝臓に腫瘍がある場合、肝生検を受けることができます。
カーン博士によると、超音波や肝臓の弾力性の測定などの非侵襲的な方法は大きく進歩したが、脂肪肝、慢性肝炎、肝硬変、肝臓がんなど多くの肝疾患の診断と判別には、依然として生検が「ゴールド」スタンダードとなっている。
この方法は、アルコール性肝疾患、自己免疫性肝炎、肝細胞癌、ホジキンリンパ腫、原発性胆汁性胆管炎、中毒性肝炎、B 型または C 型ウイルス性肝炎などの病気の特定の原因や種類を医師が特定するのに役立ちます。
肝生検の適応症は多岐にわたりますが、主に次の 3 つのカテゴリに分類されます。
診断:肝生検は診断が困難な場合に重要です。例えば、肝機能検査異常と自己免疫血清学的検査陽性を伴う肥満患者において、自己免疫性肝炎と非アルコール性脂肪肝炎を鑑別する場合などです。
肝生検は、自己免疫性肝炎や原発性胆汁性胆管炎などの重複症候群がある場合に有用です。また、肝移植直後の肝機能検査異常の評価にも用いられます。胆管癌と肝細胞癌の鑑別が困難な場合、肝生検が行われることがあります。
予後:肝生検は、肝硬変、ヘモクロマトーシス、ウイルス性肝炎に進行する非アルコール性脂肪性肝疾患など、いくつかの疾患の予後ツールとして使用できます。
治療:ステロイドや免疫調節剤で治療を受けている自己免疫性肝炎の患者にとって、肝生検は重要です。

ヴー・チュオン・カーン医師が患者を診察している。写真:病院提供
現在、一般的に行われている肝生検には、超音波ガイド下経皮生検と超音波ガイド下経皮生検の3種類があります。生検のプロセスは、針が肝臓に素早く出し入れされるため、わずか数十秒で完了します。
経頸静脈生検:医師は患者の首の側面に麻酔薬を塗布します。次に、小さな切開を加え、柔軟なプラスチック製のチューブを頸静脈と肝臓上部の静脈に挿入します。医師はチューブに生検針を刺し、1つまたは複数の肝臓サンプルを採取します。この処置は、肝臓の凝固機能が低下している場合でも安全に行うことができます。
腹腔鏡下生検では、患者は全身麻酔を受けます。医師は患者の腹部に1カ所または複数の小さな切開を入れ、そこから特殊な器具を挿入して小型カメラを用いて組織サンプルを採取します。器具と肝組織サンプルを採取した後、切開部は縫合されます。この方法は単独で行われることは稀で、腹腔鏡手術中に肝生検と組み合わせて行われることがよくあります。
カーン医師は、サンプル採取後、病理医が肝組織を評価すると付け加えた。肝細胞の大きさや形状、その他の要素に基づいて、生検によって肝障害の原因が良性か悪性かを特定することができる。
エメラルド
| 読者はここで消化器疾患に関する質問をし、医師が答えます |
[広告2]
ソースリンク


![[写真]ビンミン小学校の生徒たちは満月祭を楽しみ、子ども時代の喜びを受け継いでいる](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/3/8cf8abef22fe4471be400a818912cb85)




![[インフォグラフィック] 3ヶ月間の「国の再編」後の注目すべき数字](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/4/ce8bb72c722348e09e942d04f0dd9729)



























![[写真] ファム・ミン・チン首相、嵐10号の影響克服に向けた会議を主宰](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/3/544f420dcc844463898fcbef46247d16)







































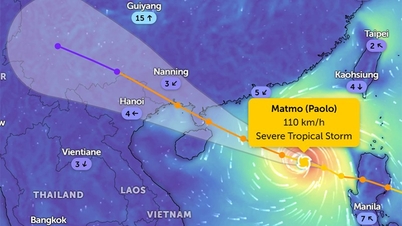








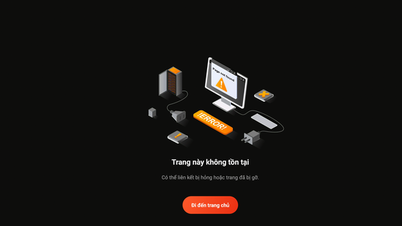




















コメント (0)